「木造と鉄骨はどっちがいいの?」
マイホーム作りで、その構造選びは重要となってきます。
「木造は温かいけど、地震が心配…」
「鉄骨は頑丈そうだけど、コストが高い…」
そんな疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。
木造と鉄骨にはそれぞれに魅力があり、どちらが良いかは、あなたのライフスタイルや価値観、そして予算によって大きく異なります。
今回この記事では、木造と鉄骨住宅のメリット・デメリットを比較し、後悔しないためのハウスメーカー選びのポイントも紹介していきます。
これから家づくりを始めようと考えている人は、ぜひこの記事を最後まで読んでみてくださいね。
本文に入る前に、これから家づくりを考えている人や、現在進行形でハウスメーカー選びを進めている人に、後悔しない家づくりのための最も重要な情報をお伝えします。
早速ですが、質問です。
家づくりで一番大切なこと、それはなんだと思いますか?
おそらく間取りや予算、建てる場所などと考える人も多いかもしれませんね。
ですが実は、家づくりで最も大切なことは「気になっているハウスメーカーのカタログを、とりあえず全て取り寄せてしまうこと」なんです。
カタログを取り寄せずに住宅展示場に行き、営業マンの言葉巧みな営業トークに押されて契約を結んでしまうのは最悪なケース。
住宅展示場に行ってその場で契約をしてしまった人の中には、「もしもカタログを取り寄せて比較検討していたら、同じ間取りの家でも300万円安かったのに・・・」と後悔する人が本当に多いんです。
このように、もう少し情報収集をしていれば理想の家をもっと安く建てられていたのに、場合によっては何百万単位の損をして後悔してしまうこともあります。
だからこそ、きちんとした情報収集をせずにハウスメーカーを選ぶのは絶対にやめてください。
そんなことにならないようにハウスメーカーのカタログを取り寄せて比較検討することが最も重要なんです。

そうは言っても、気になるハウスメーカーはたくさんあるし、気になるハウスメーカー全てに連絡してカタログを取り寄せるなんて、時間と労力がかかりすぎるよ・・・
そう思う人も少なくありません。
そもそもどのように情報収集をしたら良いのかわからないという人もいるでしょう。
そんなあなたにぜひ活用してほしいサービスが、「ハウスメーカーのカタログ一括請求サービス」や「専門家に実際に相談してみること」です!
これらのサービスを活用することで、何十倍もの手間を省くことができ、損をするリスクも最大限に減らすことができます。
中でも、不動産業界大手が運営をしている下記の3つのサービスが特におすすめです。
|
東証プライム上場企業「LIFULL」が運営をしているカタログ一括請求サービスです。厳しい審査を通過した全国の優良住宅メーカーからカタログを取り寄せることが可能です。特にローコスト住宅に強いため、ローコスト住宅でマイホームを検討している人に非常におすすめです。 不動産のポータルサイトとしておそらく全国で最も知名度のあるSUUMOが運営しています。全国各地の工務店とのネットワークも豊富。住宅の専門家との相談をすることが可能で、住宅メーカー選びのみならず、家づくりの初歩的な質問から始めることが可能です。「何から始めたら良いのかわからない」と言う人はSUUMOに相談することがおすすめです。 上場企業でもあるNTTデータが運営しているサービスです。大手ということもあり、信頼も厚いのが特徴です。全国各地の大手ハウスメーカーを中心にカタログを取り寄せることができます。また、理想の家づくりプランを作ってもらえるのも嬉しいポイントです。 |
上記の3サイトはどれも完全無料で利用できる上、日本を代表する大手企業が運営しているため、安心して利用することができます。
また、厳しい審査基準で問題のある企業を事前に弾いているため、悪質な住宅メーカーに依頼してしまうというリスクを避けることも可能です。
正直言って、こちらの3サイトならどれを利用しても間違いはないでしょう。
また、どれを利用するか迷ったら、
- ローコスト住宅メーカーや大手ハウスメーカーを検討中:LIFULL HOME'Sでカタログ請求
- 工務店をメインで検討中:SUUMOカウンターで相談
- 資金計画や土地探しも相談したい:家づくりのとびら
というふうに使い分けてみるのもおすすめです。
そのほかに、SUUMOも無料カタログの一括請求サービスを提供しています。
こちらも無料なので、ぜひ利用してみることをおすすめします。
もちろんどのサービスも無料なため、全て活用してみるのもおすすめです。
後悔のない家づくりのため、1社でも多くの会社からカタログを取り寄せてみてくださいね!
\メーカー比較で数百万円得することも!/

【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる≫

【プロと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
家づくりで後悔しないために、これらのサービスをうまく活用しながら、ぜひあなたの理想を叶えてくれる住宅メーカーを見つけてみてください!
それでは本文に入っていきましょう!
木造住宅を徹底解剖

木造住宅は、柱や梁などの主要構造部に木材を使用した住宅です。
日本の気候風土に適しており、古くから多くの人々に選ばれてきました。
木造建築の歴史は古く、縄文時代まで遡ることができます。
日本の高温多湿な気候風土において、木材は調湿性に優れ、快適な居住空間を提供してきました。
現在でも、日本の住宅の大部分を占める木造住宅は、様々な工法で建てられています。
木造住宅の工法を紹介
ここでは木造住宅でよく使用される工法を紹介します。
木造軸組構法(在来工法)
木造軸組構法は、日本で最も一般的な木造建築の工法です。
柱や梁などの構造材を金物で接合して建物を支える構造で、設計の自由度が高く、増改築やリフォームがしやすいというメリットがあります。
また、木材の調湿作用により、室内環境を快適に保つことができます。
プレカット技術の進化により、工期の短縮やコスト削減にも繋がっています。
ツーバイフォー工法
ツーバイフォー工法は、北米で発達した木造建築の工法です。
2インチ×4インチの規格木材を枠組みのように組み合わせて壁や床を構成し、面で家を支えるのが特徴です。
高い耐震性と気密性を誇り、地震や台風などの自然災害に強い家づくりが可能です。
SE構法
SE構法は、構造計算に基づいた設計・施工を行う木造建築の工法です。
強度の高い集成材を使用し、接合部には独自の金物を使用することで、高い耐震性能を実現しています。
木造でありながら、大空間や自由な間取り設計が可能で、デザイン性の高い住宅を建てることができます。
木造住宅のメリット
木造住宅のメリットとして以下のポイントが挙げられます。
温もりと快適性
木材は熱を伝えにくい性質を持ち、冬は暖かく、夏は涼しい快適な空間を実現します。
また、湿気を吸収・放出する調湿性があり、結露やカビの発生を抑えます。
地震に強い
木造住宅は、木材の持つ柔軟性と軽さで地震の揺れを吸収し、倒壊を防ぎます。
これは「粘り強さ」とも表現され、地震エネルギーを効果的に分散させることで、建物の損傷を軽減します。
耐震技術の進化も目覚ましく、耐震等級の高い住宅も増えています。
特に、制震ダンパーなどの制震装置を導入することで、地震時の揺れをさらに抑制し、建物の損傷リスクを低減することができます。
コストを抑えやすい
一般的に、木造住宅は鉄骨住宅に比べて建築コストを抑えやすい傾向があります。
また、固定資産税も鉄骨住宅に比べて安いです。
これは、材料費や工期の違いによるものです。
ただし、使用する木材の種類やグレード、設備の仕様などによって費用は変動します。
国産材と輸入材では価格差があるため、予算に合わせて選択することが重要です。
火災に強い
木材は、燃焼時に表面が炭化層を形成し、内部まで火が届きにくいため、倒壊までの時間を稼ぐことができます。
この炭化層が断熱材のような役割を果たし、木材の強度低下を遅らせる効果があります。
環境に優しい
木材は再生可能な資源であり、二酸化炭素を吸収・固定化するため、環境負荷を低減します。
適切に管理された森林から伐採された木材を使用することで、持続可能な社会の実現に貢献できます。
木造住宅のデメリット
一方で下記のようなデメリットもあります。
シロアリ対策の必要性
木造住宅は、シロアリの食害を受ける可能性があります。
定期的な点検や防蟻処理が重要です。
近年では、効果の持続する防蟻処理も開発されており、メンテナンスの手間を軽減できます。
職人の腕による品質の差
木造住宅は、職人の技術によって品質に差が出やすい傾向があります。
実績のある信頼できる施工会社を選びましょう。
施工会社の実績や評判をしっかり確認し、現場見学や担当者との面談を通じて、信頼できるパートナーを見つけることが大切です。
防音性が低い
木造住宅は一般的に鉄骨住宅に比べて防音性が低いと言われています。
二重窓や断熱材、遮音シートなどで対策をしましょう。
壁の構造や窓の種類などを工夫することで、防音性を向上させることができます。
間取りの制限
木造住宅は、耐震性を確保するために柱や壁が多く必要となるため、間取りの自由度が低い場合があります。
木造軸組工法を選ぶことで、比較的自由度の高い間取りを実現できます。
設計段階でしっかりと検討することで、希望に沿った間取りを実現できるでしょう。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
鉄骨住宅の徹底解剖

鉄骨住宅は、柱や梁などの主要構造部に鉄骨を使用した住宅です。
強度が高く、広い空間を実現しやすいのが特徴です。
鉄骨には、軽量鉄骨と重量鉄骨があり、住宅で使用する場合は主に軽量鉄骨が用いられます。
工場で精密に加工された鉄骨を使用するため、品質が安定しているというメリットもあります。
鉄骨住宅の工法を紹介
ここでは鉄骨住宅でよく使用される工法を紹介します。
軽量鉄骨ブレース工法
軽量鉄骨ブレース工法は、軽量鉄骨造の中でも一般的な工法です。
ブレースと呼ばれる斜材を柱と梁に設置することで、建物の強度を高めています。
コストパフォーマンスに優れ、耐震性も確保できることから、多くの住宅で採用されています。
ブレース材は、地震や風などの外力に対して抵抗する役割を果たし、建物の安定性を保ちます。
軽量鉄骨ラーメン工法
軽量鉄骨ラーメン工法は、柱と梁を剛接合することで、構造体全体で建物を支える工法です。
ブレース材を使用しないため、壁の配置に制約がなく、より自由度の高い間取り設計が可能です。
大空間のリビングや吹き抜けなど、開放的な空間を実現したい場合に適しています。
重量鉄骨造
重量鉄骨造は、大型のH形鋼などを用いた工法で、高層ビルやマンションなどの大型建築物に用いられます。
非常に高い強度と耐久性を持ち、大空間を実現することも可能です。
一般住宅で用いられることは少ないですが、3階建て以上の住宅や、特殊なデザインの住宅を建てる際に検討されることがあります。
鉄骨住宅のメリット
鉄骨住宅のメリットとして以下のポイントが挙げられます。
広い空間を実現
鉄骨は強度が高いため、柱と柱の間隔を大きく取ることができ、開放的な空間を実現できます。
大スパンの構造が可能になるため、リビングや吹き抜けなど、広々とした空間をデザインしやすいのが魅力です。
間仕切り壁が少ないため、ライフスタイルの変化に合わせて間取り変更もしやすいというメリットもあります。
災害に強い構造
鉄骨住宅は、高い耐震性を持ち、地震に強い構造です。
また、耐火性にも優れており、火災保険料が木造住宅より安い場合があります。
鉄骨は不燃材であるため、火災時の延焼リスクを低減できます。
耐火被覆を施すことで、さらに耐火性能を高めることができます。
品質が安定
鉄骨は工場で生産されるため、品質にばらつきが少なく、安定しています。
天候に左右されることなく、高精度な部材を製造できるため、工事期間の短縮にも繋がります。
工場で品質管理が徹底されているため、高い精度と均一性を確保できます。
シロアリに強い
鉄骨はシロアリの食害を受けないため、メンテナンスの負担を軽減できます。
木造住宅のように定期的な防蟻処理は不要です。
メンテナンス費用を抑えることができるため、長期的なコスト削減にも繋がります。
リフォームしやすい
軽量鉄骨造では、間仕切り壁が構造耐力壁ではないため、比較的容易に間取り変更が可能です。
ライフスタイルの変化に合わせて、柔軟に間取り変更できるのは大きなメリットです。
家族構成の変化やライフスタイルの変化に合わせて、自由に間取りを変更できるため、長く快適に暮らすことができます。
火災保険料が安い
木造住宅に比べて火災保険料が安い傾向にあります。
これは、鉄骨造の耐火性の高さによるものです。
火災保険料が安いことは、ランニングコストを抑える上で大きなメリットとなります。
鉄骨住宅のデメリット
一方で下記のようなデメリットもあります。
コストが高い
鉄骨住宅は、木造住宅に比べて建築コストが高くなる傾向があります。
地盤改良が必要な場合もあり、固定資産税も高くなる場合があります。
材料費や加工費が高いため、建築費全体が上昇する傾向があります。
鉄骨の価格変動も建築費に影響を与える可能性があります。
地盤補強が必要な場合がある
鉄骨住宅は重量があるため、地盤が弱い場合は地盤改良が必要になることがあります。
地盤改良工事が必要な場合は、別途費用が発生します。
地盤改良費用は、地盤の状態や改良方法によって大きく異なります。
断熱性対策が重要
鉄骨は熱を伝えやすいため、断熱対策が重要になります。
外断熱は気密性が高く、内断熱はコストを抑えやすいというメリットがあります。
適切な断熱材を選択し、施工することで、快適な居住空間を実現できます。
断熱材の種類や厚さによって、断熱性能は大きく変わります。
錆びる可能性がある
鉄は錆びる可能性があるため、防錆処理が必要です。
定期的なメンテナンスで防錆処理を行うことで、建物の寿命を延ばすことができます。
防錆処理には、塗装やメッキなど様々な方法があります。
間取りが変更しにくい
軽量鉄骨造でも、ブレース(筋交い)がある場合、間取り変更の際に制約が生じることがあります。
ブレースの位置を移動したり、構造計算をやり直したりする必要が生じるケースもあります。
ラーメン工法であれば、間取り変更の自由度が高くなります。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
地震にはどっちが強いのか
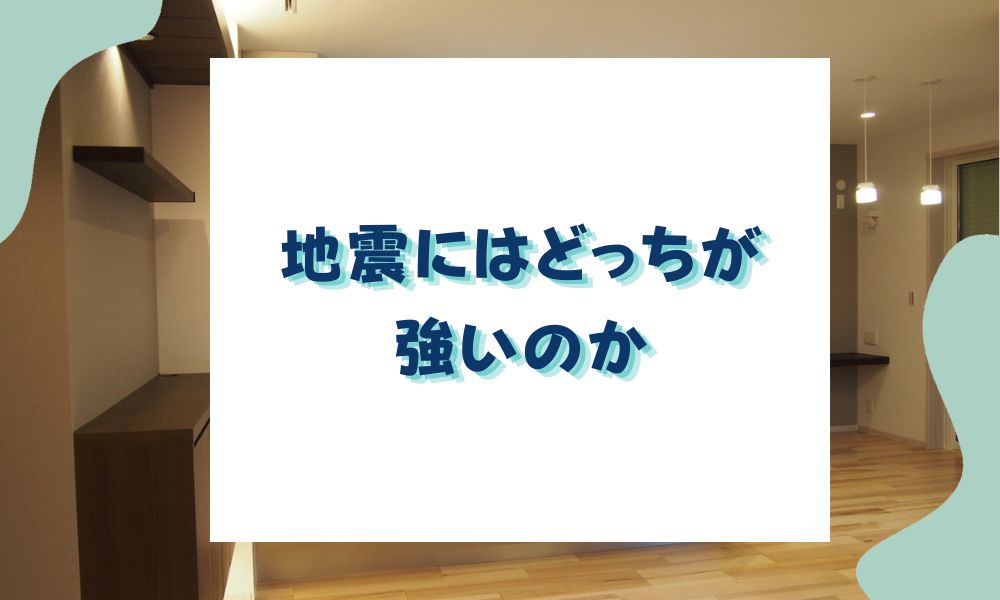
「木造は地震に弱い」「鉄骨は地震に強い」といった認識は、必ずしも正しいとは言えません。
木造、鉄骨ともに、建築基準法で定められた耐震基準を満たす必要があります。
耐震性を評価する上で重要な指標となるのが「耐震等級」です。
耐震等級は、1から3まであり、数字が大きいほど耐震性能が高いことを示します。
- 等級1は建築基準法で定められた最低限の耐震性能を満たすレベル
- 等級2は等級1の1.25倍
- 等級3は等級1の1.5倍の耐震性能
とされています。
建物の構造種別だけで耐震性を判断するのではなく、耐震等級を確認することが重要です。
住宅性能表示制度を利用すれば、耐震等級だけでなく、劣化対策等級や維持管理対策等級なども確認することができます。
木造
木造住宅の耐震性を高める技術として、近年注目を集めているのが「制震」と「免震」です。
制震装置は、地震のエネルギーを吸収することで、建物の揺れを軽減する効果があります。
オイルダンパーや粘弾性ダンパーなど、様々な種類の制震装置が開発されています。
一方、免震装置は、建物を地面から切り離すことで、地震の揺れを建物に伝わりにくくする技術です。
免震装置を設置することで、建物へのダメージを大幅に軽減することができます。
これらの技術は、木造住宅の耐震性能を飛躍的に向上させ、地震に対する安心感を高めてくれます。
鉄骨
鉄骨は、引っ張る力に強い「引張強度」と、圧縮する力に強い「圧縮強度」の両方に優れており、地震の揺れに対して粘り強く抵抗します。
鉄骨造の建物は、地震時に変形することでエネルギーを吸収し、倒壊を防ぎます。
しかし、鉄骨造だからといって必ずしも地震に強いとは限りません。
適切な構造計算と施工が不可欠です。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
木造と鉄骨のコスト比較|坪単価や費用

住宅の建築費用は、構造だけでなく、使用する材料、設備のグレード、建物のデザイン、規模など、様々な要素によって影響を受けます。
一般的に、木造住宅の坪単価は50万円~70万円程度、鉄骨住宅の坪単価は70万円〜100万円程度と言われています。
つまり、同じ延床面積の住宅を建てる場合、鉄骨造の方が木造よりも建築費用が高くなる傾向があります。
これは、鉄骨材の価格や加工費用、それに伴う人件費などが影響しているためです。
しかし、木造住宅でも、高価な木材や輸入材を使用したり、複雑なデザインを採用したりすることで、建築費用が鉄骨住宅に近づく場合もあります。
逆に、鉄骨住宅でも、シンプルなデザインや標準的な設備を採用することで、コストを抑えることも可能です。
固定資産税の違い
固定資産税は、毎年1月1日時点の建物の評価額に基づいて算出されます。
木造住宅は鉄骨住宅に比べて評価額が低くなる傾向があり、結果として固定資産税も安くなる傾向があります。
これは、木造住宅の法定耐用年数が鉄骨住宅よりも短く設定されているためです。
メンテナンス費用の内訳と周期
住宅のメンテナンス費用は、構造によって大きく異なります。
木造住宅の場合、主なメンテナンス項目としては、外壁塗装、屋根の葺き替え、シロアリ駆除などがあります。
外壁塗装は5年〜10年ごと、屋根の葺き替えは10年〜20年ごと、シロアリ駆除は3年〜5年ごとに行うのが一般的です。
一方、鉄骨住宅の場合、主なメンテナンス項目は、外壁塗装、屋上防水工事、鉄部の錆止め塗装などです。
外壁塗装は10年〜15年ごと、屋上防水工事は10年〜20年ごと、鉄部の錆止め塗装は5年〜10年ごとに行うのが一般的です。
木造住宅は鉄骨住宅に比べてメンテナンス周期が短く、費用も高くなる傾向があります。
長期的な視点で、メンテナンス費用も考慮に入れて建築費用を比較検討しましょう。
火災保険料の違い
火災保険料は、建物の構造や耐火性能によって異なります。
一般的に鉄骨住宅の方が火災保険料は安い傾向にあります。
これは鉄骨造の耐火性の高さによるものです。
保険料は、建物の所在地、構造、延床面積、補償内容などによって決定されます。
鉄骨住宅は、木造住宅に比べて耐火性能が高いため、火災リスクが低いと評価され、保険料が安くなる傾向があります。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
選び方のポイント|どんな人にどちらがおすすめ?

ここではどんな人にどちらの構造がおすすめなのかを紹介します。
木造住宅がおすすめな人
木造住宅は、自然素材の温もりや風合いを大切にする人、初期費用を抑えたい人、日本の伝統的な建築様式を好む人におすすめです。
- コストを抑えたい:初期費用を抑えたい方には、木造住宅がおすすめです。木造住宅は、鉄骨住宅に比べて建築コストが比較的安価であるため、予算を抑えたい方にとって魅力的な選択肢となります。
- 木の温もりを感じたい:自然素材に囲まれた温かい雰囲気の家に住みたい方には、木造住宅がおすすめです。木材の持つ独特の風合いと温もりは、リラックスできる空間を演出します。
- 日本の気候に合わせた快適な家:断熱性や調湿性に優れた木造住宅は、日本の気候に適しています。高温多湿な夏や寒冷な冬でも、快適な室内環境を保つことができます。
鉄骨住宅がおすすめな人
鉄骨住宅は、デザイン性や耐久性を重視する人、開放的な空間を好む人、メンテナンスの手間を省きたい人におすすめです。
- 広い空間が欲しい:開放的なリビングや大きな窓など、デザイン性を重視する方には、鉄骨住宅がおすすめです。鉄骨造は、柱や壁の少ない大空間を実現できるため、自由度の高い設計が可能です。広々としたリビングや、天井の高い開放的な空間など、理想の空間を実現することができます。
- 災害に強い家を建てたい:耐震性や耐火性に優れた鉄骨住宅は、家族の安全を守ります。地震や火災などの災害リスクを軽減したい方にとって、鉄骨住宅は安心できる選択肢となります。鉄骨は不燃材であるため、火災時の延焼リスクを低減できます。
- デザインにこだわりたい:シャープでスタイリッシュな外観を求める方には、鉄骨住宅がおすすめです。鉄骨造は、直線的なデザインやモダンな外観を実現しやすいという特徴があります。都市型の住宅や、個性的なデザインの住宅を希望する方にとって、鉄骨住宅は最適な選択肢となるでしょう。
- メンテナンスの手間を省きたい:鉄骨住宅は、木造住宅に比べてメンテナンスの手間が少ないというメリットがあります。シロアリの被害を受ける心配がなく、定期的な防蟻処理も不要です。外壁塗装の頻度も木造住宅に比べて少ないため、メンテナンス費用を抑えることができます。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
ハウスメーカー選びのポイント

家づくりは、一生に一度の大きなプロジェクトだからこそ、信頼できるハウスメーカー選びが重要になります。
ここでは数あるハウスメーカーの中から、自分に合った会社を見つけるためにはどのような点に注意すれば良いか紹介します。
住宅のプロに相談する
まず大切なのは、複数のハウスメーカーを比較検討することです。
それぞれのハウスメーカーには、得意な工法やデザイン、価格帯など、様々な特徴があります。
複数のハウスメーカーの話を聞き、比較することで、自分たちの希望や予算に合った会社を見つけることができます。
構造見学会に参加する
カタログやウェブサイトの情報だけでは、実際にどのような家が建つのかイメージしづらいものです。
そこで、積極的に構造見学会に参加することをおすすめします。
構造見学会では、建築途中の住宅を見学することができます。
柱や梁などの構造材、断熱材や配管など、普段は見ることができない家の内部構造を自分の目で確認することができます。
アフターサポート体制を確認する
家づくりは家が完成したら終わりではありません。
家が完成した後も、定期的な点検やメンテナンス、リフォームなど、長期的なサポートが必要になります。
そのため、ハウスメーカーのアフターサポート体制を確認しておくことは非常に重要です。
まとめ
木造と鉄骨、どちらの構造にもメリット・デメリットがあり、あなたのライフスタイルや価値観、予算によって最適な選択は異なります。
この記事では、両方の特徴を様々な角度から比較検討してきました。
ぜひこの記事で紹介した情報を参考に、どちらの構造があなたに合っているか判断してみてくださいね。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫

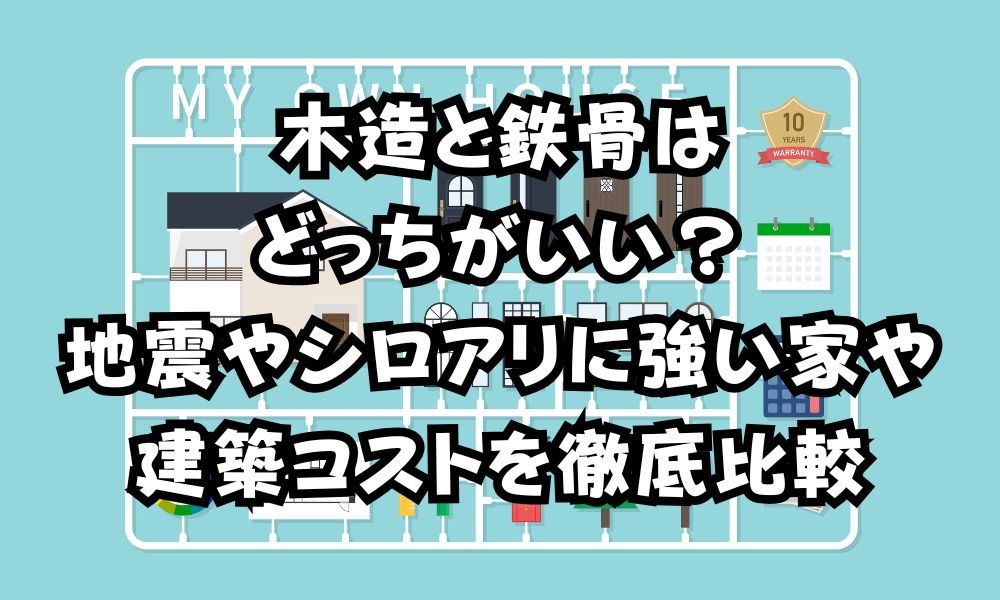

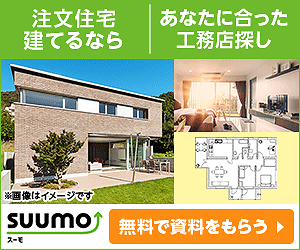


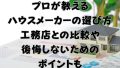

コメント