家づくりで気になるのはやはり費用面。
特に「坪単価」は、家づくりの費用を左右する重要な要素です。
しかし、坪単価だけでハウスメーカーを選んでしまうと、後々大きな後悔につながる可能性もあります。
そこでこの記事ではハウスメーカーの坪単価や、ローコスト住宅からハイグレード住宅までのメリット・デメリットを比較していきます。
ぜひ最後まで読んで、理想の家づくりを実現してくださいね。
本文に入る前に、これから家づくりを考えている人や、現在進行形でハウスメーカー選びを進めている人に、後悔しない家づくりのための最も重要な情報をお伝えします。
早速ですが、質問です。
家づくりで一番大切なこと、それはなんだと思いますか?
おそらく間取りや予算、建てる場所などと考える人も多いかもしれませんね。
ですが実は、家づくりで最も大切なことは「気になっているハウスメーカーのカタログを、とりあえず全て取り寄せてしまうこと」なんです。
カタログを取り寄せずに住宅展示場に行き、営業マンの言葉巧みな営業トークに押されて契約を結んでしまうのは最悪なケース。
住宅展示場に行ってその場で契約をしてしまった人の中には、「もしもカタログを取り寄せて比較検討していたら、同じ間取りの家でも300万円安かったのに・・・」と後悔する人が本当に多いんです。
このように、もう少し情報収集をしていれば理想の家をもっと安く建てられていたのに、場合によっては何百万単位の損をして後悔してしまうこともあります。
だからこそ、きちんとした情報収集をせずにハウスメーカーを選ぶのは絶対にやめてください。
そんなことにならないようにハウスメーカーのカタログを取り寄せて比較検討することが最も重要なんです。

そうは言っても、気になるハウスメーカーはたくさんあるし、気になるハウスメーカー全てに連絡してカタログを取り寄せるなんて、時間と労力がかかりすぎるよ・・・
そう思う人も少なくありません。
そもそもどのように情報収集をしたら良いのかわからないという人もいるでしょう。
そんなあなたにぜひ活用してほしいサービスが、「ハウスメーカーのカタログ一括請求サービス」や「専門家に実際に相談してみること」です!
これらのサービスを活用することで、何十倍もの手間を省くことができ、損をするリスクも最大限に減らすことができます。
中でも、不動産業界大手が運営をしている下記の3つのサービスが特におすすめです。
|
東証プライム上場企業「LIFULL」が運営をしているカタログ一括請求サービスです。厳しい審査を通過した全国の優良住宅メーカーからカタログを取り寄せることが可能です。特にローコスト住宅に強いため、ローコスト住宅でマイホームを検討している人に非常におすすめです。 不動産のポータルサイトとしておそらく全国で最も知名度のあるSUUMOが運営しています。全国各地の工務店とのネットワークも豊富。住宅の専門家との相談をすることが可能で、住宅メーカー選びのみならず、家づくりの初歩的な質問から始めることが可能です。「何から始めたら良いのかわからない」と言う人はSUUMOに相談することがおすすめです。 上場企業でもあるNTTデータが運営しているサービスです。大手ということもあり、信頼も厚いのが特徴です。全国各地の大手ハウスメーカーを中心にカタログを取り寄せることができます。また、理想の家づくりプランを作ってもらえるのも嬉しいポイントです。 |
上記の3サイトはどれも完全無料で利用できる上、日本を代表する大手企業が運営しているため、安心して利用することができます。
また、厳しい審査基準で問題のある企業を事前に弾いているため、悪質な住宅メーカーに依頼してしまうというリスクを避けることも可能です。
正直言って、こちらの3サイトならどれを利用しても間違いはないでしょう。
また、どれを利用するか迷ったら、
- ローコスト住宅メーカーや大手ハウスメーカーを検討中:LIFULL HOME'Sでカタログ請求
- 工務店をメインで検討中:SUUMOカウンターで相談
- 資金計画や土地探しも相談したい:家づくりのとびら
というふうに使い分けてみるのもおすすめです。
そのほかに、SUUMOも無料カタログの一括請求サービスを提供しています。
こちらも無料なので、ぜひ利用してみることをおすすめします。
もちろんどのサービスも無料なため、全て活用してみるのもおすすめです。
後悔のない家づくりのため、1社でも多くの会社からカタログを取り寄せてみてくださいね!
\メーカー比較で数百万円得することも!/

【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる≫

【プロと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
家づくりで後悔しないために、これらのサービスをうまく活用しながら、ぜひあなたの理想を叶えてくれる住宅メーカーを見つけてみてください!
それでは本文に入っていきましょう!
坪単価とは

家づくりにおいて「坪単価」は、建物の価格を比較検討する際の重要な指標です。
ここでは、坪単価の正しい理解と活用方法について解説します。
坪単価の定義と計算方法
坪単価とは、建物の本体価格を延床面積で割った、1坪(約3.3平方メートル)あたりの建築費用のことです。
計算式は下記の通りシンプルです。
- 計算方法: 建物本体価格 ÷ 延床面積
一見簡単そうですが、ここで重要なのは「延床面積」と「建物本体価格」の定義がハウスメーカーによって微妙に異なる点です。
延床面積とは、建物各階の床面積の合計を指し、一般的にはベランダ、バルコニー、ロフト、吹き抜けなどは含まれません。
一方で、「施工床面積」という用語もあり、こちらは延床面積に加えて、ベランダやロフトなどを含めた面積を指します。
坪単価を比較する際は、延床面積か施工床面積のどちらを基準にしているか、必ず確認することが重要です。
また、「建物本体価格」も注意が必要です。
これは家の基本構造部分の価格を指しますが、ハウスメーカーによっては、キッチンや浴室などの設備費用が含まれる場合もあれば、含まれない場合もあります。
さらに、付帯工事費が含まれるケースもあり、比較の際には注意が必要です。
延床面積と施工面積の違いを理解する
延床面積と施工面積の違いを理解することは、坪単価を正しく比較するために非常に重要です。
- 延床面積: 各階の床面積の合計。壁心ではなく、内法寸法(部屋の内部の寸法)で計算されます。
- 施工面積: 延床面積に、バルコニー、ベランダ、ポーチなどの面積を加えたもの。
例えば、同じ本体価格で延床面積30坪、施工面積35坪の住宅の場合、延床面積で計算した坪単価と施工面積で計算した坪単価は当然ながら異なります。
延床面積で計算した方が坪単価は高く見えます。
ハウスメーカーによっては、意図的に施工面積を使って坪単価を安く見せている場合もあるので注意が必要です。
複数のハウスメーカーを比較する際は、必ず同じ基準(延床面積または施工面積)で計算された坪単価を比較するようにしましょう。
坪単価に含まれない費用
坪単価はあくまでも建物本体価格を延床面積で割ったものであり、家づくりにかかる全ての費用ではありません。
坪単価に含まれない費用として、以下のようなものがあります。
- 土地代: これは地域や立地条件によって大きく変動します。
- 土地の仲介手数料: 土地を購入する際に不動産会社に支払う手数料です。
- 外構費用: 庭や塀、駐車場などの工事費用です。
- 屋外給排水工事: 水道や下水道の引き込み工事費用です。
- ガス引き込み費用: 都市ガスやプロパンガスの引き込み工事費用です。
- 住宅ローン保証料: 住宅ローンを組む際に金融機関に支払う保証料です。
- 地盤改良費用: 地盤が弱い場合は、地盤改良工事が必要になります。
- 火災保険料: 住宅火災保険の費用です。
- カーテン、照明、エアコン、家具、家電: これらは別途購入する必要があります。
- 設計業務報酬料: 建築家に設計を依頼する場合に発生します。
- 長期優良住宅、性能表示制度申請費: これらの制度を利用する場合に発生する申請費用です。
- 登記費用: 所有権保存登記や抵当権設定登記などの費用です。
これらの費用は総額で数百万円になる場合もあります。
家づくりの際には、坪単価だけでなく、これらの費用も含めた総費用で考えることが重要です。
坪単価の相場
坪単価の相場は、地域、住宅の構造、使用する建材、住宅設備のグレードなど、様々な要因によって大きく変動します。
全国平均ではおおむね93万円前後で推移していると言われていますが、あくまで目安です。
都市部では土地価格が高いため、坪単価も高くなる傾向があります。
また、木造住宅よりも鉄骨造や鉄筋コンクリート造の方が坪単価は高くなる傾向があります。
さらに、高性能な断熱材や高グレードの住宅設備を採用すると、坪単価は上昇します。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
ハウスメーカー坪単価一覧

ハウスメーカーは、提供する住宅の価格帯によって、大きくローコスト住宅、ミドルコスト住宅、ハイグレード住宅の3つのグループに分けられます。
それぞれの価格帯の特徴、メリット・デメリット、おすすめのターゲット層、代表的なハウスメーカーを解説します。
ローコスト住宅|坪単価50万円~70万円
- 特徴: 価格を抑えることに重点を置いており、シンプルなデザイン、規格住宅が多い傾向があります。
- メリット: 何より初期費用を抑えられることが大きなメリットです。住宅ローン負担も軽減できます。比較的短工期で完成するのも魅力です。
- デメリット: デザインの自由度が低い、住宅性能が低い場合がある点がデメリットとして挙げられます。標準仕様の範囲が狭く、オプションを追加するとコストが上がる可能性があります。
- おすすめのターゲット層: 予算を最優先する人、初期費用を抑えたい人、シンプルなデザインを好む人に向いています。
- 代表的なハウスメーカー: タマホーム、アイダ設計、秀光ビルド、パパまるハウス
ミドルコスト住宅|坪単価70万円~90万円
- 特徴: 性能とデザインのバランスが良い点が特徴です。自由設計に対応できるメーカーも多いです。
- メリット: 一定の品質を保ちながら、ある程度の自由度がある点がメリットです。ローコスト住宅よりもデザイン性や機能性に優れた住宅を建てることができます。
- デメリット: ローコスト住宅より価格が高い点がデメリットです。ハイグレード住宅と比べると、素材や設備のグレードが低い場合があります。
- おすすめのターゲット層: 性能とデザインのバランスを重視する人、ある程度の自由度を求める人、価格と品質のバランスを取りたい人に向いています。
- 代表的なハウスメーカー: アキュラホーム、桧家住宅、アイ工務店、ウィザースホーム、アエラホーム
ハイグレード住宅|坪単価90万円以上
- 特徴: 高品質、高デザイン、高性能、ブランド力がある点が特徴です。最新の技術や高品質な素材を使用し、快適性やデザイン性に優れた住宅を提供しています。
- メリット: 快適で安心な暮らし、資産価値が高い点がメリットです。高性能な設備や充実したアフターサービスにより、快適な生活を送ることができます。
- デメリット: 価格が非常に高い点がデメリットです。予算に余裕がないと、希望する住宅を建てることが難しい場合があります。
- おすすめのターゲット層: 品質、デザイン、ブランドを重視する人、高収入の人、長期的な資産価値を重視する人に向いています。
- 代表的なハウスメーカー: 積水ハウス、ダイワハウス、住友林業、三井ホーム、セキスイハイム、ヘーベルハウス
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
大手ハウスメーカー坪単価ランキング
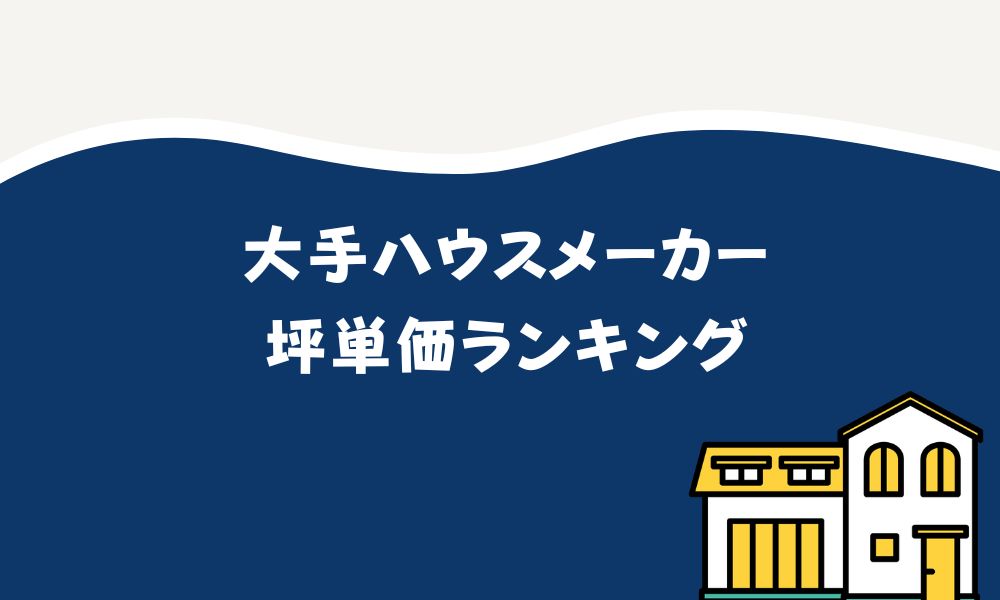
ここでは坪単価に加え、性能、保証、デザインといった観点からも比較してみましょう。
大手ハウスメーカー比較一覧
| ハウスメーカー | 坪単価(万円) | 構造 | 耐震性 | 断熱性 | 保証 | デザイン | その他特徴 |
| 積水ハウス | 100~ | 鉄骨/木造 | シェルター構造 | 高気密高断熱 | 長期保証 | 幅広い | 業界トップクラスのシェア |
| 大和ハウス工業 | 90~ | 鉄骨/木造 | xevoΣ | ダイワハウスXE断熱 | 長期保証 | モダン | 賃貸経営にも強い |
| パナソニックホームズ | 90~ | 木造 | テクノストラクチャー | キューブ構造 | 長期保証 | シンプルモダン | 耐震性に優れる |
| 旭化成ホームズ(ヘーベルハウス) | 120~130 | 鉄骨 | ヘーベル版 | ロングライフ断熱 | 長期保証 | スクエア | 独自のALCコンクリートを使用 |
| 住友林業 | 100~120 | 木造 | ビッグフレーム構法 | BF-Si | 長期保証 | 和モダン | 木材に強い |
| ミサワホーム | 85~ | 木造 | MJ Wood | センサーブレス | 長期保証 | 多様 | 制震装置に強み |
| 三井ホーム | 100~115 | 木造 | プレミアム・モノコック構法 | フィールグッド断熱 | 長期保証 | アメリカンスタイル | デザイン性が高い |
| セキスイハイム | 90~100 | 鉄骨/木造 | ハイブリッド耐震ガイアス | 快適エアリー | 長期保証 | モダン | 工場生産率が高い |
| トヨタホーム | 80~100 | 鉄骨 | ユニバーサル鉄骨 | T-ブレス | 長期保証 | モダン | 鉄骨ラーメン構造 |
| 一条工務店 | 80~100 | 木造 | i-cube構法 | ロスガード90 | 長期保証 | シンプル | 高気密高断熱性能 |
ローコスト住宅メーカー坪単価一覧

ここでは、ローコスト住宅メーカーの坪単価一覧をみていきましょう。
ローコスト住宅メーカー坪単価一覧と特徴
| メーカー名 | 坪単価(万円) | 特徴 |
| タマホーム | 50~ | 徹底したコストダウンで低価格を実現 |
| アイダ設計 | 45~ | 規格住宅で低価格を実現 |
| 秀光ビルド | 55~ | 自由設計も可能なローコスト住宅 |
| パパまるハウス | 50~ | 長期優良住宅対応のローコスト住宅 |
| レオハウス | 55~ | デザイン性が高いローコスト住宅 |
| アーネストワン | 45~ | 分譲住宅にも強いローコスト住宅メーカー |
上記はあくまでも目安であり、地域や仕様によって変動します。
ローコスト住宅の安さの秘密
ローコスト住宅メーカーは、様々な工夫によって低価格を実現しています。
主なコストダウンの方法は以下の通りです。
- 規格住宅の採用: 間取りやデザインを規格化することで、設計費用や材料費を削減しています。
- 大量仕入れ: 建材を大量に仕入れることで、スケールメリットを活かし、仕入れ価格を削減しています。
- 広告宣伝費の削減: テレビCMなどを控えることで、広告宣伝費を削減しています。
- 間接費の削減: モデルハウスの簡素化や営業担当者の絞り込みなど、間接費を削減しています。
- 施工の効率化: 工期を短縮することで、人件費などのコストを削減しています。
ローコスト住宅を選ぶ上での注意点
ローコスト住宅は価格が魅力ですが、以下のような点に注意が必要です。
- 標準仕様の範囲: 標準仕様の範囲が狭いため、必要な設備がオプションになっている場合が多くあります。オプション費用を含めた総額で比較検討しましょう。
- 住宅性能: 断熱性や耐震性など、住宅性能が低い場合があります。快適な住まいを実現するためには、必要な性能を確保するために追加費用が必要となるケースもあります。
- 保証内容: 保証期間や保証内容が、大手ハウスメーカーと比べて限定的である場合があります。保証内容を事前にしっかり確認しましょう。
- アフターサービス: アフターサービスの体制が大手ハウスメーカーに比べて十分でない場合があります。定期点検や修理対応など、アフターサービスの内容を確認しておきましょう。
- 追加費用の発生: 契約後に追加費用が発生するケースも少なくありません。契約前に見積もり内容を詳細に確認し、不明な点は必ず質問するようにしましょう。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
工務店の坪単価

地域密着型の工務店は、大手ハウスメーカーとは異なる魅力を持っています。
柔軟な対応やコストパフォーマンスの良さ、地域に根ざした家づくりなど、メリットが多い一方で、注意すべき点もあります。
ここでは、工務店の坪単価の相場感やメリット・デメリットを解説します。
工務店の坪単価相場
工務店の場合、坪単価は50万円〜100万円程度と幅広いです。
地域や工務店の規模、建材のグレード、住宅設備の仕様、設計の自由度などによって大きく変動します。
ローコスト住宅を手がける工務店もあれば、ハイグレード住宅を手がける工務店もあります。
ハウスメーカーと工務店の違い
| 項目 | ハウスメーカー | 工務店 |
| 価格 | 比較的高価 | 比較的安価 |
| 自由度 | ある程度可能 | 高い |
| 対応 | マニュアル化されている | 柔軟 |
| 保証 | 手厚い | 限定的 |
| 規模 | 大規模 | 小規模 |
| 施工エリア | 広範囲 | 地域密着 |
| アフターサービス | 体制が整っている | 対応が早い場合もある |
工務店を選ぶメリット
- 自由度の高さ: ハウスメーカーの規格住宅とは異なり、間取りやデザイン、使用する材料など、自由に決めることができます。
- 柔軟な対応: 施主の要望に柔軟に対応してくれることが多いです。
- 地域密着型: 地域の気候風土を熟知しているため、最適な家づくりを提案してくれます。
- 顔が見える関係: 工務店の担当者と直接やり取りするため、信頼関係を築きやすいです。
- コストパフォーマンス: 広告費や人件費を抑えているため、コストパフォーマンスに優れている場合があります。
工務店を選ぶデメリット
- 倒産リスク: 大手ハウスメーカーに比べて倒産リスクがあります。
- 保証の範囲: 保証内容や保証期間が限定的である場合があります。
- 施工品質: 工務店によって施工品質に差があります.
- 対応エリア: 対応エリアが限定されている場合があります。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
家づくりで本当に重要な10のポイント

家づくりは人生における大きなイベントです。
坪単価は重要な指標ですが、それだけで判断してしまうと、後悔する可能性があります。
快適で安全な住まいを実現するためには、様々な要素を考慮する必要があります。
1. 住宅性能
住宅性能とは、耐震性、断熱性、気密性、省エネ性などを指します。
地震や台風などの災害に強く、夏涼しく冬暖かい家は、快適な暮らしの基盤となります。
長期的に見て、光熱費の削減にもつながります。
2. デザイン・間取りの自由度
家族構成や生活動線、趣味、将来の変化など、ライフスタイルを反映した間取りやデザインは、快適な暮らしに欠かせません。
- 間取り: 部屋の数や配置、収納スペースなどを考慮しましょう。
- デザイン: 外観デザインや内装デザインなど、自分の好みに合ったデザインを選びましょう。
- 動線: キッチン、洗面所、浴室などの水回り動線や、家事動線を考慮しましょう。
3. アフターサービス・保証の内容
家は建てたら終わりではなく、そこから長い付き合いが始まります。
万が一のトラブルに備え、アフターサービスや保証の内容はしっかりと確認しておきましょう。
- 保証期間: 保証期間の長さを確認しましょう。
- 保証内容: どのような場合に保証が適用されるのかを確認しましょう。
- 定期点検: 定期点検の有無や内容を確認しましょう。
- 対応の迅速さ: トラブル発生時の対応の迅速さを確認しましょう。
4. 住宅設備のグレード
キッチン、お風呂、トイレなどの住宅設備は、日々の暮らしの質に大きく影響します。
使いやすさ、デザイン性、機能性などを考慮して選びましょう。
- キッチン: システムキッチン、IHクッキングヒーターなど、機能性やデザイン性を考慮しましょう。
- お風呂: 浴室乾燥機、ミストサウナなど、快適性を高める機能も検討しましょう。
- トイレ: タンクレストイレ、自動洗浄機能など、使いやすさや清潔さを考慮しましょう。
5. 営業担当者との相性
営業担当者との信頼関係は、スムーズな家づくりに不可欠です。
- コミュニケーション: しっかりとコミュニケーションを取ってくれる担当者を選びましょう。
- 誠実さ: 誠実で信頼できる担当者を選びましょう。
- 知識・経験: 豊富な知識と経験を持つ担当者を選びましょう。
6. 資金計画・住宅ローン
無理のない返済計画を立てることは、家づくりにおいて非常に重要です。
- 予算設定: 収入や支出、将来のライフイベントなどを考慮して、無理のない予算を設定しましょう。
- 住宅ローン: 金利タイプや返済期間など、自分に合った住宅ローンを選びましょう。
- 諸費用: 登記費用や印紙税など、住宅ローン以外にも様々な諸費用がかかります。
7. 土地探し
土地は理想の家を建てるための土台となります。
周辺環境、交通アクセス、日当たりなどを考慮して、最適な土地を選びましょう。
- 立地: 生活の利便性や、周辺環境を確認しましょう。
- 地盤: 地盤の強さを確認しましょう。地盤改良が必要な場合は、別途費用がかかります。
- 法規制: 建築基準法などの法規制を確認しましょう。
8. 将来のメンテナンスコスト
家は建てたら終わりではなく、定期的なメンテナンスが必要です。
外壁塗装や屋根の葺き替えなど、将来発生するメンテナンスコストも考慮に入れて資金計画を立てましょう。
9. 建築事例・モデルハウス
実際に建てられた家やモデルハウスを見学することで、具体的なイメージを持つことができます。
間取りやデザイン、設備などを参考にしましょう。
10. 口コミ・評判
インターネットや住宅情報誌などで、様々な情報を収集し、比較検討しましょう。
ただし、インターネット上の口コミは、悪い評判が目立ちやすい傾向があります。
あくまでも参考程度にとどめ、最終的には自分の目で確かめることが重要です。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
まとめ
家づくりは、人生で最も大きな買い物の一つ。
だからこそ、後悔のない選択をするためには、事前の準備と情報収集が不可欠です。
この記事では、坪単価を中心としたハウスメーカー選びのポイントを解説してきました。
坪単価は重要な指標となりますが、坪単価だけでなく、各社の特徴やメリット・デメリットを比較して、理想のハウスメーカーや工務店を見つけてみてくださいね。
この記事が、少しでもあなたの家づくりの役に立てば幸いです。

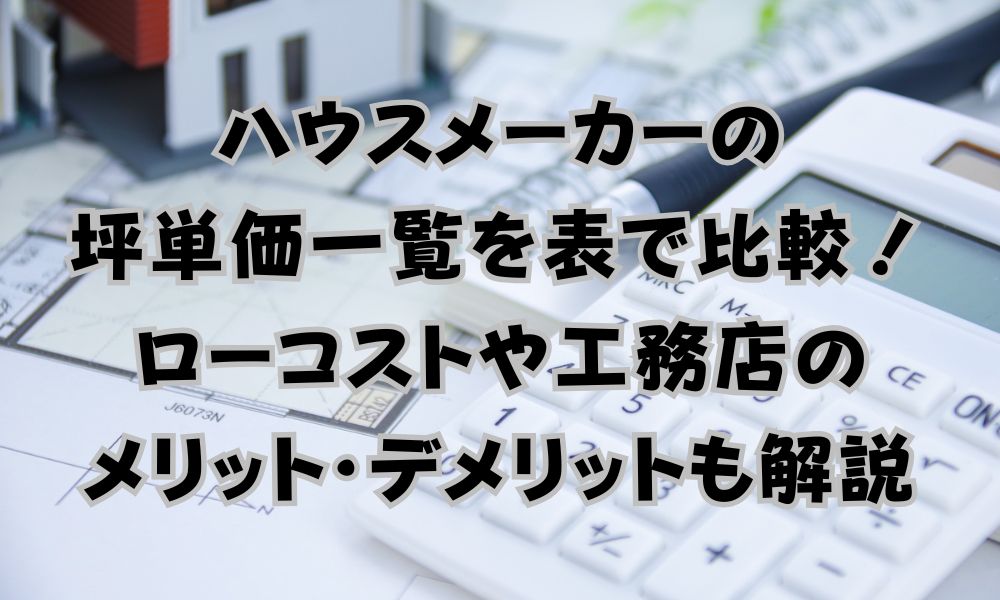

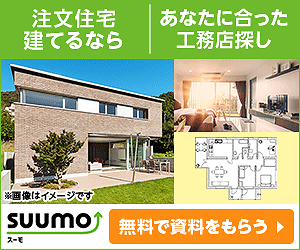


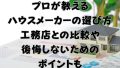

コメント