日本に住む以上、地震への備えは避けて通れません。
そのため家を建てる際に地震に強い家にすることは最優先事項と言えるでしょう。
そこでこの記事では、地震に強い家を建てるための方法やハウスメーカー選びの注意点などをまとめました。
ぜひ最後まで参考にしてみてくださいね。
本文に入る前に、これから家づくりを考えている人や、現在進行形でハウスメーカー選びを進めている人に、後悔しない家づくりのための最も重要な情報をお伝えします。
早速ですが、質問です。
家づくりで一番大切なこと、それはなんだと思いますか?
おそらく間取りや予算、建てる場所などと考える人も多いかもしれませんね。
ですが実は、家づくりで最も大切なことは「気になっているハウスメーカーのカタログを、とりあえず全て取り寄せてしまうこと」なんです。
カタログを取り寄せずに住宅展示場に行き、営業マンの言葉巧みな営業トークに押されて契約を結んでしまうのは最悪なケース。
住宅展示場に行ってその場で契約をしてしまった人の中には、「もしもカタログを取り寄せて比較検討していたら、同じ間取りの家でも300万円安かったのに・・・」と後悔する人が本当に多いんです。
このように、もう少し情報収集をしていれば理想の家をもっと安く建てられていたのに、場合によっては何百万単位の損をして後悔してしまうこともあります。
だからこそ、きちんとした情報収集をせずにハウスメーカーを選ぶのは絶対にやめてください。
そんなことにならないようにハウスメーカーのカタログを取り寄せて比較検討することが最も重要なんです。

そうは言っても、気になるハウスメーカーはたくさんあるし、気になるハウスメーカー全てに連絡してカタログを取り寄せるなんて、時間と労力がかかりすぎるよ・・・
そう思う人も少なくありません。
そもそもどのように情報収集をしたら良いのかわからないという人もいるでしょう。
そんなあなたにぜひ活用してほしいサービスが、「ハウスメーカーのカタログ一括請求サービス」や「専門家に実際に相談してみること」です!
これらのサービスを活用することで、何十倍もの手間を省くことができ、損をするリスクも最大限に減らすことができます。
中でも、不動産業界大手が運営をしている下記の3つのサービスが特におすすめです。
|
東証プライム上場企業「LIFULL」が運営をしているカタログ一括請求サービスです。厳しい審査を通過した全国の優良住宅メーカーからカタログを取り寄せることが可能です。特にローコスト住宅に強いため、ローコスト住宅でマイホームを検討している人に非常におすすめです。 不動産のポータルサイトとしておそらく全国で最も知名度のあるSUUMOが運営しています。全国各地の工務店とのネットワークも豊富。住宅の専門家との相談をすることが可能で、住宅メーカー選びのみならず、家づくりの初歩的な質問から始めることが可能です。「何から始めたら良いのかわからない」と言う人はSUUMOに相談することがおすすめです。 上場企業でもあるNTTデータが運営しているサービスです。大手ということもあり、信頼も厚いのが特徴です。全国各地の大手ハウスメーカーを中心にカタログを取り寄せることができます。また、理想の家づくりプランを作ってもらえるのも嬉しいポイントです。 |
上記の3サイトはどれも完全無料で利用できる上、日本を代表する大手企業が運営しているため、安心して利用することができます。
また、厳しい審査基準で問題のある企業を事前に弾いているため、悪質な住宅メーカーに依頼してしまうというリスクを避けることも可能です。
正直言って、こちらの3サイトならどれを利用しても間違いはないでしょう。
また、どれを利用するか迷ったら、
- ローコスト住宅メーカーや大手ハウスメーカーを検討中:LIFULL HOME'Sでカタログ請求
- 工務店をメインで検討中:SUUMOカウンターで相談
- 資金計画や土地探しも相談したい:家づくりのとびら
というふうに使い分けてみるのもおすすめです。
そのほかに、SUUMOも無料カタログの一括請求サービスを提供しています。
こちらも無料なので、ぜひ利用してみることをおすすめします。
もちろんどのサービスも無料なため、全て活用してみるのもおすすめです。
後悔のない家づくりのため、1社でも多くの会社からカタログを取り寄せてみてくださいね!
\メーカー比較で数百万円得することも!/

【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる≫

【プロと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
家づくりで後悔しないために、これらのサービスをうまく活用しながら、ぜひあなたの理想を叶えてくれる住宅メーカーを見つけてみてください!
それでは本文に入っていきましょう!
「地震に強い家」が求められる理由
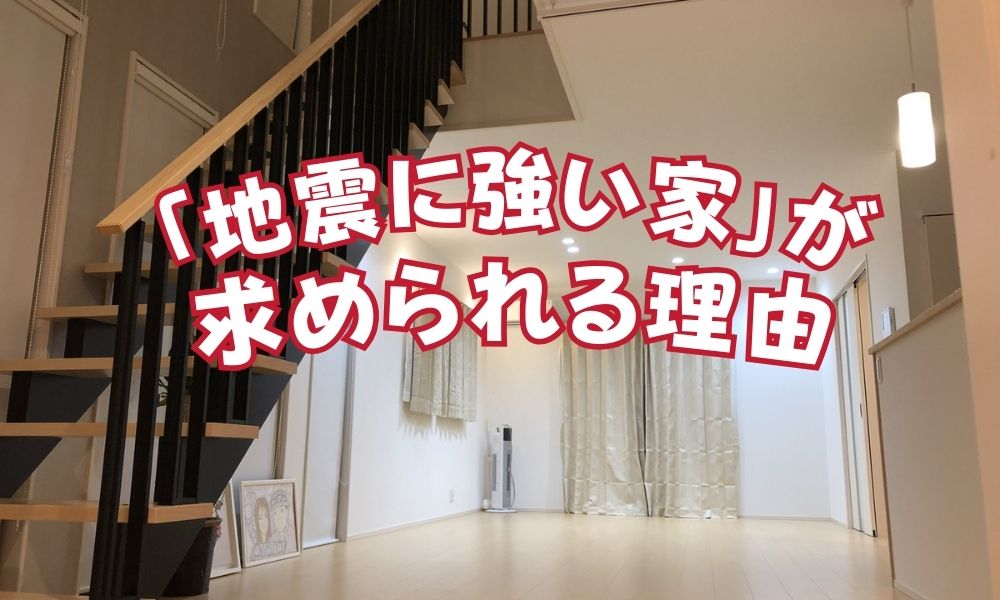
近年の巨大地震の発生は、私たちの防災意識を大きく変えました。
建物の耐震性だけでなく、地震後の生活への備えの重要性が広く認識されるようになってきました。
被害の具体的事例と備えの重要性
過去の巨大地震は、私たちに多くの教訓を残しました。
1995年の阪神・淡路大震災では、約6,400人以上が犠牲となり、その多くが建物の倒壊によるものでした。
この地震は、既存の耐震基準の見直しを迫る大きな契機となりました。
2011年の東日本大震災では、地震そのものに加え、巨大津波による被害が甚大でした。
地震と津波という複合災害への備えの重要性を改めて認識させられる自然災害となりました。
さらに2016年の熊本地震では、震度7の地震が2度発生し、建物の倒壊だけでなく、地盤の液状化や土砂災害など、広範囲にわたる被害が発生しました。
これらの地震は地震発生時の安全確保だけでなく、地震後の生活継続性も考慮した家づくりが不可欠であることを示しています。
建築基準法の耐震基準とは
建築基準法には、建物の最低限の耐震性を確保するための基準が定められています。
1981年に制定された新耐震基準は、「数百年に一度発生する地震(震度6強〜震度7程度)に対し、人命を守るため倒壊・崩壊しない」ことを目的としています。
しかし、これはあくまで最低限の基準であり、建物が損傷したり、住めなくなる可能性は否定できません。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
地震に強い家の定義

地震に強い家とは、単に倒壊しない家ではありません。
地震発生時、そして地震後も、家族の命を守り、資産を守り、生活を守ることができる家が真に地震に強い家と言えるでしょう。
単なる倒壊防止ではない
地震に強い家は、建物の倒壊を防ぐだけでなく、地震後の生活の継続性も考慮した設計が重要です。
具体的には、以下の点を考慮する必要があります。
- 建物の損傷の最小化: 耐震構造、制震構造、免震構造など、適切な構造を採用することで、地震による建物の損傷を最小限に抑えることができます。
- 避難経路の確保: 地震発生時には、家具の転倒などで避難経路が塞がれる可能性があります。家具の配置や固定方法を工夫し、安全な避難経路を確保しましょう。
- ライフラインの確保: 電気、ガス、水道などのライフラインが途絶した場合に備え、太陽光発電システムや蓄電池、井戸などの導入を検討しましょう。
- 家具の転倒防止: 家具の転倒は、負傷の原因となるだけでなく、避難経路を塞ぐ危険性もあります。家具の固定や転倒防止器具の設置など、対策を徹底しましょう。
- 二次災害への備え: 地震後の火災発生を防ぐため、耐火性の高い建材を使用したり、住宅用火災警報器を設置しましょう。
二次災害(火災、津波、液状化)への備え
地震発生後の二次災害への備えも、地震に強い家づくりには欠かせません。
火災、津波、液状化など、それぞれの災害リスクを把握し、適切な対策を講じることが重要です。
- 火災への備え: 地震による火災は、延焼しやすく、甚大な被害をもたらす可能性があります。耐火性の高い建材を使用する、住宅用火災警報器を設置するなどの対策が重要です。
- 津波への備え: 沿岸部に住む場合は、津波のリスクを十分に認識し、避難経路や避難場所を確認しておくことが重要です。津波避難タワーの設置場所や、高台への避難経路などを事前に確認しておきましょう。
- 液状化への備え: 液状化現象は、地盤が液体状になる現象で、建物の傾斜や倒壊を引き起こす可能性があります。地盤改良工事や、液状化に強い基礎構造の採用などを検討しましょう。
耐震・制震・免震とは

地震に強い家を建てるためには、建物の構造を理解することが不可欠です。
耐震、制震、免震は、地震に対する建物の強度や挙動を決定づける重要な要素です。
それぞれの構造の特徴についてみていきましょう。
耐震・制震・免震のメカニズム
- 耐震構造: 地震の力に抵抗する構造で、建物の強度を高めることで倒壊を防ぎます。柱や梁、壁などの主要構造部材を強化することで、地震の揺れに耐える仕組みです。「耐える」構造であるため、地震後は損傷が生じる可能性があり、修復が必要となるケースもあります。
- 制震構造: 地震エネルギーを吸収することで建物の揺れを軽減する構造です。ダンパーなどの制震装置を設置し、地震エネルギーを熱エネルギーなどに変換して吸収します。建物の損傷を軽減し、家具の転倒防止にも効果的です。耐震構造と組み合わせることで、より高い効果を発揮します。
- 免震構造: 地震の揺れを建物に伝わりにくくする構造です。建物の基礎部分に免震装置を設置し、地面の揺れを建物に伝達させにくくすることで、建物へのダメージを最小限に抑えます。建物や家具への損傷が少ないだけでなく、地震発生時の居住者の安全性を高めます。
コスト・効果・メンテナンスの比較
各構造には、それぞれコスト、効果、メンテナンスに関するメリット・デメリットがあります。
長期的な視点で比較検討し、最適な構造を選びましょう。
| 構造 | コスト | 効果 | メンテナンス |
| 耐震 | 低 | 中 | 低 |
| 制震 | 中 | 高 | 中 |
| 免震 | 高 | 最高 | 高 |
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
地震に強い家を実現する7つのポイント
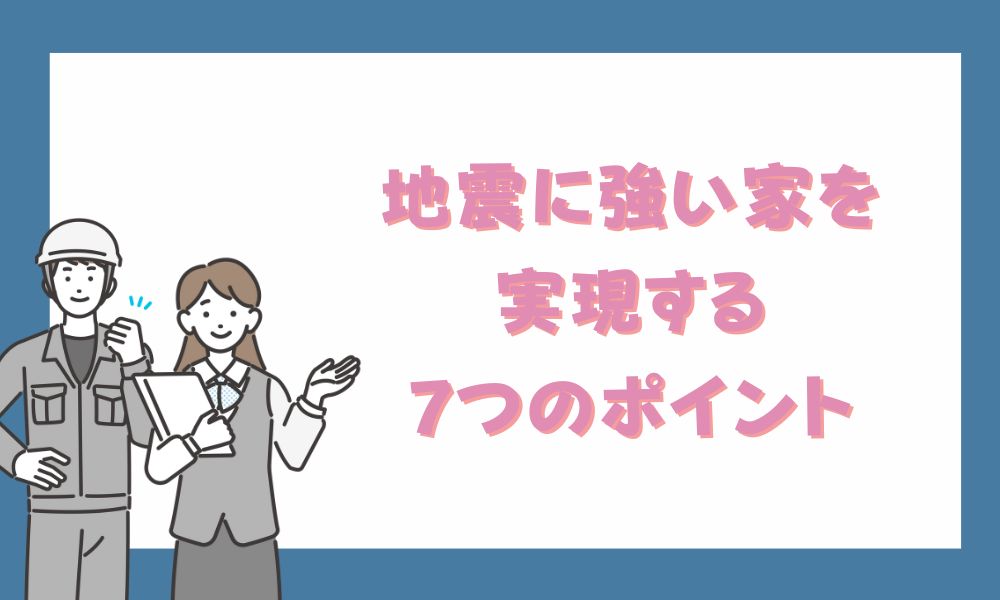
地震に強い家を建てるには、構造だけでなく、形状、地盤、屋根、基礎、間取り、メンテナンスに至るまで、多くの要素を考慮する必要があります。
ここではこれら7つのポイントについてみていきましょう。
【構造】耐震、制震、免震構造を徹底比較
耐震、制震、免震構造については、前のセクションで詳しく解説しましたが、ここではそれぞれの構造のメリット・デメリットを改めて整理し、選び方のポイントを解説します。
- 耐震構造: メリットは、コストが比較的安価で、工期が短いことです。デメリットは、大地震時には建物の損傷が生じる可能性があることです。選び方のポイントは、予算を抑えたい方、工期を短縮したい方におすすめです。
- 制震構造: メリットは、耐震構造に比べて建物の損傷を軽減できることです。デメリットは、耐震構造よりもコストがかかることです。選び方のポイントは、耐震性を高めたい方、建物の損傷を最小限に抑えたい方におすすめです。
- 免震構造: メリットは、地震の揺れを大幅に軽減できることです。デメリットは、コストが最も高くなることです。選び方のポイントは、地震による揺れを最小限に抑えたい方、家具の転倒などを防ぎたい方におすすめです。
【形状】正方形・長方形が有利な理由
建物の形状は、地震時の揺れ方に大きく影響します。
シンプルな形状である正方形や長方形は、地震エネルギーを均等に分散させることができるため、耐震性の高い建物を実現しやすい形状です。
シンプルな形状が地震エネルギーを分散
正方形や長方形のようなシンプルな形状は、地震の揺れを均一に受け止めることができるため、建物への負担を軽減することができます。
L字型・コの字型など複雑な形状のリスクと対策
L字型やコの字型など、複雑な形状の建物は、地震時にねじれや偏心が生じやすく、損傷のリスクが高まります。
このような形状の建物を建てる場合は、構造計算を綿密に行い、耐震壁を適切に配置することで、ねじれや偏心を防ぐ工夫が必要です。
狭小住宅・都市型住宅における形状の工夫
都市部の狭小住宅や変形敷地など、敷地の制約がある場合でも、建物の形状を工夫することで耐震性を高めることができます。
例えば、建物を分割して複数のシンプルな形状に組み合わせたり、耐震壁を効果的に配置するなど、設計段階での工夫が重要です。
【間取り】地震に強い間取りと自由度の両立
間取りは、居住性だけでなく耐震性にも影響を与える重要な要素です。
耐震性を考慮した間取りを理解し、自由度の高い設計と安全性を両立させる工夫が必要です。
吹き抜け・ビルトインガレージ
吹き抜けやビルトインガレージは、開放的な空間を演出できる一方で、耐震性を低下させる可能性があります。
壁の量が少なくなるため、建物の強度が不足しやすくなるためです。
これらの空間を設ける場合は、構造計算を綿密に行い、適切な構造補強を行う必要があります。
窓の配置・大きさ
窓は、採光や眺望を確保するために重要な要素ですが、耐震性を考慮した配置と大きさにする必要があります。
窓が大きすぎたり、数が多すぎると、壁の面積が減り、建物の強度が低下する可能性があります。
耐力壁の配置
耐力壁は、地震の力に抵抗する重要な壁です。
耐力壁の配置が偏っていると、建物がねじれたり、部分的に大きな力が集中する可能性があります。
耐力壁はバランス良く配置し、建物の強度を均一に保つことが重要です。
直下率
直下率とは、1階の柱や壁の上に、2階の柱や壁がどれだけ乗っているかを表す割合です。
直下率が高いほど、建物の重心が安定し、耐震性が高まります。
1階と2階の柱や壁の配置を揃えることで、直下率を高めることができます。
リビング階段
リビング階段は、空間を広く見せる効果がありますが、耐震性を低下させる可能性があります。
壁の量が少なくなるため、建物の強度が不足しやすいためです。
リビング階段を採用する場合は、構造計算を綿密に行い、適切な構造補強を行うことが重要です。
間取りの自由度と耐震性のバランス
耐震性を高めるためには、間取りの自由度が制限される場合もあります。
しかし、耐震性と居住性を両立させる工夫は可能です。
設計段階で専門家と相談し、最適な間取りを検討しましょう。
【地盤】不同沈下を防ぐ地盤調査と改良工事
家は地盤の上に建っています。
どんなに頑丈な家でも、地盤が弱ければ、不同沈下を起こし、家が傾いたり、壁にひびが入ったりする可能性があります。
そのため、地盤調査と適切な地盤改良工事は、地震に強い家づくりにおいて非常に重要な要素となります。
地盤調査の種類と費用
地盤調査には、主に以下の2つの方法があります。
- SWS試験(スウェーデン式サウンディング試験): 比較的簡易な方法で、費用も安価です。建物の四隅と中心部など、数カ所で行います。鉄の棒に重りを載せて地盤に貫入させ、地盤の固さを測定します。
- ボーリング調査: より詳細な地盤の情報を得ることができる方法です。地盤を掘削し、土質サンプルを採取することで、地盤の層構造や土質、強度などを詳しく調べることができます。SWS試験よりも費用は高くなりますが、大規模な建物や、地盤が複雑な場合に適しています。
【屋根】軽量な屋根材で重心を低くする
屋根は家の中で最も高い位置にあり、その重量は建物の重心に大きく影響します。
屋根を軽量化することで、建物の重心を低く抑え、地震時の揺れを軽減することができます。
瓦・スレート・ガルバリウム鋼板
屋根材には、瓦、スレート、ガルバリウム鋼板など、様々な種類があります。
それぞれの素材の特性を理解し、耐震性、耐久性、コストなどを考慮して最適な屋根材を選びましょう。
- 瓦: 重厚感があり、耐久性に優れていますが、重量があるため、地震時には建物に大きな負担がかかります。
- スレート: 瓦よりも軽量で、施工性も良好です。耐震性とコストのバランスが良い選択肢です。
- ガルバリウム鋼板: 軽量で耐震性に優れており、近年人気が高まっている屋根材です。耐久性にも優れ、メンテナンスも比較的容易です。
それぞれの屋根材には、メリット・デメリットがあります。
予算、デザイン性、メンテナンス性などを考慮し、総合的に判断して選びましょう。
【基礎】ベタ基礎 vs 布基礎
基礎は、建物を支える土台となる部分で、耐震性を確保するために非常に重要な役割を果たします。
ここでは、代表的な基礎であるベタ基礎と布基礎の特徴、強度、コストを比較し、選び方のポイントを解説します。
ベタ基礎
ベタ基礎は、建物の底面全体に鉄筋コンクリートの盤を敷き詰める基礎工法です。
面全体で建物を支えるため、荷重を均等に分散させることができ、不同沈下を防ぎ、建物の安定性を高めます。
- 不同沈下防止効果: 地盤が軟弱な場合でも、不同沈下を抑制し、建物の安定性を確保します。
- シロアリ対策: コンクリートで床下全体を覆うため、シロアリの侵入を防ぎます。
- 湿気対策: 地面からの湿気を遮断し、建物の耐久性を向上させます。
布基礎
布基礎は、建物の壁の下に沿って鉄筋コンクリートの連続基礎を設ける工法です。
ベタ基礎に比べてコストを抑えることができますが、耐震性はベタ基礎に劣ります。
- コストメリット: ベタ基礎に比べて、材料費や工費を抑えることができます。
- 耐震性の課題: 面で支えるベタ基礎に比べて、不同沈下が発生しやすい傾向があります。
- 用途: 比較的小規模な建物や、地盤が安定している場合に適しています。
ベタ基礎 vs 布基礎
| 項目 | ベタ基礎 | 布基礎 |
| 耐震性 | 高 | 中 |
| 不同沈下防止効果 | 高 | 中 |
| 湿気対策 | 高 | 中 |
| シロアリ対策 | 高 | 中 |
| コスト | 高 | 低 |
| 工期 | 長 | 短 |
基礎のひび割れ
基礎にひび割れが発生した場合、建物の耐震性が低下する可能性があります。
ひび割れの原因を特定し、適切な補修工事を行うことが重要です。
- 構造的なひび割れ: 地震や不同沈下などによって発生するひび割れで、建物の構造に影響を与える可能性があります。専門業者による調査と補修が必要です。
- 乾燥収縮によるひび割れ: コンクリートの乾燥収縮によって発生するひび割れで、一般的には構造的な問題はありません。ヘアークラックと呼ばれる細いひび割れが代表的です。
- 温度変化によるひび割れ: 温度変化によってコンクリートが膨張・収縮することで発生するひび割れです。
ひび割れの状態によっては、緊急性を要する場合もあります。
専門業者に相談し、適切な対処を行いましょう。
【メンテナンス】定期的な点検で住まいの寿命を長くする
家を建てたら終わりではなく、定期的なメンテナンスを行うことで、建物の寿命を延ばし、安全性を維持することができます。
地震に強い家であり続けるためには、日頃からのメンテナンスが不可欠です。
木造住宅のシロアリ対策・腐食対策
木造住宅は、シロアリや腐食による劣化を防ぐためのメンテナンスが重要です。
- シロアリ対策: シロアリは、木材を食害する害虫で、建物の強度を著しく低下させる可能性があります。定期的な点検を行い、シロアリの発生を早期に発見し、駆除することが重要です。
- 腐食対策: 木材は、湿気によって腐食する可能性があります。床下換気を適切に行い、湿気がこもらないようにすることが重要です。また、木材に防腐処理を施すことも有効です。
耐震診断
既存の住宅の耐震性を評価するために、耐震診断を行うことができます。
耐震診断では、建物の構造や劣化状況などを調査し、耐震性能を評価します。
- 耐震診断の費用: 建物の規模や築年数、診断方法によって異なります。
- 耐震診断の方法: 専門家が建物を訪問し、図面や構造材などを確認します。
- 耐震補強: 耐震診断の結果、耐震性が不足している場合は、耐震補強工事を行うことで耐震性を向上させることができます。壁の補強、筋交いの追加、基礎の補強など、様々な補強方法があります。
住宅のメンテナンス時期
住宅のメンテナンスは、定期的に行うことが重要です。
メンテナンス時期や費用は、建物の種類や部位によって異なります。
- 屋根の点検: 10年~15年ごと
- 外壁の点検: 5年~10年ごと
- 水回りの点検: 2年~5年ごと
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
地震に強い家を建てるためのハウスメーカー選びの注意点
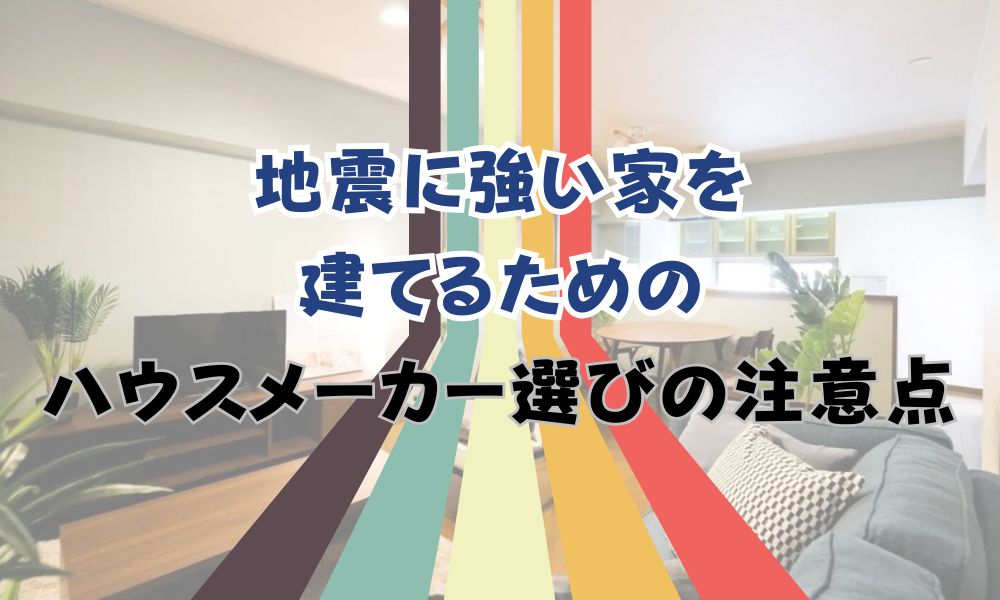
地震に強い家を建てるためには、ハウスメーカー選びも重要なポイントです。
数あるハウスメーカーの中から、自分に合った会社を選ぶためには、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。
ハウスメーカーの得意な工法・構造を比較
ハウスメーカーによって、得意とする工法や構造が異なります。
- 木造: 木造住宅は、日本の風土に合った伝統的な工法で、温かみのある空間を演出できます。耐震性も高く、コストパフォーマンスにも優れています。
- 鉄骨造: 鉄骨造住宅は、強度が高く、耐火性にも優れています。間取りの自由度も高く、デザイン性の高い住宅を建てることができます。
- RC造(鉄筋コンクリート造): RC造住宅は、耐震性、耐火性、耐久性に優れています。設計の自由度も高く、様々なデザインの住宅を建てることができます。
住宅展示場で実物を確認
カタログやウェブサイトの情報だけでは、実際に住む家のイメージを掴むのは難しいものです。
住宅展示場では、様々なハウスメーカーの住宅を実際に見て、触れて、体感することができます。
構造や素材、技術などを自分の目で確認し、各ハウスメーカーの特徴を比較検討しましょう。
耐震等級3は必須?
住宅性能表示制度では、建物の耐震性能を耐震等級で示しています。
耐震等級3は、最高等級であり、数百年に一度発生する地震にも倒壊しない性能を有しています。
耐震等級3は必須ではありませんが、地震に対する安心感を高めるためには、取得を検討する価値があります。
保証とアフターサービス
ハウスメーカーの保証内容やアフターサービスも重要なポイントです。
長期保証や定期点検の有無を確認し、万が一のトラブル発生時にも安心して対応してもらえるかを確認しましょう。
保証内容の確認
保証内容は、ハウスメーカーによって異なります。
保証期間、保証範囲、保証の条件などをしっかりと確認しておきましょう。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
地震に強い家づくりにおすすめのハウスメーカー
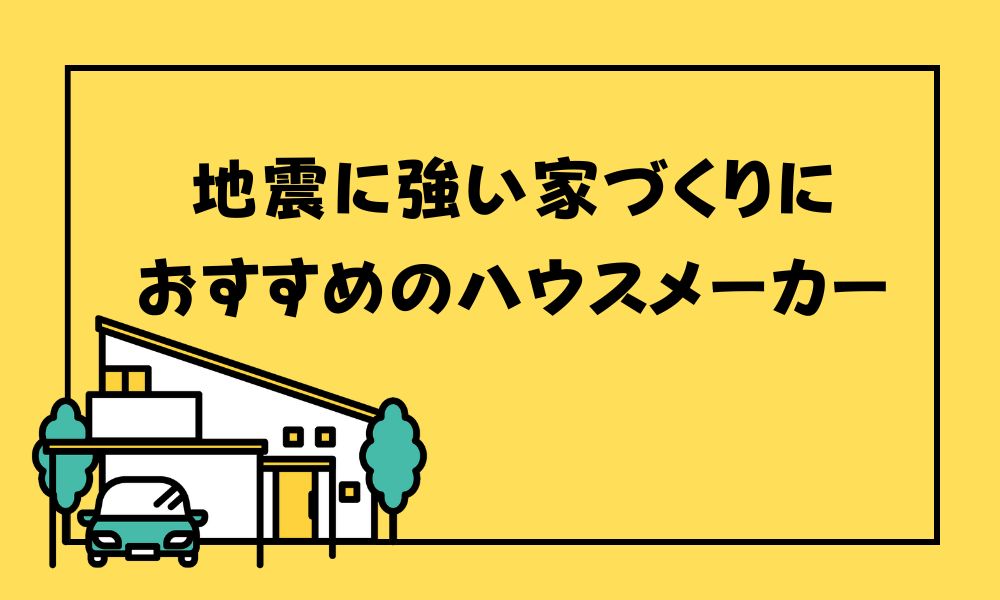
地震に強い家づくりを目指すなら、耐震技術に定評のあるハウスメーカーを選ぶことが重要です。
ここでは、木造と鉄骨造を得意とするハウスメーカーをいくつか紹介します。
木造住宅でおすすめのハウスメーカー
木造住宅は、日本の伝統的な建築様式であり、自然素材ならではの温かみと快適な居住性を実現できます。
耐震性にも優れており、適切な設計と施工を行うことで、地震に強い家づくりが可能です。
三井ホーム
三井ホームの「プレミアム・モノコック構法」は、屋根、壁、床を一体化した構造で、高い強度と耐震性を実現しています。
モノコック構造は、航空機や自動車にも採用されている技術で、外壁全体で荷重を支えるため、地震や風などの外力に強い構造です。
一条工務店
一条工務店の「ツインモノコック構造」は、2枚の壁パネルで建物を包み込む構造で、高気密・高断熱を実現しています。
高い断熱性能により、省エネルギーで快適な住まいを実現できます。
耐震性にも優れており、地震に強い家づくりが可能です。
ミサワホーム
ミサワホームの「木質パネル接着工法」は、工場で生産された高精度な木質パネルを接着することで、高い耐震性と気密性を実現しています。
工場生産による均一な品質管理により、安定した品質の住宅を提供しています。
住友林業
住友林業の「ビッグフレーム構法」は、大断面集成材を使用することで、高い耐震性と開放的な空間を実現しています。
大空間を実現しながらも、耐震性を確保できるため、デザイン性の高い住宅を建てることができます。
鉄骨住宅でおすすめのハウスメーカー
鉄骨住宅は、鉄骨の強度を活かした耐震性の高い住宅です。
間取りの自由度も高く、デザイン性の高い住宅を建てることができます。
ヘーベルハウス
ヘーベルハウスは、軽量で高強度なALCコンクリートを使用した独自の構造で、高い耐震性と耐火性を実現しています。
「ハイパワードクロスシステム」は、地震エネルギーを吸収し、建物の揺れを抑制する制震構造です。
セキスイハイム
セキスイハイムの「GAIASS(ガイアス)」は、ユニット工法と制震構造を組み合わせた独自の構造で、高い耐震性を実現しています。
工場で生産されたユニットを組み立てる工法により、工期を短縮し、安定した品質を確保しています。
積水ハウス
積水ハウスの「ダイナミックフレームシステム」は、強固な鉄骨架構と制震ダンパーを組み合わせた構造で、高い耐震性を実現しています。
「シーカス」は、積水ハウスが開発した制震装置で、地震エネルギーを効果的に吸収します。
ダイワハウス
ダイワハウスの「D-NΣQST(ディーネクスト)」は、高強度の鉄骨ラーメン構造と制震ダンパーを組み合わせた構造で、高い耐震性を実現しています。
制震システム「xevoΣ(ジーヴォシグマ)」は、地震エネルギーを吸収し、建物の揺れを抑えます。
パナソニックホームズ
パナソニックホームズの「アタックダンパー」は、地震エネルギーを吸収する制震装置で、建物の揺れを抑制します。
繰り返しの地震にも効果を発揮し、建物の損傷を最小限に抑えます。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
地震に強い家に関するQ&A

地震に強い家づくりに関する疑問や不安を解消するために、よくある質問と回答をまとめました。
Q:地震に強い間取りの秘訣は?
A:地震に強い間取りを実現するためには、以下のポイントに注意しましょう。
- 耐力壁のバランス: 耐力壁は、建物を支える重要な壁です。バランスよく配置することで、地震の力を効果的に分散し、建物の倒壊を防ぎます。偏った配置は、ねじれや変形のリスクを高めるため避けるべきです。
- 直下率の確保: 1階と2階の壁や柱の位置を揃えることで、建物の重心が安定し、耐震性が向上します。
- 開口部の配置: 窓やドアなどの開口部は、耐力壁の強度を弱める可能性があります。開口部の配置は、耐震性を考慮してバランスよく計画しましょう。
- 偏心率の低減: 建物の重心と剛心(建物の変形に対する抵抗の中心)が一致するように設計することで、地震時のねじれを防ぎます。
Q:耐震等級はどこまで必要?
A:建築基準法では、最低限の耐震性能として耐震等級1が定められています。
等級2は等級1の1.25倍、等級3は等級1の1.5倍の耐震性を持ちます。
等級3は、数百年に一度発生する大地震でも倒壊しないレベルの耐震性を備えているとされています。
Q:木造と鉄骨、どちらが有利?
A:木造と鉄骨、どちらにもメリット・デメリットがあり、一概にどちらが有利とは言えません。
- 木造: 柔軟性があり、地震の揺れを吸収しやすいというメリットがあります。また、コストパフォーマンスにも優れています。
- 鉄骨造: 強度が高く、耐火性にも優れています。間取りの自由度も高いですが、コストは木造よりも高くなる傾向があります。
Q:平屋 vs 2階建て:耐震性で選ぶなら?
A:一般的に、平屋は2階建てに比べて重心が低いため、耐震性に優れていると言われています。
ただし、2階建てでも適切な耐震設計を行うことで、十分な耐震性を確保できます。
Q:リフォームで耐震性は向上する?
A:耐震リフォームを行うことで、既存の住宅の耐震性を向上させることが可能です。
耐震診断を行い、必要な補強工事を行うことで、建物の耐震性を強化できます。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
まとめ
この記事では、地震大国である日本で安心して暮らすために、「地震に強い家」とは何か、そしてどのように実現するのかを詳しく解説しました。
単に倒壊しないだけでなく、地震後も家族の命と財産、そして生活を守ることができる家が、真に地震に強い家と言えるでしょう。
ぜひこの記事を参考にハウスメーカー選びにも気を遣いながら、理想の家を作ってくださいね。

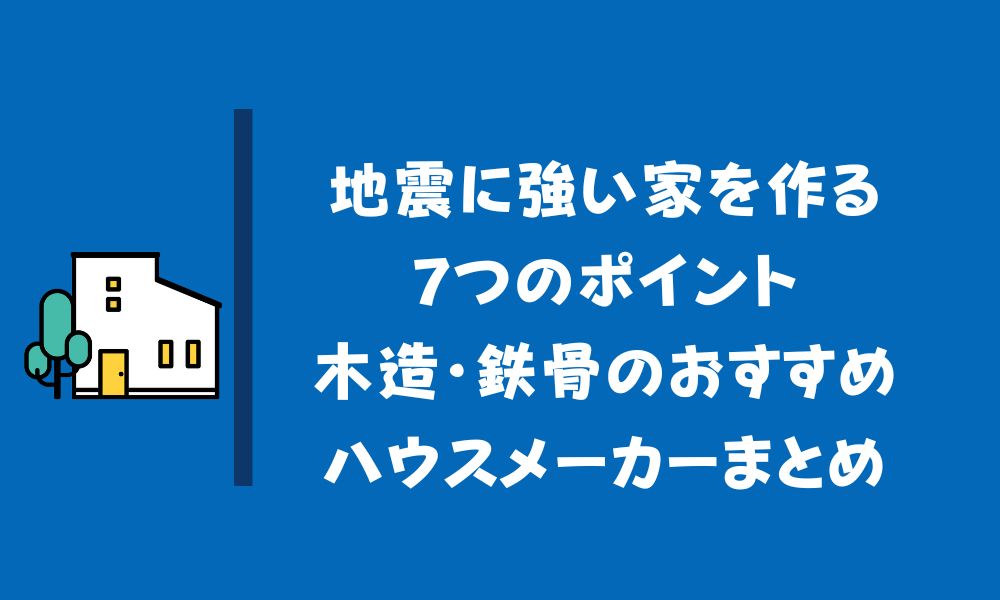

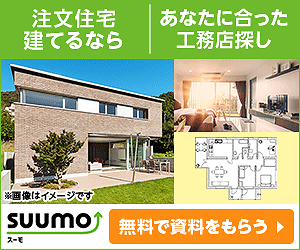


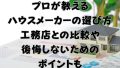

コメント