「家づくりをするとき、騒音問題に悩まされたくない」
「都市に家が欲しいけど、どれくらい音を遮断できるか疑問」
このように感じている人は多いでしょう。
そんな人におすすめなのが、「防音住宅」という選択肢です。
防音住宅にすることで、周囲の騒音を気にせず、自分だけの時間や家族の時間を楽しむことができます。
そこでこの記事では、防音住宅のメリット・デメリットから、防音の基礎知識、効果的な防音対策、費用相場、建築を依頼できる業者まで、防音住宅に関するあらゆる情報を解説していきます。
騒音に悩まされず快適な暮らしを実現したい人は、ぜひこの記事を参考にしてみてくださいね!
本文に入る前に、これから家づくりを考えている人や、現在進行形でハウスメーカー選びを進めている人に、後悔しない家づくりのための最も重要な情報をお伝えします。
早速ですが、質問です。
家づくりで一番大切なこと、それはなんだと思いますか?
おそらく間取りや予算、建てる場所などと考える人も多いかもしれませんね。
ですが実は、家づくりで最も大切なことは「気になっているハウスメーカーのカタログを、とりあえず全て取り寄せてしまうこと」なんです。
カタログを取り寄せずに住宅展示場に行き、営業マンの言葉巧みな営業トークに押されて契約を結んでしまうのは最悪なケース。
住宅展示場に行ってその場で契約をしてしまった人の中には、「もしもカタログを取り寄せて比較検討していたら、同じ間取りの家でも300万円安かったのに・・・」と後悔する人が本当に多いんです。
このように、もう少し情報収集をしていれば理想の家をもっと安く建てられていたのに、場合によっては何百万単位の損をして後悔してしまうこともあります。
だからこそ、きちんとした情報収集をせずにハウスメーカーを選ぶのは絶対にやめてください。
そんなことにならないようにハウスメーカーのカタログを取り寄せて比較検討することが最も重要なんです。

そうは言っても、気になるハウスメーカーはたくさんあるし、気になるハウスメーカー全てに連絡してカタログを取り寄せるなんて、時間と労力がかかりすぎるよ・・・
そう思う人も少なくありません。
そもそもどのように情報収集をしたら良いのかわからないという人もいるでしょう。
そんなあなたにぜひ活用してほしいサービスが、「ハウスメーカーのカタログ一括請求サービス」や「専門家に実際に相談してみること」です!
これらのサービスを活用することで、何十倍もの手間を省くことができ、損をするリスクも最大限に減らすことができます。
中でも、不動産業界大手が運営をしている下記の3つのサービスが特におすすめです。
|
東証プライム上場企業「LIFULL」が運営をしているカタログ一括請求サービスです。厳しい審査を通過した全国の優良住宅メーカーからカタログを取り寄せることが可能です。特にローコスト住宅に強いため、ローコスト住宅でマイホームを検討している人に非常におすすめです。 不動産のポータルサイトとしておそらく全国で最も知名度のあるSUUMOが運営しています。全国各地の工務店とのネットワークも豊富。住宅の専門家との相談をすることが可能で、住宅メーカー選びのみならず、家づくりの初歩的な質問から始めることが可能です。「何から始めたら良いのかわからない」と言う人はSUUMOに相談することがおすすめです。 上場企業でもあるNTTデータが運営しているサービスです。大手ということもあり、信頼も厚いのが特徴です。全国各地の大手ハウスメーカーを中心にカタログを取り寄せることができます。また、理想の家づくりプランを作ってもらえるのも嬉しいポイントです。 |
上記の3サイトはどれも完全無料で利用できる上、日本を代表する大手企業が運営しているため、安心して利用することができます。
また、厳しい審査基準で問題のある企業を事前に弾いているため、悪質な住宅メーカーに依頼してしまうというリスクを避けることも可能です。
正直言って、こちらの3サイトならどれを利用しても間違いはないでしょう。
また、どれを利用するか迷ったら、
- ローコスト住宅メーカーや大手ハウスメーカーを検討中:LIFULL HOME'Sでカタログ請求
- 工務店をメインで検討中:SUUMOカウンターで相談
- 資金計画や土地探しも相談したい:家づくりのとびら
というふうに使い分けてみるのもおすすめです。
そのほかに、SUUMOも無料カタログの一括請求サービスを提供しています。
こちらも無料なので、ぜひ利用してみることをおすすめします。
もちろんどのサービスも無料なため、全て活用してみるのもおすすめです。
後悔のない家づくりのため、1社でも多くの会社からカタログを取り寄せてみてくださいね!
\メーカー比較で数百万円得することも!/

【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる≫

【プロと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
家づくりで後悔しないために、これらのサービスをうまく活用しながら、ぜひあなたの理想を叶えてくれる住宅メーカーを見つけてみてください!
それでは本文に入っていきましょう!
防音住宅を建てる前に知っておきたいこと

まずは防音住宅の建築を検討する際のメリット・デメリット、注意点などを確認しましょう。
防音住宅のメリット・デメリット
防音住宅には、多くのメリットがある一方で、デメリットも存在します。
【メリット】
- 静かな生活環境の確保:最大のメリットは、静かな生活環境を手に入れられることです。外部からの騒音だけでなく、室内の生活音も軽減されるため、静かで落ち着いた空間で過ごすことができます。
- 趣味の充実:楽器演奏や音楽鑑賞、ホームシアターなどを、時間や音量を気にせず楽しめます。
- 近隣トラブルの回避:生活音による近隣トラブルを未然に防ぐことができます。周囲への配慮を欠かさず、良好な近隣関係を築く上で大きなメリットとなります。
- プライバシーの保護:家族間でも、それぞれのプライバシーを確保することができます。
- 資産価値の向上:防音性能の高い住宅は、一般的な住宅に比べて希少価値が高く、資産価値の向上も期待できます。将来的な売却時にも有利に働く可能性があります。
【デメリット】
- 建築費用の増加:防音対策には、専用の材料や工法が必要となるため、建築費用が通常の住宅よりも高くなる傾向があります。
- 部屋の狭さ:防音対策として壁を厚くしたり二重構造にする場合、部屋の広さが狭くなることがあります。限られたスペースを有効活用するための工夫が必要となります。
- 換気・採光への影響:防音性を高めるためには、窓の数を減らしたり、サイズを小さくする必要がある場合があり、換気や採光が悪くなる可能性があります。
防音の基礎知識
防音対策を効果的に行うためには、音の性質や伝わり方、防音に関する用語などを理解しておくことが重要です。
音の性質と伝わり方
音は、空気の振動によって伝わります。
空気中を伝わる音を「空気伝搬音」、壁や床などの固体を伝わる音を「固体伝搬音」といいます。
防音対策では、これらの両方に対応する必要があります。
例えば、話し声やテレビの音は空気伝搬音、足音やドアの開閉音は固体伝搬音に該当します。
遮音・吸音
これらは防音における重要なキーワードです。
それぞれの役割を理解することで、適切な防音対策を選択できます。
- 遮音:音を跳ね返すことで、音の伝わりを遮断します。コンクリートや遮音シート、鉛などが遮音材として用いられることが多いです。
- 吸音:音を吸収することで、音のエネルギーを減衰させます。グラスウールやロックウール、吸音パネルなどが吸音材として用いられることが多いです。
失敗しないための注意点
防音住宅の建築で失敗しないためには、事前の計画と準備が不可欠です。
以下の注意点に留意することで、理想的な防音住宅を実現することができます。
- 専門知識を持つ業者選び:防音住宅の建築には、専門知識と経験が不可欠です。実績やノウハウを持つ業者を選び、専門業者との連携も検討しましょう。
- ライフスタイルの変化を見据えた計画:将来的な家族構成やライフスタイルの変化を考慮し、柔軟性のある設計にしましょう。例えば、子供部屋の防音性能を高めたり、将来的なリフォームを想定した設計にするなど、長期的な視点で考えることが重要です。
- 適切な換気計画:防音性と換気の両立は重要です。換気設備の導入や間取りの工夫で、適切な換気を確保しましょう。24時間換気システムの導入や、窓の位置や大きさなどを工夫することで、空気の流れを確保できるでしょう。
- 周辺環境の確認:騒音源となる道路や施設などを確認し、土地選びに注意しましょう。騒音マップなどを活用することで、周辺環境の騒音レベルを把握できます。
- 予算とのバランス:防音対策は、費用がかかるため、予算とのバランスを考慮することが重要です。必要な防音レベルを明確にし、予算内で実現可能な範囲で対策を行うようにしましょう。
- 契約内容の確認:工事契約を結ぶ前に、契約内容をしっかりと確認しましょう。工事内容、費用、保証内容、工期などが明確に記載されているかを確認し、不明な点があれば、業者に確認するようにしましょう。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
注文住宅でできる効果的な防音対策

注文住宅では、様々な防音対策を施すことができます。
構造、間取り、設備、DIYなど、多角的なアプローチで防音性能を高めることが可能です。
構造編:家全体の防音性能を高める
家全体の防音性能を高めるためには、構造材の選択、壁・床・天井の構造、防振対策などが重要です。
- RC造(鉄筋コンクリート造):コンクリートの質量効果により、高い遮音性能を実現できます。耐火性、耐久性にも優れているため、マンションや高層ビルなどで多く採用されています。
- 鉄骨造:木造よりも遮音性が高いですが、RC造よりは劣ります。比較的工期が短く、設計の自由度も高いというメリットがあります。
- 木造:一般的に遮音性は低いとされていますが、適切な防音対策を施すことで、RC造や鉄骨造に匹敵する遮音性能を実現することも可能です。
- 壁・床・天井の二重構造:壁、床、天井を二重構造にすることで、空気層を設けることができます。空気層は、音を遮断する効果があるため、防音性能を向上させることができます。
間取り編:音の伝わり方をコントロールする
間取りの工夫によっても、効果的な防音対策を実現できます。
- 音源からの距離:騒音源となる道路や隣家から離れた場所に寝室や書斎などの静けさを必要とする部屋を配置することで、騒音の影響を軽減できます。
- 防音室の設置:楽器演奏や音楽鑑賞、ホームシアターなどを楽しむための防音室を設置することで、周囲への音漏れを防ぎ、集中できる空間を作れます。
- 間仕切りの工夫:廊下や収納スペースを挟むことで、部屋間の音の伝わりを遮断できます。
- 水回りの配置:水回りは、生活音の発生源となるため、寝室やリビングから離れた場所に配置することが望ましいです。
- 開口部の位置:窓やドアなどの開口部は音の出入り口となるため、騒音源に面した壁には、できるだけ開口部を設けないようにすることが大切です。
設備編:防音性能を高める設備を選ぶ
防音性能を高めるための設備を選ぶことで、より効果的な防音対策が可能です。
- 防音サッシ:二重サッシや、特殊なガラスを採用した防音サッシは、外部からの騒音を効果的に遮断します。
- 二重窓:既存の窓の内側にもう一枚窓を設置することで、空気層を作り、遮音性を高めます。比較的低コストで防音性能を向上させることができます。
- 防音ドア:遮音性能の高いドアは、気密性の高い構造や遮音材を内蔵することで、音漏れを防ぎます。
- 遮音フローリング:遮音性能の高いフローリングは、特殊な構造や下地材を用いることで、足音などを軽減します。LL-40、LL-45など、遮音等級によって性能が異なります。
- カーペット:カーペットは、音を吸収する効果があるため、床に敷くことで防音対策になります。厚手のカーペットほど吸音効果が高くなります。
- 防音型換気扇:遮音性能の高い換気扇は、外部からの騒音の侵入を防ぎます。ダクト内部に消音効果のある素材を使用することで、騒音を軽減します。
DIY編:自分でできる防音対策
比較的低コストでできるDIYによる防音対策も効果的です。
- 防音カーテン・遮音シートの設置:窓や壁に取り付けることで、遮音効果を高めます。厚手で遮光性の高いカーテンや、特殊な素材で作られた遮音シートなどがあります。
- 家具の配置工夫:背の高い家具を壁際に置くことで、音を遮断する効果があります。本棚などを壁際に配置することで、音の伝わりを軽減できます。
- 100均グッズの活用:100均で販売されているグッズを活用したDIYも効果的です。例えば、隙間テープやクッション材などを利用して、隙間を塞ぐことができます。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
【タイプ別】防音室の設置方法と費用相場

防音室の設置方法は大きく分けて、「部屋全体を防音室にする」方法と「組み立て式の防音室を設置する」方法の2種類があります。
それぞれのメリット・デメリット、費用相場、用途などを解説します。
部屋全体を防音室にする
既存の部屋全体を防音室に改修する方法です。
本格的な防音性能を実現できるため、音楽スタジオやオーディオルームなど、高い遮音性能を必要とする用途に適しています。
メリット
- 高い遮音性能を実現できる:壁、床、天井、窓、ドアなど、部屋全体に防音対策を施すため、高い遮音性能を実現できます。D-70以上の遮音性能を実現することも可能です。
- 広々とした空間を確保できる:既存の部屋を利用するため、組み立て式の防音室に比べて広々とした空間を確保できます。
- 設計の自由度が高い:部屋の形状や大きさに合わせて、自由に設計することができます。
デメリット
- 工事費用が高額になる:大規模な工事が必要となるため、費用が高額になる傾向があります。
- 工期が長くなる:工事期間が長くなるため、生活への影響も大きくなります。
費用相場
部屋の広さや仕様、遮音性能によって大きく変動しますが、数百万円から数千万円程度かかる場合もあります。
組み立て式の防音室
プレハブのような形で、工場で製造された防音室を部屋の中に設置する方法です。
手軽に設置できるため、書斎や楽器練習室など、比較的簡易な防音で十分な場合に適しています。
メリット
- 設置が容易:組み立て式のため、設置が容易で工期も短縮できます。
- 移動が可能:必要に応じて、移動させることができます。
- 費用を抑えられる:部屋全体を防音室にするよりも、費用を抑えることができます。
デメリット
- 遮音性能は部屋全体を防音室にする場合に比べて劣る:完全な遮音は難しく、音漏れのリスクがあります。
- スペースが必要:設置スペースが必要となるため、部屋の広さが狭くなります。
費用相場
サイズや遮音性能によって変動しますが、数十万円から数百万円程度が相場です。
用途
書斎、楽器練習室、ボーカルブース、テレワークブースなど、比較的簡易な防音で十分な場合に適しています。
DIYで防音室を作る
費用を抑えたい場合は、DIYで防音室を作るという方法もあります。
ただし、遮音性能は専門業者に依頼する場合に比べて劣るため、簡易的な防音対策として検討しましょう。
メリット
- 費用を大幅に抑えられる
- 自分好みにカスタマイズできる
デメリット
- 遮音性能は低い
- 労力と時間がかかる
費用相場
使用する材料によって異なりますが、数万円から数十万円程度で作成可能です。
用途
簡易的な防音ブース、楽器練習室などの用途に使用することができます。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
【2024年最新】防音住宅建築を依頼できる業者

防音住宅の建築を依頼できる業者は、ハウスメーカー、工務店、防音工事専門業者などがあります。
それぞれのメリット・デメリットを理解し、最適な業者を選びましょう。
防音に強いハウスメーカー
大手ハウスメーカーは、防音住宅の建築実績が豊富で、専門知識を持ったスタッフが在籍しているため、安心して依頼することができます。
また、保証やアフターサービスが充実している点もメリットです。
- 積水ハウス:高気密・高断熱に加え、高い遮音性能を備えています。独自の制振技術により、地震や風による振動も軽減します。
- ダイワハウス:「音の自由区」という防音室のラインナップがあり、用途に合わせて防音グレードを選ぶことができます。xevoΣ(ジーヴォシグマ)など、高い遮音性能を備えた住宅商品も展開しています。
- ミサワホーム:高い遮音等級を誇り、防音室の施工実績も豊富です。「蔵」と呼ばれる収納空間を活用した防音室の提案なども行っています。
- 富士住建:「完全フル装備の家」という商品ブランドがあり、防音室をオプションで追加できます。目的に合わせたグレードを選べるため、コストを抑えながら防音対策ができます。
- 一条工務店:高気密・高断熱住宅を得意としており、防音室との組み合わせ事例もあります。i-smartやi-cubeといった高性能住宅は、気密性が高いため、防音性能も高いです。
- パナソニックホームズ:キラテックタイルを採用した高耐久住宅が特徴です。高い気密性と断熱性を備え、防音性能にも優れています。
- ヘーベルハウス:ALCコンクリートを使用した重量鉄骨住宅が特徴です。ALCコンクリートは、遮音性、耐火性、断熱性に優れており、高い防音性能を実現できます。
防音工事専門業者
防音工事専門業者は、防音に関する専門知識と技術力に特化しているため、より高度な防音対策を求める場合に適しています。
ハウスメーカーでは対応できない特殊なニーズにも対応できる点がメリットです。
メリット
- 防音に関する専門知識と技術力が高い:専門業者だからこそ可能な、きめ細やかな防音設計・施工が可能です。特定の音域への対策や、特殊な環境への対応など、専門的な知識と経験に基づいた提案を受けることができます。
- 幅広いニーズに対応可能:ハウスメーカーでは対応できないような特殊な防音工事にも対応可能です。
選び方のポイント
実績、保証内容、対応力などを確認しましょう。
複数の業者に見積もりを依頼し、比較検討することが重要です。
費用相場
工事内容や規模によって大きく異なりますが、一般的にはハウスメーカーに依頼するよりも高額になる傾向があります。
工務店
地域密着型の工務店の中には、防音住宅の建築に力を入れているところもあります。
ハウスメーカーに比べて、小回りが利き、柔軟な対応が期待できる点がメリットです。
メリット
- 地域密着型で、きめ細やかな対応が可能:地域の情報に精通しており、顧客のニーズに合わせた柔軟な対応が可能です。
- ハウスメーカーに比べて費用を抑えられる場合もある:中間マージンが発生しないため、ハウスメーカーに比べて費用を抑えられる場合があります。
選び方のポイント
防音工事の実績や、専門知識の有無を確認しましょう。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
防音住宅建築の成功事例

ここでは防音住宅の具体的な事例をみていきましょう。
楽器演奏を楽しむ家
- 事例1:ピアノ教室を自宅で開いている施主が、レッスン室として防音室を設置。近隣への音漏れを気にせず、いつでもレッスンができるようになっただけでなく、自身も時間を気にせず演奏を楽しめるようになりました。
- 事例2:趣味でドラム演奏を楽しむ施主が、自宅に防音室を設置。以前は、時間帯を制限したり、防音対策が不十分なため思う存分演奏できなかったのが、防音室のおかげで好きな時間に好きなだけ演奏できるようになり、ストレス解消にも繋がっているそうです。
- 事例3:家族で様々な楽器を演奏する施主が、広い防音室を設置。家族それぞれが好きな楽器を演奏できるようになったとのことです。
静かな環境で仕事に集中できる家
- 事例1:在宅ワークが増えた施主が、書斎を防音室に改装。周囲の騒音を気にせず、仕事に集中できるようになり、作業効率が格段に向上したとのことです。Web会議なども安心して行えるようになり、仕事環境が大きく改善されました。
- 事例2:作曲や執筆活動を行うクリエイターの施主が、防音室を設置。静かな環境で作業に没頭できるようになり、創造性が向上したと実感しているそうです。
家族みんなが快適に過ごせる家
- 事例1:小さなお子様がいる施主が、防音住宅を建築。子供たちの泣き声や遊び声が近隣に漏れる心配がなくなり、安心して子育てができるようになったとのことです。
- 事例2:二世帯住宅で生活時間帯の異なる家族が、お互いの生活音に悩まされないよう、防音対策を施しました。プライバシーが確保できるようになり、快適な二世帯生活を送れるようになったとのことです。
- 事例3:ペットの鳴き声に悩んでいた施主が、ペット専用の防音室を設置。近隣への鳴き声の漏れを防ぐことができ、近隣トラブルも解消されたそうです。
これらの事例はあくまでも一例です。防音住宅の効果は、個々のライフスタイルやニーズによって異なります。
様々な事例を参考にしながら、自身のライフスタイルやニーズに合った防音対策を検討しましょう。
専門業者に相談することで、より具体的なアドバイスを受けることもできますよ。
まとめ
この記事では防音住宅について、メリットやデメリット、防音室の作り方などを解説しました。
防音住宅にすることで快適な住空間を実現できますが、同時に大きなお金がかかります。
そのため、必要な防音対策を見極め、予算と相談しながら判断することが重要です。
騒音が多いエリアに住んでいる人や、趣味を楽しむために防音室が欲しい人は、ぜひ防音住宅や防音室の設置を考えてみてはいかがでしょうか。
この記事が防音住宅の参考になれば嬉しいです!
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫



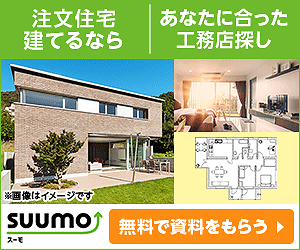




コメント