世帯年収900万円は、日本の世帯全体で見れば上位層に入り、夢のマイホーム購入がぐっと現実味を帯びてくる収入ラインです。金融機関からも高い評価を得やすく、選択できる物件の幅も広がるため、期待に胸を膨らませている方も多いのではないでしょうか。
しかし、その「選択肢の多さ」と「借入可能額の大きさ」こそが、思わぬ落とし穴になりかねません。
金融機関が提示する「貸せる上限額」と、あなたの家庭が将来にわたって無理なく「返せる適正額」は全くの別物です。
高収入に安心して、安易に上限額いっぱいでローンを組んでしまうと、数十年後、「こんなはずではなかった…」と後悔する「住宅ローン貧乏」に陥ってしまう危険性があります。
そこでこの記事では、年収900万円世帯の手取り額や家計の実態から、具体的な返済シミュレーション、そして失敗しないための計画の立て方まで解説します。
ぜひ最後まで参考にしてみてくださいね。
本文に入る前に、これから家づくりを考えている人や、現在進行形でハウスメーカー選びを進めている人に、後悔しない家づくりのための最も重要な情報をお伝えします。
早速ですが、質問です。
家づくりで一番大切なこと、それはなんだと思いますか?
おそらく間取りや予算、建てる場所などと考える人も多いかもしれませんね。
ですが実は、家づくりで最も大切なことは「気になっているハウスメーカーのカタログを、とりあえず全て取り寄せてしまうこと」なんです。
カタログを取り寄せずに住宅展示場に行き、営業マンの言葉巧みな営業トークに押されて契約を結んでしまうのは最悪なケース。
住宅展示場に行ってその場で契約をしてしまった人の中には、「もしもカタログを取り寄せて比較検討していたら、同じ間取りの家でも300万円安かったのに・・・」と後悔する人が本当に多いんです。
このように、もう少し情報収集をしていれば理想の家をもっと安く建てられていたのに、場合によっては何百万単位の損をして後悔してしまうこともあります。
だからこそ、きちんとした情報収集をせずにハウスメーカーを選ぶのは絶対にやめてください。
そんなことにならないようにハウスメーカーのカタログを取り寄せて比較検討することが最も重要なんです。

そうは言っても、気になるハウスメーカーはたくさんあるし、気になるハウスメーカー全てに連絡してカタログを取り寄せるなんて、時間と労力がかかりすぎるよ・・・
そう思う人も少なくありません。
そもそもどのように情報収集をしたら良いのかわからないという人もいるでしょう。
そんなあなたにぜひ活用してほしいサービスが、「ハウスメーカーのカタログ一括請求サービス」や「専門家に実際に相談してみること」です!
これらのサービスを活用することで、何十倍もの手間を省くことができ、損をするリスクも最大限に減らすことができます。
中でも、不動産業界大手が運営をしている下記の3つのサービスが特におすすめです。
|
東証プライム上場企業「LIFULL」が運営をしているカタログ一括請求サービスです。厳しい審査を通過した全国の優良住宅メーカーからカタログを取り寄せることが可能です。特にローコスト住宅に強いため、ローコスト住宅でマイホームを検討している人に非常におすすめです。 不動産のポータルサイトとしておそらく全国で最も知名度のあるSUUMOが運営しています。全国各地の工務店とのネットワークも豊富。住宅の専門家との相談をすることが可能で、住宅メーカー選びのみならず、家づくりの初歩的な質問から始めることが可能です。「何から始めたら良いのかわからない」と言う人はSUUMOに相談することがおすすめです。 上場企業でもあるNTTデータが運営しているサービスです。大手ということもあり、信頼も厚いのが特徴です。全国各地の大手ハウスメーカーを中心にカタログを取り寄せることができます。また、理想の家づくりプランを作ってもらえるのも嬉しいポイントです。 |
上記の3サイトはどれも完全無料で利用できる上、日本を代表する大手企業が運営しているため、安心して利用することができます。
また、厳しい審査基準で問題のある企業を事前に弾いているため、悪質な住宅メーカーに依頼してしまうというリスクを避けることも可能です。
正直言って、こちらの3サイトならどれを利用しても間違いはないでしょう。
また、どれを利用するか迷ったら、
- ローコスト住宅メーカーや大手ハウスメーカーを検討中:LIFULL HOME'Sでカタログ請求
- 工務店をメインで検討中:SUUMOカウンターで相談
- 資金計画や土地探しも相談したい:家づくりのとびら
というふうに使い分けてみるのもおすすめです。
そのほかに、SUUMOも無料カタログの一括請求サービスを提供しています。
こちらも無料なので、ぜひ利用してみることをおすすめします。
もちろんどのサービスも無料なため、全て活用してみるのもおすすめです。
後悔のない家づくりのため、1社でも多くの会社からカタログを取り寄せてみてくださいね!
\メーカー比較で数百万円得することも!/

【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる≫

【プロと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
家づくりで後悔しないために、これらのサービスをうまく活用しながら、ぜひあなたの理想を叶えてくれる住宅メーカーを見つけてみてください!
それでは本文に入っていきましょう!
世帯年収900万円でも住宅ローンは計画が重要

まずは、ご自身の世帯が社会的にどのような位置づけにあるのかを客観的に把握することから始めましょう。
年収900万円は高所得層?
厚生労働省の「国民生活基礎調査の概況」(2020年)によると、日本の全世帯における所得の中央値は440万円です。
また、総務省統計局の「2021年家計調査」では、世帯年収が900万円台の家庭は全体のわずか5%と報告されています。
これらのデータから、世帯年収900万円は日本のなかで上位層に入る、比較的高所得な世帯であることは間違いありません。
この収入レベルであれば、金融機関からの評価も高まり、住宅ローンの選択肢も広がるでしょう。
「借りられる額」と「無理なく返せる額」
住宅ローンを検討する上で最も重要な心構えは、「金融機関が貸してくれる上限額」と「自分たちが将来にわたって無理なく返せる額」は全く違うということです。
金融機関は、あなたの年収や勤務先といった情報から「返済能力」を算出し、融資の上限額を提示します。しかし、その計算には、あなたご自身のライフプランや価値観は含まれていません。
例えば、子どもの教育方針、趣味や旅行にかける費用、老後の生活設計など、将来の家計に影響を与える個人的な支出までは考慮してくれないのです。
金融機関が提示する「借りられる額」を鵜呑みにして上限額いっぱいでローンを組んでしまうと、購入後の生活がローンの返済に追われ、他のことにお金を使えない「住宅ローン貧乏」に陥ってしまう危険性があります。
住宅ローンで後悔しないためのポイント
高収入世帯は借入可能額が大きくなるため、つい予算を上げてしまいがちです。
しかし、数十年という長期にわたる返済期間中には、予期せぬライフイベントが起こる可能性も十分に考えられます。
転職や病気による収入減、家族構成の変化による支出増など、様々なリスクが存在します。
だからこそ、年収の高さに安心するのではなく、ご自身の家庭にとっての「適正な借入額」を冷静に見極めることが、後悔しない住宅購入の第一歩となります。
世帯年収900万円の手取りと家計の実態

無理のない住宅ローン計画を立てるためには、まず現在の家計を正確に把握することが不可欠です。
月々の手取り収入はどのくらい?(共働き・片働きの場合)
年収900万円といっても、税金や社会保険料が差し引かれるため、全額が手元に残るわけではありません。
一般的に、手取り額は額面年収のおよそ75%〜85%とされ、年収900万円の場合は年間で約675万円〜765万円、月々に換算すると約56万円〜64万円が目安となります。
さらに、同じ世帯年収900万円でも、働き方によって手取り額に差が生じる点も押さえておきましょう。
- 片働き世帯のケース(例:夫が年収900万円、妻が専業主婦):手取り年収の目安は約650万円〜670万円、月々の手取り額は約54万円〜56万円となります。
- 共働き世帯のケース(例:夫が年収500万円、妻が年収400万円):夫婦の合計手取り年収は約720万円、月々の手取り額は約60万円が目安です。
このように、共働き世帯の方が片働き世帯よりも手取り額が多くなる傾向があります。
これは、所得税や住民税が収入に応じて税率の上がる「累進課税」という仕組みを採用しているためです。
収入を夫婦で分散させることで、一人で高額な収入を得るよりも世帯全体での税負担が軽減されるのです。
住宅ローン返済の原資はいくら?
次に、手取り収入から毎月いくらを住宅関連費に充てられるのかを考えてみましょう。
総務省統計局の2022年「家計調査報告・家計収支編」によると、年収900万円〜1,000万円の世帯における1ヶ月あたりの生活費(住居費を除く)は、平均で約36万2,761円です。
その内訳の一例は以下の通りです。
ご自身の家計と見比べてみてください。
- 食費:約89,512円
- 水道・光熱費:約26,078円
- 家具・家事用品費:約14,198円
- 被服費:約14,317円
- 保健医療費:約17,293円
- 交通・通信費:約62,582円
- 教育費:約23,038円
- 教養・娯楽費:約36,248円
- その他(交際費など):約79,495円
仮に手取り月収が54万円〜60万円だとすると、この平均的な生活費を差し引いた後、手元には毎月約18万円〜24万円が残る計算になります。
この金額が、住宅ローンの返済や将来のための貯蓄、投資などに充てられる資金の目安となります。
住宅購入の元手となる貯蓄額のリアル
住宅購入には、頭金や諸費用といったまとまった資金が必要です。
2022年の「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査]」によれば、年収750万円〜1,000万円の世帯における預貯金残高の平均は570万円というデータがあります。
また、別の調査「日本の統計2021」では、年収757万円〜969万円以上の勤労世帯の平均貯蓄額は1,535万円、住宅ローンを含む負債額は1,075万円でした。
これらの数字は、多くの世帯が貯蓄と並行して住宅ローンなどの返済を行っている実態を示しています。
ご自身の貯蓄額と照らし合わせ、無理のない頭金の額や、購入後の生活を守るための予備費をどれくらい確保すべきか、具体的に計画することが重要です。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
住宅ローン借入額の目安と適正額

住宅ローンの計画において、多くの人が最初に疑問に思うのが「一体いくらまで借りられるのか?」ということでしょう。
しかし、ここで冷静になる必要があります。
金融機関が提示する「借入上限額」と、あなたの家庭が将来にわたって安定して返済できる「適正借入額」には、大きな隔たりがあるからです。
金融機関が提示する「借入上限額」
金融機関は、主に「返済負担率」と「年収倍率」という2つの指標を用いて、融資できる金額の上限を判断します。
- 返済負担率(年収に占める年間のローン返済額の割合):多くの金融機関がこの指標を重視しています。例えば、住宅金融支援機構が提供する「フラット35」では、年収400万円以上の世帯の返済負担率の上限を35%以下と定めています。これを年収900万円の世帯に当てはめると、年間の返済上限額は900万円 × 35% = 315万円(月額約26万円)となります。この返済額を基準に、金利1.84%、返済期間35年でシミュレーションすると、借入可能額はなんと約8,046万円と算出されます。
- 年収倍率(住宅購入価格が年収の何倍かを示す指標):こちらも借入額の目安としてよく使われます。一般的に適正範囲は年収の5倍〜6倍とされ、2021年のフラット35利用者調査では、中古マンション購入者の平均年収倍率は5.8倍でした。年収900万円の場合、4,500万円〜5,400万円が物件価格の一つの目安となります。より具体的には、新築物件で年収の6.5倍〜7.5倍(5,850万円〜6,750万円)、中古物件で5倍〜6倍(4,500万円〜5,400万円)が目安とされています。
しかし、これらの数字はあくまで金融機関が「これだけ貸せますよ」と判断した理論上の上限額に過ぎません。
この金額を鵜呑みにしてしまうと、将来の家計を圧迫するリスクが高まります。
現実的な「適正借入額」はいくら?
では、実際に年収900万円世帯はどのくらいの金額を借り入れているのでしょうか。
住宅金融支援機構の「2023年度 フラット35利用者調査」によると、年収900万円台の世帯の平均借入額は5,261万円でした。
これは、先ほどの借入上限額の目安である約8,000万円よりも、3,000万円近くも少ない金額です。
この事実は、多くの世帯が上限額よりもかなり保守的な借入を選択していることを示しています。
無理なく返済できる「適正借入額」を考える上で、より現実的な指標となるのが、手取り年収に対する返済負担率です。
多くの専門家は、この割合を20%〜25%以内に抑えることを推奨しています。
年収900万円世帯にとって本当に安心して返済していける借入額は、おおよそ4,000万円台後半から5,000万円台前半が一つの目安と言えるでしょう。
この金額が、あなたの家庭の生活を守りながらマイホームの夢を叶えるための、現実的なラインとなります。
【シミュレーション】借入額・期間・金利タイプ別の返済イメージ

適正な借入額の目安がわかったところで、次は具体的な数字を使って、月々の返済が家計にどのような影響を与えるのかをシミュレーションしてみましょう。
借入額4,000万円の場合(安全圏)
年収900万円世帯にとって、借入額4,000万円は比較的安全性が高く、精神的にもゆとりの持てる水準です。
- 条件:フラット35(金利1.84%)、返済期間35年
- 月々の返済額:約130,000円
手取り月収を54万円と仮定すると、返済負担率は約24%となり、理想とされる25%以内に収まります。
返済後も手元に41万円が残るため、平均的な生活費(約36万円)を差し引いても毎月5万円程度の余裕が生まれます。
この余裕資金を、子どもの教育費の積立や老後資金の準備、家族旅行などの娯楽費に充てることができ、住宅ローン返済に追われることなく、豊かな生活を送ることが可能です。
借入額5,000万円の場合(適正上限)
借入額5,000万円は、年収900万円世帯の平均的な借入額に近く、適正ラインの上限といえる水準です。
- 条件:金利1.5%、返済期間35年
- 月々の返済額:約154,000円
手取り月収を56万円とすると、返済負担率は約27.5%となり、理想の25%を少し超えます。
このレベルになると、計画的な家計管理が求められます。
返済後の手取りは約40万6,000円となり、生活費を差し引いた後の余裕資金は約4万6,000円です。
将来の教育費や万が一の病気・失業、そして金利が上昇した際の返済額増加にも耐えられるよう、意識的に支出を管理し、貯蓄に回していく必要があります。
借入額6,000万円の場合(高リスク)
借入額6,000万円は、適正額を大きく超える、かなり挑戦的な借入額です。
- 条件:フラット35(金利1.84%)、返済期間35年
- 月々の返済額:約194,000円
手取り月収56万円に対する返済負担率は約35%に達し、家計を著しく圧迫します。
返済後の手取りは約36万6,000円となり、平均生活費を差し引くと手元に残るのはわずか数千円です。
ここに固定資産税や修繕費などの住宅維持費(月3〜4万円)を加味すると、家計は赤字になりかねません。
この借入レベルが許容されるのは、将来の大幅な昇給がほぼ確実な場合や、潤沢な貯蓄がありいつでも繰り上げ返済できるなど、ごく限定的な世帯のみでしょう。
返済期間が月々の負担と総返済額に与える影響
返済期間を長くすれば月々の負担は軽くなりますが、利息が増え総返済額は膨らみます。
逆に期間を短くすれば、総返済額は減りますが月々の負担は重くなります。
シミュレーション例:借入額4,381万円、金利1.54%(全期間固定)
- 返済期間35年:月々返済額 約135,000円 / 総返済額 約5,670万円
- 返済期間30年:月々返済額 約152,000円 / 総返済額 約5,473万円
- 返済期間25年:月々返済額 約176,000円 / 総返済額 約5,281万円
35年と25年では、月々の負担に約4万円の差が出る一方、総返済額では約389万円もの差が生まれます。
ご自身の定年退職時期なども考慮し、月々のキャッシュフローと総支払額のどちらを優先するか、慎重に判断する必要があります。
金利タイプ別の返済イメージ
金利タイプの選択は、返済額を大きく左右します。
シミュレーション例:借入額4,381万円、返済期間35年
- 全期間固定金利(2.13%):月々返済額 約148,000円 / 総返済額 約6,219万円
- 変動金利(0.537%):月々返済額 約114,000円 / 総返済額 約4,807万円 ※金利変動なしの場合
金利が低い変動金利は当初の返済額を大きく抑えられますが、将来の金利上昇リスクを伴います。
一方、固定金利は返済額が変わらない安心感がありますが、金利は高めに設定されています。
どちらが最適かは、ご自身の家計のリスク許容度によって異なります。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
住宅ローン以外にかかる費用

夢のマイホーム計画で、物件価格や月々のローン返済額にばかり目が行きがちですが、実は住宅購入にはそれ以外にも多くの費用が発生します。
これらの「見えないコスト」を事前に把握しておかなければ、せっかくの資金計画が根底から崩れてしまう危険性があります。
住宅購入時に発生する諸費用(物件価格の7%〜10%)
住宅を購入する際には、物件の価格とは別に「諸費用」と呼ばれるまとまったお金が必要です。
これはローンに含められない場合も多く、基本的に現金で用意する必要があります。
一般的に、新築物件では物件価格の3%〜7%、中古物件では6%〜10%が目安とされており、5,000万円の物件であれば、およそ350万円から500万円程度の諸費用がかかる計算になります。
主な諸費用の内訳は以下の通りです。
税金関係
- 印紙税:不動産売買契約書やローン契約書に貼る印紙代。
- 登録免許税:購入した土地や建物の所有権を法務局に登記する際にかかる税金。
- 不動産取得税:不動産を取得した際に一度だけかかる税金。購入後しばらくして納税通知書が届きます。
住宅ローン関係
- 融資事務手数料:金融機関に支払う手数料。借入額の2.2%といった定率型や、3万円〜5万円程度の定額型があります。
- ローン保証料:万が一返済できなくなった場合に備え、保証会社に支払う費用。数十万円から数百万円になることもあります。
- 団体信用生命保険料:多くの住宅ローンでは金利に含まれていますが、別途必要な場合もあります。
その他
- 火災保険料・地震保険料:万が一の災害に備える保険料。10年分などを一括で支払うと数十万円単位の出費になります。
- 司法書士報酬:所有権移転登記などの手続きを代行してもらう専門家への報酬。10万円〜20万円が目安です。
- 仲介手数料(中古物件の場合):不動産会社に支払う手数料。「物件価格の3%+ 6万円+消費税」が上限です。
- その他:引っ越し代や、新しい生活に合わせた家具・家電の購入費用も忘れてはなりません。
購入後の年間維持費
住宅は購入して終わりではありません。
所有している限り、継続的に「維持費」がかかります。
これらの費用は、年間で50万円以上になるケースも珍しくなく、長期的な家計計画に組み込んでおく必要があります。
- 税金:毎年1月1日時点の所有者に「固定資産税」と「都市計画税」が課税されます。物件や地域によりますが、年間10万円〜20万円程度の負担は覚悟しておきましょう。
- 保険料:火災保険や地震保険は数年ごとに更新が必要で、その都度まとまった費用が発生します。
- マンションの場合:管理費(月々1万円〜2万円程度)、修繕積立金(月々1万円〜3万円程度)、また駐車場代・駐輪場代など。
- 一戸建ての場合:マンションのような管理費はありませんが、外壁や屋根の塗装、給湯器などの設備交換といったメンテナンス費用はすべて自己責任で準備する必要があります。将来の大きな出費に備え、計画的に年間10万円〜30万円程度を積み立てておくのが賢明です。
理想的な「総住居費」の割合
重要なのは、月々のローン返済額だけでなく、これらの維持費まで含めた「総住居費」で家計を管理することです。
専門家の間では、この総住居費を手取り収入の30%以下に抑えるのが理想的とされています。
年収900万円(手取り年収約650万円〜672万円)の世帯であれば、年間の総住居費の上限は約195万円〜201万円、月々に換算すると約16万円〜17万円が目安となります。
住宅ローンの返済額を決める際は、この維持費分を差し引いた上で、無理のない金額を設定することが極めて重要です。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
年収900万円世帯に最適な住宅ローンの組み方

同じ世帯年収900万円でも、その収入構成によって住宅ローンの最適な組み方は異なります。
一人の収入で900万円を稼ぐのか、夫婦の収入を合算して900万円になるのか、それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご自身の家庭に最も合った戦略を選択することが、長期的な安定につながります。
単独で住宅ローンを組む場合の考慮点
夫または妻のどちらか一人が年収900万円を稼ぎ、単独で住宅ローンを組むケースです。
メリット
- 収入の安定性が高く評価され、金融機関の審査に通りやすい傾向があります。
- 手続きがシンプルで、契約者が一人であるため意思決定がスムーズです。
- 住宅ローン控除(減税)の恩恵を一人で最大限に受けられる可能性があります。
注意点と対策
- 最大の懸念点は、収入源が一つに集中していることです。万が一、病気やケガ、失業などで主たる稼ぎ手の収入が途絶えてしまった場合、返済が即座に困難になるリスクを抱えています。
- このリスクに備えるため、返済計画はより保守的に考えるべきです。月々の返済額を手取りの20%〜25%以内に厳守することはもちろん、不測の事態に備えて生活費の6ヶ月分以上の緊急予備資金を確保しておくことが極めて重要です。
- また、通常の団体信用生命保険(団信)に加え、がん・脳卒中・急性心筋梗塞の三大疾病や、その他の疾病・ケガによる就業不能状態を保障する特約付きの団信への加入を積極的に検討しましょう。
夫婦合算で住宅ローンを組む場合
夫婦の収入を合算して世帯年収900万円とする場合、ローンの組み方には主に3つの選択肢があり、それぞれに特徴があります。
ペアローン
- 概要:夫婦それぞれが個別の住宅ローンを契約し、お互いが相手のローンの連帯保証人になります。
- メリット:夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられるため、世帯全体での節税効果が最も高くなります。また、それぞれが団信に加入するため、どちらか一方に万が一のことがあった場合、その人のローン残債は保険で完済されます。
- デメリット:ローン契約が2本になるため、印紙税や事務手数料などの諸費用が2人分かかり、コストが割高になります。
収入合算(連帯債務型)
- 概要:夫婦のどちらかが主たる債務者となり、もう一方が連帯債務者として一つの住宅ローンを契約します。夫婦ともに返済義務を負います。
- メリット:諸費用は1本分で済みます。フラット35など一部の金融機関では、夫婦それぞれが持ち分に応じて住宅ローン控除を受けられます。
- デメリット:団信は基本的に主たる債務者しか加入できません。連帯債務者に万が一のことがあっても、ローンの返済義務は残ってしまう点に注意が必要です(近年は夫婦連生団信などもありますが、保険料は割高です)。
収入合算(連帯保証型)
- 概要:どちらか一方が債務者となり、もう一方は連帯保証人となります。返済義務は債務者にありますが、返済が滞った場合は連帯保証人が返済義務を負います。
- メリット:手続きが比較的シンプルです。
- デメリット:住宅ローン控除や団信の対象は債務者のみです。連帯保証人は返済義務を負う可能性があるにもかかわらず、これらの恩恵を受けられないため、他の方法に比べてメリットは少ないと言えます。
共働き世帯が陥りやすい「借りすぎの罠」
共働き世帯の強みは収入の高さですが、それゆえに「二人なら大丈夫」と借入額を大きくしてしまう「借りすぎの罠」に陥りやすい傾向があります。
特に、将来の出産や育児による一時的な収入減、子どもの成長に伴う教育費の増加、どちらかの転職など、ライフステージの変化による収入変動リスクは常に考慮しなければなりません。
最も安全な戦略は、「片方の収入だけでも無理なく返済できる範囲」で借入額を設定することです。
例えば、主たる稼ぎ手(夫または妻)の年収をベースに返済計画を立て、もう一方の収入は「ないもの」として考え、頭金の増額や教育資金、繰り上げ返済用の資金として貯蓄に回すという方法です。
この戦略をとることで、将来の不確実性に対する備えが万全になり、安心して返済を続けていくことができます。
後悔しない年収900万円世帯の住宅ローン返済計画

年収900万円という恵まれた収入は、住宅購入において大きなアドバンテージとなります。
しかし、その一方で「これだけ収入があるのだから、多少高い物件でも大丈夫だろう」という油断が生じやすく、それが数十年後に大きな後悔を生む原因にもなりかねません。
ここでは、長期にわたる返済期間を安心して乗り切るために、すべての年収900万円世帯が守るべき「5つの鉄則」を解説します。
【鉄則1】月々返済額は「手取りの25%以内」
住宅ローン計画で最も重要な原則です。
計算の基準は、税金や社会保険料が引かれる前の「額面年収」ではなく、実際に自由に使える「手取り月収」である点を忘れないでください。
年収900万円世帯の手取り月収が約54万円〜56万円の場合、その25%は月々13万5,000円〜14万円となります。
この「25%」という数字には明確な根拠があります。
この範囲内に返済額を収めることで、日々の生活費はもちろん、将来のための貯蓄(教育費・老後資金)、不測の事態に備える予備費、そして人生を豊かにする趣味や旅行といった娯楽費まで、バランス良く支出を配分することが可能になります。
このラインを超えると、家計に余裕がなくなり、何かを我慢する生活を強いられる可能性が高まります。
【鉄則2】ゴールは「定年完済」
住宅ローンの返済期間は、主たる働き手の「定年退職年齢」から逆算して設定するのが鉄則です。
定年後は、収入の柱が公的年金となり、現役時代の3割〜5割程度まで減少するのが一般的です。
その状況で、現役時代と同じ水準のローン返済を続けるのは極めて困難であり、「老後破綻」の引き金になりかねません。
安易に退職金での一括返済をあてにするのも危険な考え方です。
退職金は、本来ゆとりある老後生活を送るための貴重な原資です。
それをローン返済に充ててしまうと、その後の生活資金が枯渇してしまう恐れがあります。
例えば40歳で住宅を購入する場合、定年を65歳と見据え、返済期間は25年以内に設定するのが理想的な計画と言えるでしょう。
【鉄則3】頭金は最低2割
頭金を準備することには、計り知れないメリットがあります。
まず、借入元金が減るため、支払う利息の総額を大幅に圧縮できます。
月々の返済額も軽くなり、日々の家計に余裕が生まれます。
また、金融機関によっては頭金の割合に応じて金利を優遇してくれるケースもあり、さらにお得になります。
理想的な頭金の額は、物件価格の20%以上です。
5,000万円の物件なら1,000万円が目安となります。
これにより、将来の金利上昇や不動産価格の下落といったリスクに対する耐性も高まります。
ただし、貯蓄のすべてを頭金に投入するのは避けるべきです。
購入時にかかる諸費用(物件価格の7%〜10%)と、万が一に備える生活防衛資金(生活費の最低6ヶ月分)は、必ず現金で手元に残しておきましょう。
【鉄則4】住宅ローンと将来資金は並行して準備
住宅ローン返済に追われ、人生の二大支出である「教育資金」と「老後資金」の準備がおろそかになるのは、最も避けたいシナリオです。
子ども一人あたりの教育費は、進路によっては1,000万円以上かかると言われ、夫婦二人の老後には2,000万円以上の資金が必要とされています。
これらの将来必ず必要になる資金を考慮せずに住宅ローンの返済額を決めてしまうと、数年後、数十年後に必ず無理が生じます。
子どもの進学時に教育ローンに頼らざるを得なくなったり、老後の生活が困窮したりする事態を招きかねません。
住宅ローンの返済計画は、必ずこれらの将来の積立額を確保した上で、余裕をもって支払える金額に設定することが不可欠です。
【鉄則5】金利上昇シナリオを想定
特に変動金利を選択する場合は、将来の金利上昇リスクへの備えが絶対条件です。
現在の低金利が永遠に続く保証はどこにもありません。
金利がわずか1%上昇しただけでも、総返済額は数百万円単位で増加し、家計を圧迫します。
対策として、金利が上昇した際の返済額増加分を吸収できるだけの余裕資金を常に確保しておくこと、あるいは、その資金を繰り上げ返済に充てる計画を立てておくことが重要です。
住宅ローンを組む前に、「もし金利が2%上昇したら、我が家の家計は耐えられるか?」というストレステスト(耐久テスト)を必ず行いましょう。
もし耐えられないのであれば、その借入額はあなたの家庭にとって過大である証拠です。
借入額を見直すか、返済額が変わらない固定金利を検討する必要があります。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
住宅ローン金利の選び方|変動金利vs固定金利

住宅ローンの金利タイプ選びは、数十年間の総返済額に数百万円単位の差を生むこともある、非常に重要な決断です。
金利の低さを取るか、返済額の安定を取るか。
年収900万円という比較的体力のある世帯だからこそ、それぞれのメリット・デメリットを深く理解し、自身のライフプランやリスク許容度に合った選択をする必要があります。
変動金利のメリット・デメリットと金利上昇リスク
変動金利型は、その名の通り、市場金利の動きに連動して半年ごとに適用金利が見直されるタイプです。
現在、歴史的な低金利を背景に、多くの金融機関が非常に魅力的な金利を提供しており、多くの利用者に選ばれています。
- メリット:最大の魅力は、固定金利に比べて金利が圧倒的に低いことです。当初の月々の返済額を大きく抑えることができ、家計にゆとりをもたらします。
- デメリット:最大の懸念点は、将来の金利上昇リスクを常に抱えることです。金利が上昇すれば、当然ながら月々の返済額も増加し、家計を圧迫する可能性があります。
「5年ルール」と「125%ルール」とは
多くの変動金利ローンには、金利が急上昇した際の負担を和らげるための仕組みが備わっています。
- 5年ルール:適用金利が半年ごとに見直されても、月々の返済額は5年間据え置かれるというルールです。
- 125%ルール:5年後の返済額見直しの際、新しい返済額はそれまでの返済額の1.25倍(125%)を上限とするルールです。
これらは一見、借り手を守る安全装置のように見えます。
しかし、注意すべき「落とし穴」も存在します。
返済額が据え置かれている間に金利が大幅に上昇した場合、返済額に占める利息の割合が増え、元金の減りが遅くなります。
最悪の場合、月々の返済額が利息分にすら満たず、返済しているにもかかわらず元金が増えてしまう「未払利息」が発生するリスクもゼロではありません。
これらのルールがない金融機関も存在するため、契約前の確認は必須です。
固定金利のメリット・デメリット
固定金利型は、借入期間中ずっと金利が変わらない「全期間固定金利」と、当初の3年、5年、10年といった一定期間の金利が変わらない「固定金利期間選択型」があります。
- メリット:最大の魅力は、返済額が借入時に確定することによる「安心感」と「計画の立てやすさ」です。将来、市場金利がどれだけ上昇しても、あなたの返済額は一切変わりません。子どもの教育費のピークや老後資金の準備など、長期的なライフプランを正確に描くことができます。
- デメリット:一般的に変動金利よりも金利が高めに設定されています。そのため、金利が低いまま推移した場合は、変動金利を選んだ場合よりも総返済額が多くなる「機会損失」が生じる可能性があります。
年収900万円世帯におすすめの金利選択とミックスローン
では、年収900万円世帯はどちらを選ぶべきでしょうか。
それは「借入額」と「リスクに対する考え方」によって決まります。
- 借入額が比較的少ない場合(例:4,000万円以下):家計に余裕があるため、金利上昇時の返済額増加にも対応しやすいと考えられます。低金利の恩恵を最大限に受けるため「変動金利」を選択するのが合理的かもしれません。ただし、金利上昇に備えて繰り上げ返済用の資金を計画的に貯めるなどの対策は必須です。
- 借入額が適正上限に近い場合(例:5,000万円前後):金利上昇の影響が家計に与えるインパクトが大きくなるため、慎重な判断が必要です。「変動金利」でリスクを取りつつ低金利のメリットを狙うか、「固定金利」で安心を買うか、まさに個人の価値観が問われます。当初10年間だけ金利を固定する「10年固定」なども有力な選択肢です。
- 借入額が高額な場合(例:6,000万円以上):金利上昇が即座に家計の危機に直結するレベルです。リスクを回避し、返済計画の安定性を最優先すべきであり、「全期間固定金利」を強く推奨します。
また、「ミックスローン」という選択肢も有効です。
これは、例えば借入額5,000万円のうち、3,000万円を変動金利、2,000万円を固定金利といったように、一つのローンを二つの金利タイプに分けて契約する方法です。
変動金利のメリットを享受しつつ、固定金利でリスクをヘッジできるため、リスクとリターンのバランスを取りたい世帯には最適な選択肢の一つと言えるでしょう。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
住宅ローン審査を通過するコツと金融機関選び

年収900万円という高い属性は、住宅ローン審査において非常に有利に働きます。
しかし、「高年収=審査は安泰」と考えるのは早計です。
思わぬ理由で審査に落ちてしまったり、期待したほどの好条件で借りられなかったりするケースも存在します。
ここでは、審査を確実に通過し、最適な金融機関と出会うための具体的なポイントを解説します。
年収900万円でも審査に落ちるケースとその理由
高年収であっても、金融機関が「この人にお金を貸すのはリスクがある」と判断すれば、審査は通りません。
特に注意すべきは以下の3点です。
- 他の借入・クレジット履歴の影響:住宅ローン以外の借入状況は厳しくチェックされます。自動車ローンや教育ローンはもちろん、特に注意が必要なのがカードローンやクレジットカードのリボ払いです。これらは金利が高く、日常的な資金繰りに困っている印象を与えかねません。他の借入の年間返済額と住宅ローンの年間返済額を合算した金額が、返済負担率の上限を超えていないかどうかが一つの基準となります。
- 「ブラックリスト」の存在:過去にクレジットカードの支払いや携帯電話の分割代金、奨学金の返済などで延滞した記録はありませんか。金額の大小にかかわらず、これらの情報は「信用情報機関」に記録されており、審査の際に金融機関は必ず照会します。ここに傷(いわゆるブラックリスト状態)があると、審査通過は極めて困難になります。
- 勤続年数・雇用形態の重要性:年収の「高さ」だけでなく「安定性」も重要な審査項目です。転職して間もない(勤- 続1年未満など)場合、いくら年収が高くても「この収入が今後も続くか不透明」と見なされ、審査が厳しくなる傾向があります。一般的に勤続3年以上が有利とされます。また、個人事業主や自営業の場合、会社員に比べて収入の波が大きいと判断され、直近数年間の安定した所得証明が求められます。
複数銀行での事前審査の重要性
住宅ローンを申し込む際は、必ず複数の金融機関に「事前審査(仮審査)」を申し込みましょう。
これは、本審査の前に、借入希望額や個人の属性から大まかな融資の可否を判断してもらう手続きです。
事前審査を複数受けることには、以下のような大きなメリットがあります。
- 自分の借入可能額や適用金利の相場観がわかる。
- 金融機関によって審査基準が異なるため、A銀行ではダメでもB銀行なら通る、といったケースがある。
- 複数の承認を得ることで、より金利が低い、団信の保障が手厚いなど、最も条件の良い金融機関を選ぶ「交渉材料」にできる。
最適な金融機関選び
金融機関にはそれぞれ特徴があります。
ネット銀行
- メリット:店舗を持たない分、人件費や運営コストを抑えられるため、金利が低い傾向にあります。手続きもオンラインで完結することが多く、手軽です。
- デメリット:対面での相談ができないため、複雑な事情がある場合や手厚いサポートを求める人には不向きなことがあります。
都市銀行・地方銀行
- メリット:窓口で担当者と直接相談しながら手続きを進められる安心感があります。給与振込などで既に取引がある場合、金利優遇を受けられることもあります。
- デメリット:一般的にネット銀行よりは金利がやや高めに設定されていることが多いです。
フラット35
- メリット:最長35年の全期間固定金利が特徴です。国の機関が関わっているため審査基準が比較的明確で、個人事業主や勤続年数が短い人でも借りやすい傾向があります。
年収900万円世帯の場合、わずかな金利差でも総返済額への影響は大きくなります。
まずは金利の低いネット銀行を中心に複数比較し、もし不安な点があれば対面相談ができる都市銀行や地方銀行も検討するという流れが効率的です。
審査を有利にするための事前準備
審査をスムーズに進め、より良い条件を引き出すためには、申込前の準備が重要です。
- 必要書類の準備:源泉徴収票(できれば直近2〜3年分)、課税証明書、本人確認書類、物件資料などをあらかじめ揃えておきましょう。
- 信用情報の事前確認:CICやJICCといった信用情報機関に情報開示請求(有料)をすれば、自分の信用情報を確認できます。もし身に覚えのない延滞記録などがあれば、すぐに対応しましょう。
- 既存借入の整理:可能であれば、カードローンや残債の少ないローンは住宅ローン申込前に完済しておくのがベストです。使っていないクレジットカードを解約するだけでも、与信枠が整理され、心証が良くなることがあります。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
まとめ
今回は、世帯年収900万円の住宅ローンについて、適正な借入額から具体的な返済計画、後悔しないための鉄則までを解説しました。
この記事で紹介した事例や平均データはあくまで参考です。
大切なのは、他人と比較することなく、ご自身の家庭の価値観とライフプランに真摯に向き合い、「我が家だけの最適解」を見つけ出すことです。
ぜひこの記事も参考に、理想の資金計画を立ててくださいね。



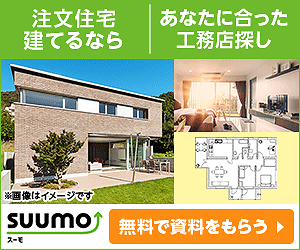




コメント