年収700万円は多くの人が憧れる収入ラインであり、理想のマイホーム購入が現実味を帯びてくるステージです。
金融機関からは「最大5,000万円超の融資も可能です」といった魅力的な提案を受け、夢の注文住宅や都心のタワーマンションにも手が届くかもしれないと、胸が高鳴る方も多いのではないでしょうか。
しかし、その一方で、「本当にこの金額を借りて大丈夫だろうか?」「将来、子どもの教育費や老後資金は確保できるのか?」という漠然とした不安がよぎるのも事実です。
そこでこの記事は、「戦略的な住宅ローン計画」を網羅しながら解説します。
ぜひ最後まで参考にしてみてくださいね。
本文に入る前に、これから家づくりを考えている人や、現在進行形でハウスメーカー選びを進めている人に、後悔しない家づくりのための最も重要な情報をお伝えします。
早速ですが、質問です。
家づくりで一番大切なこと、それはなんだと思いますか?
おそらく間取りや予算、建てる場所などと考える人も多いかもしれませんね。
ですが実は、家づくりで最も大切なことは「気になっているハウスメーカーのカタログを、とりあえず全て取り寄せてしまうこと」なんです。
カタログを取り寄せずに住宅展示場に行き、営業マンの言葉巧みな営業トークに押されて契約を結んでしまうのは最悪なケース。
住宅展示場に行ってその場で契約をしてしまった人の中には、「もしもカタログを取り寄せて比較検討していたら、同じ間取りの家でも300万円安かったのに・・・」と後悔する人が本当に多いんです。
このように、もう少し情報収集をしていれば理想の家をもっと安く建てられていたのに、場合によっては何百万単位の損をして後悔してしまうこともあります。
だからこそ、きちんとした情報収集をせずにハウスメーカーを選ぶのは絶対にやめてください。
そんなことにならないようにハウスメーカーのカタログを取り寄せて比較検討することが最も重要なんです。

そうは言っても、気になるハウスメーカーはたくさんあるし、気になるハウスメーカー全てに連絡してカタログを取り寄せるなんて、時間と労力がかかりすぎるよ・・・
そう思う人も少なくありません。
そもそもどのように情報収集をしたら良いのかわからないという人もいるでしょう。
そんなあなたにぜひ活用してほしいサービスが、「ハウスメーカーのカタログ一括請求サービス」や「専門家に実際に相談してみること」です!
これらのサービスを活用することで、何十倍もの手間を省くことができ、損をするリスクも最大限に減らすことができます。
中でも、不動産業界大手が運営をしている下記の3つのサービスが特におすすめです。
|
東証プライム上場企業「LIFULL」が運営をしているカタログ一括請求サービスです。厳しい審査を通過した全国の優良住宅メーカーからカタログを取り寄せることが可能です。特にローコスト住宅に強いため、ローコスト住宅でマイホームを検討している人に非常におすすめです。 不動産のポータルサイトとしておそらく全国で最も知名度のあるSUUMOが運営しています。全国各地の工務店とのネットワークも豊富。住宅の専門家との相談をすることが可能で、住宅メーカー選びのみならず、家づくりの初歩的な質問から始めることが可能です。「何から始めたら良いのかわからない」と言う人はSUUMOに相談することがおすすめです。 上場企業でもあるNTTデータが運営しているサービスです。大手ということもあり、信頼も厚いのが特徴です。全国各地の大手ハウスメーカーを中心にカタログを取り寄せることができます。また、理想の家づくりプランを作ってもらえるのも嬉しいポイントです。 |
上記の3サイトはどれも完全無料で利用できる上、日本を代表する大手企業が運営しているため、安心して利用することができます。
また、厳しい審査基準で問題のある企業を事前に弾いているため、悪質な住宅メーカーに依頼してしまうというリスクを避けることも可能です。
正直言って、こちらの3サイトならどれを利用しても間違いはないでしょう。
また、どれを利用するか迷ったら、
- ローコスト住宅メーカーや大手ハウスメーカーを検討中:LIFULL HOME'Sでカタログ請求
- 工務店をメインで検討中:SUUMOカウンターで相談
- 資金計画や土地探しも相談したい:家づくりのとびら
というふうに使い分けてみるのもおすすめです。
そのほかに、SUUMOも無料カタログの一括請求サービスを提供しています。
こちらも無料なので、ぜひ利用してみることをおすすめします。
もちろんどのサービスも無料なため、全て活用してみるのもおすすめです。
後悔のない家づくりのため、1社でも多くの会社からカタログを取り寄せてみてくださいね!
\メーカー比較で数百万円得することも!/

【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる≫

【プロと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
家づくりで後悔しないために、これらのサービスをうまく活用しながら、ぜひあなたの理想を叶えてくれる住宅メーカーを見つけてみてください!
それでは本文に入っていきましょう!
借入可能額と適正な借入額の目安

年収700万円の方が住宅ローンを組む際、最初の関門となるのが「いくら借りられるのか」という疑問です。
しかし、ここで最も重要なのは、金融機関が提示する「借入可能額」と、ご自身のライフプランに沿った「無理なく返せる適正額」は全くの別物であるという事実を深く理解することです。
年収700万円は高収入層にあたるため、金融機関からは高額な融資提案を受ける可能性があります。
その数字に安堵し、上限額に近いローンを組んでしまうと、後々の家計を圧迫し、「住宅ローンのために働く」という本末転倒な事態に陥りかねません。
ここでは、その二つの指標の違いを明確にし、真にあなたにとって最適な借入額を見極めるための具体的な考え方を深掘りしていきます。
「借入可能額」とその上限のカラクリ
まず、金融機関が審査で用いる「借入可能額」の目安について見ていきましょう。
一般的に、住宅ローンの借入可能額は年収の5〜7倍が目安とされており、年収700万円の場合、3,500万円〜4,900万円が一つの基準となります。
さらに、金融機関によっては審査基準を緩和し、年収の8倍、つまり最大で5,600万円まで融資を行うケースも存在します。
なぜこれほど高額な融資が可能なのでしょうか。
その理由は、金融機関が審査で用いる「返済負担率(返済比率)」の上限設定にあります。
多くの金融機関は、この返済負担率の上限を30%〜35%に設定しています。
年収700万円で返済負担率35%を適用すると、年間の返済額は245万円(月々約20.4万円)となり、これを基に逆算すると非常に大きな金額を貸し出せる計算になるのです。
しかし、この「借入可能額」は、あくまで「あなたの将来のライフイベントや個別の支出状況を一切考慮しない、機械的な審査上の上限値」に過ぎません。
金融機関はあなたの子供の教育費、親の介護費用、車の買い替え、自己投資といった未来の支出までは審査に含めません。
あくまで「現在の年収と信用情報から、滞りなく返済できるか」という一点で判断していることを忘れてはいけません。
「無理なく返せる適正額」の考え方
住宅購入後の生活にゆとりを持ち、豊かな暮らしを実現するためには、前述の「借入可能額」ではなく、ご自身の家計に基づいた「適正額」でローンを組む必要があります。
その際に理想とされる返済負担率は20%〜25%です。
年収700万円であれば、年間返済額140万円〜175万円、月々約11.7万円〜14.6万円が、生活に余裕を持たせる一つの目安となります。
なぜ上限の35%ではなく、25%以下に抑えるべきなのでしょうか。
その理由は、住宅購入後に発生する「新たな支出」と「将来のリスク」に備えるためです。
- 住宅購入後のランニングコスト:マイホームを持つと、固定資産税・都市計画税(年間十数万円〜)、火災保険・地震保険料、マンションの場合は管理費・修繕積立金(月々数万円)といった、賃貸時代にはなかった費用が継続的に発生します。これらの費用を考慮せずにローン返済額を設定すると、想定以上に家計が圧迫されます。
- 将来のライフイベント費用:お子様がいれば教育費(大学進学までに1人1,000万円以上とも言われます)、親の介護、自身のセカンドライフへの備えなど、将来にわたって大きな支出が見込まれます。
- 不測の事態への備え:病気やケガによる休職、会社の業績悪化によるボーナスカットや減給、転職など、収入が不安定になるリスクは誰にでもあります。返済額に余裕がなければ、このような事態に全く対応できなくなってしまいます。
これらの要素を考慮すると、返済負担率25%という数字は、決して低すぎる目標ではないことがお分かりいただけるでしょう。
「額面年収」と「手取り年収」で見る返済負担率の違い
さらに重要なのが、「額面年収」ではなく「手取り年収」で返済計画を立てることです。
年収700万円(額面)の場合、所得税や住民税、社会保険料が差し引かれた後の手取り額は、扶養家族の有無などにもよりますが、およそ525万円〜595万円になります。
仮に、返済負担率25%(年間返済額175万円)でローンを組んだとしましょう。
- 額面年収ベースの計算: 175万円 ÷ 700万円 = 25%
- 手取り年収ベースの計算: 175万円 ÷ 525万円 = 約33.3%
このように、額面では「理想的な25%」に見えても、実際に家計をやりくりする手取り収入から見ると、負担率は33%を超え、かなり余裕のない状態であることがわかります。
より安全な資金計画を立てるためには、「手取り年収の20%〜25%」を年間返済額の上限として考えることを強く推奨します。
他の人はいくら借りてる?物件種別ごとの平均借入額
自分以外の人がどの程度借り入れをしているのか、客観的なデータを見てみましょう。
住宅金融支援機構の「2022年度 フラット35利用者調査」によると、年収700万円台の人が実際に借り入れた額の平均は以下のようになっています。
- 土地付き注文住宅: 5,180万円(年収倍率7.4倍)
- 注文住宅: 4,690万円(年収倍率6.7倍)
- マンション(新築): 4,900万円(年収倍率7.0倍)
- 建売住宅: 4,760万円(年収倍率6.8倍)
- 中古マンション: 4,060万円(年収倍率5.8倍)
- 中古戸建: 3,850万円(年収倍率5.5倍)
このデータから、新築物件では年収の7倍前後、中古物件では6倍弱と、物件種別によって借入額に差が出る傾向が見て取れます。
ただし、これはあくまで全国の平均値です。頭金の額や世帯構成、ライフプランは人それぞれ異なります。
これらのデータは一つの参考とし、最終的にはご自身の家計と将来設計に責任を持てる範囲で、最適な借入額を決定することが何よりも重要です。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
無理のない返済計画を立てるポイント

住宅ローンは「借りて終わり」ではなく、「数十年にわたって健全に返し続ける」ことが本質です。
年収700万円という安定した収入基盤があっても、計画の精度が低ければ、理想のマイホームが将来の重荷に変わりかねません。
ここでは、単なる節約術ではなく、将来のあらゆる変化に耐えうる強固な返済計画を構築するための、具体的かつ戦略的な9つのポイントを徹底的に深掘りします。
現実的な返済可能額の算出
返済計画の第一歩は、年収という「入口」からではなく、支出という「出口」から逆算することです。
そのためには、まずご自身の家計を徹底的に「見える化」する必要があります。
- 最低3ヶ月間の家計簿で現状を把握する: 感覚で「毎月これくらい」と考えるのは危険です。家計簿アプリなどを活用し、最低でも3ヶ月間、できれば半年間の支出を記録しましょう。これにより、月々の平均的な支出額だけでなく、季節ごとの変動(夏の光熱費、年末年始の交際費など)も把握できます。
- 「見えないコスト」を具体的に織り込む: 住宅購入後に新たに発生するコストを、甘く見積もってはいけません。これらを月々の支出としてあらかじめ計上しておくことが重要です。見えないコストには、固定資産税や修繕費などがあります。
将来の選択肢を広げる頭金戦略
年収700万円という収入があると、「フルローンでも問題ないだろう」と考えがちですが、頭金の有無は将来の選択肢を大きく左右します。
- 頭金のメリット: 頭金の最大のメリットは、支払うべき利息総額を劇的に圧縮できることです。例えば、金利1.5%、35年返済で5,000万円を借りる場合と、頭金1,000万円を入れて4,000万円を借りる場合では、総利息額に約280万円もの差が生まれます。また、物件価格に対する借入金の割合(LTV)が下がることで、金融機関からの信用度が上がり、より良い金利条件を引き出せる可能性もあります。
- 資金確保の重要性: しかし、貯蓄のすべてを頭金に投入するのは絶対に避けるべきです。手元には必ず「生活防衛資金」と「ライフイベント資金」を確保しておく必要があります。
頭金ゼロ(フルローン)は、購入時期を早められるメリットはありますが、金利が割高になったり、将来物件を売却する際にローン残高が売却価格を上回る「残債割れ」のリスクが高まったりするデメリットも理解しておく必要があります。
「金利タイプ」の賢い選び方
金利タイプの選択は、あなたの将来に対する考え方やリスク許容度そのものを反映します。
それぞれの特性と、それに伴うリスクを深く理解しましょう。
- 変動金利: 現在の低金利の恩恵を最大限に受けられるタイプです。しかし、将来の金利上昇リスクを自身で負うことになります。金利が上昇しても5年間は返済額が変わらない「5年ルール」や、返済額の上昇幅が直前の1.25倍までに制限される「125%ルール」がありますが、これは痛みを先送りしているに過ぎません。返済額に占める利息の割合が増え、元金が想定通りに減らない「未払利息」が発生するリスクを内包しています。金利の動向を常にチェックし、上昇局面でも対応できる貯蓄力がある、または繰り上げ返済で柔軟に対応できる方に向いています。
- 全期間固定金利(フラット35など): 返済開始から完済まで金利が変わらないため、返済計画が非常に立てやすいのが最大のメリットです。子どもの教育費がピークを迎える時期など、将来の家計が見通しにくい時期でも、返済額が一定という安心感は絶大です。金利は変動型より高めですが、それは「金利が変わらない安心」という保険料を払っていると考えることができます。将来の金利変動に一喜一憂したくない、安定志向の方に最適な選択です。
- 固定金利期間選択型: 当初3年、5年、10年といった期間は低めの固定金利が適用され、魅力的に見えます。しかし、最も注意すべきは固定期間終了後です。金利の優遇幅が縮小し、適用金利が大幅に跳ね上がる「金利の崖」に直面する可能性があります。固定期間中にしっかりと貯蓄し、繰り上げ返済や有利なローンへの借り換えができる明確な計画がある方向けの、やや上級者向けの選択肢と言えるでしょう。
バランスを取る返済期間の設定
返済期間の設定は、月々の返済額と総支払額のトレードオフの関係にあります。
年収700万円の方の平均返済年数が34.79年と長期化している背景には、月々のキャッシュフローを楽にしたいというニーズがあります。
しかし、その選択が将来にどのような影響を与えるのか、両側面から深く理解する必要があります。
長期返済(35年ローン)のメリットとデメリット
- メリット: 最大のメリットは、月々の返済額を抑えられることです。これにより、日々の生活にゆとりが生まれ、教育費や自己投資など、住宅以外の事柄にも資金を振り分けやすくなります。特に子育て期など、支出が多い時期の家計管理には有効な手段です。
- デメリット: 最大のデメリットは、総支払利息額が大幅に増加することです。例えば、4,000万円を金利1.5%で借りた場合、返済期間25年と35年では、月々の返済額は約3.2万円の差ですが、総支払額では約250万円もの差が生まれます。また、完済時の年齢が高くなるため、定年後もローン返済が続くリスクがあります。退職金で一括返済を考えている場合も、その退職金が目減りし、老後資金を圧迫する可能性を考慮しなければなりません。
短期返済(25年ローンなど)のメリットとデメリット
- メリット: 総支払額を大幅に圧縮でき、早くローンから解放される精神的なメリットは非常に大きいです。定年前に完済できれば、退職金をまるごと老後資金に充てることができ、安心してセカンドライフを迎えられます。
- デメリット: 月々の返済額が高額になるため、家計に余裕がなくなります。特に、収入が不安定になったり、予期せぬ大きな支出が発生したりした際には、返済が困難になるリスクが高まります。
「住宅ローン控除」を最大限に活用する戦略
住宅ローン控除(住宅ローン減税)は、国が提供する極めて強力な家計支援策です。
この制度を正しく理解し、最大限に活用することで、実質的な金利負担を劇的に軽減できます。
- 制度の基本: 年末時点の住宅ローン残高の0.7%が、所得税(控除しきれない場合は一部住民税)から最長13年間にわたって控除される制度です。例えば、年末のローン残高が4,000万円であれば、その年の所得税から28万円が還付されます。仮にあなたの住宅ローン金利が0.5%であれば、控除率(0.7%)が金利を上回るため、最初の数年間は「実質マイナス金利」の状態になるのです。
- 【重要】2024年改正のポイントと子育て世帯への優遇: 2024年の税制改正で、特に子育て世帯(19歳未満の子どもがいる世帯)や若者夫婦世帯(夫婦のどちらかが40歳未満の世帯)に対する優遇措置が拡充されました。
「期間短縮型」と「返済額軽減型」を使い分ける
繰り上げ返済は、総支払額を減らすための最も効果的な手段の一つですが、その方法には2種類あり、目的によって使い分けることが重要です。
- 期間短縮型: 毎月の返済額は変えずに、返済期間を短くする方法です。元金が早く減るため、利息の軽減効果が非常に大きいのが特徴です。総支払額を1円でも多く減らしたい、早く完済して精神的に楽になりたいという場合に最適な方法です。
- 返済額軽減型: 返済期間は変えずに、毎月の返済額を減らす方法です。利息の軽減効果は期間短縮型より小さいですが、即座に月々のキャッシュフローが改善するのがメリットです。子どもの教育費がかさむ時期や、収入が減少した際に、家計の負担を直接的に軽くしたい場合に有効です。
繰り上げ返済を行うタイミングは、一般的にローン実行後の早い段階であるほど利息軽減効果は高まります。
しかし、前述の住宅ローン控除との兼ね合いや、手元の資金が減りすぎないよう、ライフプランと照らし合わせながら計画的に実行することが肝心です。
手数料の有無も金融機関によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
「ライフプランニング」の重要性
目の前の返済額だけにとらわれず、家計の変化を具体的にシミュレーションし、計画に織り込む「ライフプランニング」こそが、長期的な返済を成功させるための鍵となります。
ライフイベントと必要資金のシミュレーション
- 子どもの教育費という最大の支出: 子どもの教育費は、住宅費、老後資金と並ぶ「人生の三大支出」です。文部科学省の調査などによると、幼稚園から大学卒業までにかかる費用は、すべて国公立でも約1,000万円、すべて私立(大学は理系)となると2,500万円を超えることも珍しくありません。お子様の進学プランを想定し、教育費のピークとなる大学在学中の4年間(一般的に18歳〜22歳)が、住宅ローン返済の何年目にあたるのかを把握することが極めて重要です。この時期に家計が赤字にならないよう、計画的な貯蓄や、ピーク前に繰り上げ返済でローン残高を減らしておくなどの対策が不可欠です。
- 親の介護という突然の出費: 自分たちの生活だけでなく、両親の老後も考慮に入れる必要があります。生命保険文化センターの調査では、介護にかかる費用は一時的な費用(住宅改修や介護用品購入など)の平均が74万円、月々の費用が平均8.3万円とされています。これが数年にわたって続けば、家計への影響は甚大です。また、介護離職による収入減のリスクもゼロではありません。
- 自身の老後資金の確保: 年収700万円であっても、公的年金だけでゆとりある老後を送るのは難しい時代です。「老後2000万円問題」が示すように、自助努力による資産形成が求められます。住宅ローンの返済に追われ、iDeCo(個人型確定拠出年金)やNISA(少額投資非課税制度)といった有効な資産形成手段を活用できなければ、ローン完済後に資金不足に陥る可能性があります。ローン返済と資産形成は、車の両輪として並行して進めるべきものです。
- キャリアプランと収入変動リスク: 50代以降、役職定年や早期退職などで収入が減少する可能性も考慮しておくべきです。順調な昇給を前提とした返済計画は非常に危険です。最悪のケースとして、収入が2割〜3割減少しても耐えられる程度の返済額に設定しておくことが、精神的な安定につながります。
共働き世帯の「強み」と「落とし穴」
夫婦共働きの場合、世帯年収で審査を受けることで借入可能額を大きく増やすことができ、これは大きな「強み」です。
しかし、その裏には見過ごされがちな「落とし穴」も存在します。
収入合算やペアローンといった選択肢のメリットとデメリットを正確に理解し、夫婦で将来のリスクを共有することが不可欠です。
借入方法の選択肢と特徴
- 収入合算: 夫婦の収入を合算して1本のローンを組む方法。「連帯債務」と「連帯保証」の2種類があります。「連帯債務」は夫婦ともに債務者となり、それぞれが住宅ローン控除を受けられますが、「連帯保証」は主債務者1人だけが控除対象です。
- ペアローン: 夫婦それぞれが個別にローン契約を結び、お互いが連帯保証人になる方法。夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられ、それぞれが団信に加入できるのが最大のメリットです。
潜む重大なリスクと対策
- 産休・育休・時短勤務による収入減: 審査時の世帯年収を前提に上限額まで借りてしまうと、出産後の収入減少期に返済が苦しくなるリスクがあります。計画段階で、妻の収入が一時的にゼロになる期間や、復職後の時短勤務による収入減をあらかじめ計算に入れ、「夫の収入だけでも無理なく返済できる範囲」を一つの安全ラインとして検討することが賢明です。
- 団信の「落とし穴」: ペアローンは夫婦それぞれが団信に加入しますが、これは「片方に万一のことがあっても、完済されるのはその人の分のローンだけ」ということを意味します。残された配偶者は、自身のローン返済を続けなければなりません。このリスクに備えるには、別途生命保険で保障を手厚くするか、金融機関が提供する「連生団信(クロスサポートなど)」を検討する価値があります。これは、夫婦のどちらか一方に万一のことがあった場合に、住宅ローン残高の全額が弁済される団信です。
- 離婚のリスク: 万が一離婚に至った場合、ペアローンや連帯債務の解消は非常に複雑です。財産分与で家の所有権をどうするか、残ったローンを誰がどう返済していくのか、売却するにしても残債割れのリスクはないかなど、深刻な問題に発展する可能性があります。
金融機関は「金利」だけで選ばない
住宅ローン選びにおいて、金利の低さはもちろん重要ですが、それだけで金融機関を決めてしまうのは早計です。
特に年収700万円という世帯の主たる稼ぎ手にとっては、金利以外の「保障」や「サービス」の価値が、0.1%の金利差以上に大きな意味を持つことがあります。
表面的な数字だけでなく、総合力で比較検討する視点を持ちましょう。
比較すべき3つの重要ポイント
- 団体信用生命保険(団信)の保障内容: 団信は、単なる死亡保障ではありません。現代の団信は、生命保険としての機能が非常に充実しています。
- 各種手数料のトータルコスト: ローン契約時には、利息以外にも様々な手数料が発生します。これらを合算した「実質金利」や「総支払コスト」で比較することが重要です。
- サービスの柔軟性と利便性: 長期にわたる返済期間中には、何が起こるかわかりません。万一の際のサポート体制も比較検討しましょう。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
住宅ローン審査に落ちる可能性のある要因

年収700万円という収入は、一般的に住宅ローン審査において非常に有利です。
しかし、「年収さえ高ければ審査は必ず通る」と考えるのは大きな誤解です。
金融機関の審査は、収入額という一点だけでなく、「長期間にわたり安定して返済を続けられるか」という個人の総合的な信用力を多角的に評価するプロセスとなっています。
収入の安定性
金融機関が最も重視する項目の一つが「収入の安定性」です。
現在の年収額だけでなく、その収入が将来にわたって継続する見込みがあるかが厳しくチェックされます。
- 勤続年数の壁: なぜ勤続年数が重要視されるのでしょうか。それは、収入の「継続性」と「再現性」を測る最も分かりやすい指標だからです。一般的に勤続1年未満では、多くの金融機関で審査の土俵に上がることさえ難しいのが現実です。勤続3年以上でようやく「安定している」と評価され、審査が有利に進む傾向にあります。
- 「転職」が与える影響: 転職直後は特に注意が必要です。キャリアダウンや全くの異業種への転職は、収入の不安定化を懸念され、マイナス評価につながることがあります。一方で、同業種へのキャリアアップ転職で年収が大幅に増加した場合は、その将来性を評価され、プラスに働くこともあります。転職直後に審査を受ける場合は、給与明細だけでなく、職務経歴書や採用条件通知書などを提出し、今後の収入の安定性を積極的にアピールする必要があります。
- 雇用形態の評価: 正社員が最も有利なのは言うまでもありませんが、契約社員や派遣社員、個人事業主(フリーランス)であってもローンを組むことは可能です。ただし、契約社員や派遣社員の場合は、契約更新の実績や今後の見込みが問われます。特に個人事業主は、収入の波が激しいと見なされがちで、直近3期分の確定申告書の提出を求められ、安定した所得を証明する必要があります。たとえ年収700万円を超えていても、特定の年に突出して高いだけで、他の年が低い場合は評価が下がるため注意が必要です。
個人の信用力
住宅ローン審査では、あなたの「お金に関する過去の行い」がすべて記録された「信用情報」が徹底的にチェックされます。
自分では些細なことだと思っていても、これが原因で審査に落ちるケースは少なくありません。
- 「総返済負担率」に含まれる全ての借入: 審査で用いられる返済負担率は、住宅ローンの返済額だけでなく、現在利用している全ての借入の年間返済額を合算して計算されます。これには、自動車ローンや教育ローンはもちろんのこと、クレジットカードのリボ払いや分割払い、カードローン、さらにはスマートフォンの本体代金の分割払いまで含まれます。借入額そのものが少なくても、複数の借入がある「借入件数の多さ」自体が、資金管理能力を疑われる要因となり得ます。審査前には、不要なカードローン契約を解約したり、リボ残高を完済したりするなど、借入状況をできる限りクリーンにしておくことが重要です。
- 信用情報の傷(異動情報): いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれる状態です。過去にクレジットカードやローンの支払いを61日以上または3ヶ月以上延滞したり、自己破産や債務整理などを行ったりした履歴があると、信用情報に「異動」という記録が残り、この記録がある間は審査通過が極めて困難になります。特に注意したいのが、携帯電話料金の延滞です。本体代金を分割払いにしている場合、その支払いが遅れるとローン延滞として信用情報に記録されてしまいます。「うっかり払い忘れた」が命取りになりかねません。不安な方は、CIC、JICC、KSCといった信用情報機関に情報開示請求を行い、自身の信用情報を事前に確認しておくことを強く推奨します。
健康状態
ほとんどの民間金融機関では、住宅ローンの契約時に団体信用生命保険(団信)への加入が必須条件とされています。
これは、契約者に万一のことがあった際にローン残高が保険金で完済される仕組みで、金融機関にとってのリスクヘッジです。
そのため、団信の審査に通らなければ、住宅ローンを組むことはできません。
- 告知義務の重要性: 団信の申込時には、過去の病歴や現在の健康状態について正直に告知する義務があります。もしここで虚偽の告知をしてしまうと「告知義務違反」となり、万が一の際に保険金が支払われないばかりか、ローン契約自体が解除されるという最悪の事態を招きます。
- 審査に影響しやすい病歴: 高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病や、うつ病・適応障害などの精神疾患、がん、心疾患、脳卒中の治療歴などは、審査が厳しくなる傾向にあります。しかし、病名だけで即座に否決されるわけではありません。重要なのは、治療を経て現在の健康状態が良好にコントロールされているかという点です。通院や服薬を続けていても、医師の診断書などを添えることで加入が認められるケースもあります。
- 団信に落ちた場合の代替案: もし通常の団信審査に落ちてしまった場合でも、道が完全に閉ざされるわけではありません。金利が0.2%〜0.3%程度上乗せされますが、引受基準が緩和された「ワイド団信」を取り扱う金融機関を検討しましょう。それでも加入が難しい場合は、団信への加入が任意である住宅金融支援機構の「フラット35」が有力な選択肢となります。その場合は、自身で別途生命保険に加入し、万一の際の返済資金を確保しておく必要があります。
物件の価値
住宅ローン審査は、人だけでなく「購入する物件」も審査の対象です。
金融機関は融資する物件を担保とするため、その物件に十分な担保価値があるかを評価します。
物件の評価額が借入希望額に対して著しく低い場合、融資額が減額されたり、融資自体が否決されたりすることがあります。
担保評価が低い物件の具体例
- 建築基準法違反の物件: 建ぺい率や容積率が基準を超えている、いわゆる「違法建築」の物件は、原則として融資の対象外です。
- 再建築不可物件: 建築基準法で定められた幅4m以上の道路に2m以上接していない土地(接道義務違反)など、現在の法律では同じ建物を建て替えられない物件は、担保価値がほぼないと見なされ、審査は非常に困難です。
- 旧耐震基準の物件: 1981年(昭和56年)5月31日以前の建築確認で建てられた物件は、現行の耐震基準を満たしていない可能性があり、金融機関によっては融資対象外としたり、耐震診断を求められたりします。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
まとめ
この記事を通じて、年収700万円の方が住宅ローンを組む際の様々な側面を掘り下げてきました。
年収700万円という収入は、日本国内において高収入層に位置し、理想のマイホームを手に入れるための大きなアドバンテージとなります。
金融機関からも魅力的な融資提案を受け、多くの選択肢の中から物件を選ぶことができるでしょう。
しかし、その「選択肢の多さ」と「借入可能額の大きさ」にこそ、最大の落とし穴が潜んでいるということを、最後に改めて強調したいと思います。
この記事が少しでもあなたの資金計画の参考になれば嬉しいです。



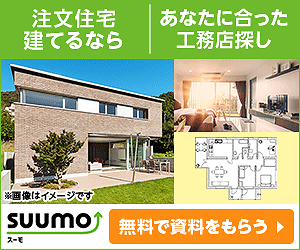




コメント