年収600万円でマイホームを検討している人は、「一体いくらまで借りられるんだろう?」「今の家賃と同じくらいの返済額なら大丈夫かな?」といった疑問や、将来の不安を抱えてはいないでしょうか。
もし金融機関の窓口へ行き、「あなたなら5,000万円まで借りられますよ」という言葉を鵜呑みにしてしまうと、それは将来の家計を圧迫する「後悔への第一歩」かもしれません。
住宅ローンで失敗する人の多くが陥る最大の過ちは、金融機関が提示する「借入可能額」を、自分たちが「借りていい額」だと勘違いしてしまうことです。
しかし、その数字は、あなたのリアルな生活費や子どもの教育費、不測の事態への備えを一切考慮しない、あくまで金融機関側のビジネス上の上限値に過ぎません。
そこでこの記事では、借入額のシミュレーションのみならず、年収600万円世帯の「手取り収入」を基点に、将来のライフイベントや見えない維持コストまでを解説していきます。
ぜひ最後まで読んで参考にしてみてくださいね。
本文に入る前に、これから家づくりを考えている人や、現在進行形でハウスメーカー選びを進めている人に、後悔しない家づくりのための最も重要な情報をお伝えします。
早速ですが、質問です。
家づくりで一番大切なこと、それはなんだと思いますか?
おそらく間取りや予算、建てる場所などと考える人も多いかもしれませんね。
ですが実は、家づくりで最も大切なことは「気になっているハウスメーカーのカタログを、とりあえず全て取り寄せてしまうこと」なんです。
カタログを取り寄せずに住宅展示場に行き、営業マンの言葉巧みな営業トークに押されて契約を結んでしまうのは最悪なケース。
住宅展示場に行ってその場で契約をしてしまった人の中には、「もしもカタログを取り寄せて比較検討していたら、同じ間取りの家でも300万円安かったのに・・・」と後悔する人が本当に多いんです。
このように、もう少し情報収集をしていれば理想の家をもっと安く建てられていたのに、場合によっては何百万単位の損をして後悔してしまうこともあります。
だからこそ、きちんとした情報収集をせずにハウスメーカーを選ぶのは絶対にやめてください。
そんなことにならないようにハウスメーカーのカタログを取り寄せて比較検討することが最も重要なんです。

そうは言っても、気になるハウスメーカーはたくさんあるし、気になるハウスメーカー全てに連絡してカタログを取り寄せるなんて、時間と労力がかかりすぎるよ・・・
そう思う人も少なくありません。
そもそもどのように情報収集をしたら良いのかわからないという人もいるでしょう。
そんなあなたにぜひ活用してほしいサービスが、「ハウスメーカーのカタログ一括請求サービス」や「専門家に実際に相談してみること」です!
これらのサービスを活用することで、何十倍もの手間を省くことができ、損をするリスクも最大限に減らすことができます。
中でも、不動産業界大手が運営をしている下記の3つのサービスが特におすすめです。
|
東証プライム上場企業「LIFULL」が運営をしているカタログ一括請求サービスです。厳しい審査を通過した全国の優良住宅メーカーからカタログを取り寄せることが可能です。特にローコスト住宅に強いため、ローコスト住宅でマイホームを検討している人に非常におすすめです。 不動産のポータルサイトとしておそらく全国で最も知名度のあるSUUMOが運営しています。全国各地の工務店とのネットワークも豊富。住宅の専門家との相談をすることが可能で、住宅メーカー選びのみならず、家づくりの初歩的な質問から始めることが可能です。「何から始めたら良いのかわからない」と言う人はSUUMOに相談することがおすすめです。 上場企業でもあるNTTデータが運営しているサービスです。大手ということもあり、信頼も厚いのが特徴です。全国各地の大手ハウスメーカーを中心にカタログを取り寄せることができます。また、理想の家づくりプランを作ってもらえるのも嬉しいポイントです。 |
上記の3サイトはどれも完全無料で利用できる上、日本を代表する大手企業が運営しているため、安心して利用することができます。
また、厳しい審査基準で問題のある企業を事前に弾いているため、悪質な住宅メーカーに依頼してしまうというリスクを避けることも可能です。
正直言って、こちらの3サイトならどれを利用しても間違いはないでしょう。
また、どれを利用するか迷ったら、
- ローコスト住宅メーカーや大手ハウスメーカーを検討中:LIFULL HOME'Sでカタログ請求
- 工務店をメインで検討中:SUUMOカウンターで相談
- 資金計画や土地探しも相談したい:家づくりのとびら
というふうに使い分けてみるのもおすすめです。
そのほかに、SUUMOも無料カタログの一括請求サービスを提供しています。
こちらも無料なので、ぜひ利用してみることをおすすめします。
もちろんどのサービスも無料なため、全て活用してみるのもおすすめです。
後悔のない家づくりのため、1社でも多くの会社からカタログを取り寄せてみてくださいね!
\メーカー比較で数百万円得することも!/

【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる≫

【プロと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
家づくりで後悔しないために、これらのサービスをうまく活用しながら、ぜひあなたの理想を叶えてくれる住宅メーカーを見つけてみてください!
それでは本文に入っていきましょう!
年収600万円で借りられる住宅ローンはいくら?

住宅ローンの計画において、その成否は最初の「借入額設定」で9割が決まると言っても過言ではありません。
ここで最も重要になるのが、金融機関が審査で算出する「借入可能額(借入限度額)」と、あなたの家庭が将来にわたって安定して支払いを続けられる「無理のない借入額」との間にある違いを正しく理解することです。
なぜ「借りられる額」と「返せる額」は違うのか?
この根本的な疑問を解き明かすには、住宅ローンを提供する「金融機関の視点」と、実際に生活を送る「あなたの視点」の違いを理解する必要があります。
金融機関の視点
金融機関が住宅ローンの審査で重視するのは、あなたの「生活の質」ではなく、あくまで貸したお金が返ってくる確率、すなわち「返済能力」です。
彼らが見ているのは、年収(額面)、勤務先の規模や安定性、勤続年数、個人の信用情報(過去の延滞履歴など)といった客観的なデータです。
これらの情報から「この人なら、毎月これくらいの返済までは滞納するリスクが低いだろう」という上限額を算出します。
極端な話、彼らにとっては、万が一返済が滞っても、購入した住宅という「担保」を売却すれば資金を回収できるという安心材料があります。
つまり、金融機関の提示する借入可能額とは、「あなたの生活を保障する金額」ではなく、「金融機関がビジネスとして許容できるリスクの上限」に過ぎないのです。
あなたの視点
一方、あなたが目を向けるべきは、税金や社会保険料が天引きされた後の、実際に銀行口座に振り込まれる「手取り年収」です。
そして、その手取り収入から、食費や水道光熱費、通信費といった日々の「生活費」、子どもの習い事や将来の学費といった「教育費」、生命保険や医療保険などの「保険料」、そして万が一に備えるための「貯蓄」や、人生を楽しむための「娯楽・レジャー費」をすべて差し引いて、初めて「住宅ローンに安心して回せる金額」が算出されます。
この、金融機関の審査では全く考慮されないリアルな生活コストの存在こそが、「借りられる額」と「返せる額」の間に大きなギャップを生む最大の原因なのです。
年収600万円の返済可能額シミュレーション
では、具体的に年収600万円の家計では、いくらまでなら無理なく返済できるのでしょうか。
リアルな数字でシミュレーションしてみましょう。
手取り月収の確認
年収600万円(ボーナス年2回・各2ヶ月分と仮定)の場合、所得税や住民税、社会保険料などが引かれた後の手取り年収は、扶養家族の有無で変動しますが、おおよそ458万円程度。
これを月収に換算すると約38万円となります。
1ヶ月の生活費モデルケース(夫婦+子ども1人世帯の場合)
- 食費:80,000円
- 水道光熱費:25,000円
- 通信費(スマホ・ネット):15,000円
- 保険料(生命・医療):20,000円
- 日用品・雑費:20,000円
- 教育費・習い事:20,000円
- 車両費(維持費・ガソリン代):20,000円
- こづかい(夫婦):40,000円
- 生活費 合計:240,000円
住宅ローンに回せる金額の算出
手取り月収38万円から、上記の生活費24万円を差し引くと、残りは14万円です。
しかし、この14万円のすべてを住宅ローン返済に充てるのは非常に危険です。
なぜなら、この中から将来のための「貯蓄(老後資金、教育資金の積立など)」や、急な出費に備える「予備費(冠婚葬祭、家電の買い替え、車の修理など)」を捻出しなければならないからです。
仮に、これらを合わせて月々4万円確保すると仮定すると、住宅ローンに安心して回せる上限額は「月々10万円程度」ということになります。
これが、年収600万円世帯にとっての「無理なく返せる額」の現実的なラインなのです。
「住宅ローン破綻」というリスク
もし、前述の家計シミュレーションを無視して、金融機関が提示する上限額(例えば返済負担率35%で月々約17.5万円)に近いローンを組んでしまったら、どのような未来が待っているのでしょうか。
これは決して大げさな話ではなく、現実に起こり得ることです。
当初は共働きや節約で何とかなるかもしれません。
しかし、子どもの成長と共に食費や教育費は確実に増加します。
塾や習い事の費用がかさみ、「うちにはそんな余裕はないから」と子どもの可能性を諦めさせなければならない場面が出てくるかもしれません。
大学進学の際には、多額の教育ローンや奨学金を子ども自身に背負わせることになり、その後の人生に大きな負担を残す可能性もあります。
家計は常に自転車操業となり、家族旅行や趣味といった心の潤いはなくなり、夫婦関係がギスギスすることも考えられます。
そんな状況で、もし変動金利が上昇したり、病気で収入が途絶えたりすれば、返済は即座に行き詰まります。
結果として、夢を持って手に入れたマイホームを自らの手で売却する「任意売却」や、強制的に家を追われる「競売」といった、最も避けたい事態に追い込まれるのです。
ネット上の口コミには、安易な借り入れで生活が苦しくなったという声も散見されますが、これはネット特有の目立ちやすい意見という側面もあります。
しかし、一部にそうした現実があることも事実であり、自らがそうならないための備えが不可欠です。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
借入可能額と返済負担率の基本

住宅ローンの審査プロセスにおいて、金融機関が最も重要視し、あなたの借入可能額を決定づける絶対的な指標、それが「返済負担率」です。
この数字は、あなたの年収に対して年間のローン返済額がどれくらいの割合を占めるかを示すもので、金融機関が「この人にお金を貸しても安全か」を判断するための、いわば身体測定のようなものです。
しかし、この一見シンプルな指標には、多くの人が見落としがちな「からくり」と「落とし穴」が隠されています。
審査で使われる「年収」は手取りではない
まず、返済負担率の計算式「年間返済額 ÷ 年収 × 100」で使われる「年収」が、税金や社会保険料が引かれる前の「額面年収」であるという事実を、強く認識する必要があります。
年収600万円の人が実際に生活費として使えるのは、手元に残る「手取り年収」です。
しかし、金融機関は審査の基準を統一するため、扶養家族の数など個々の状況で変動する手取り額ではなく、客観的な数値である額面年収を用います。
この差が、現実の家計感覚との間に大きなズレを生みます。
年収600万円の場合、手取り年収は概算で約458万円。
その差は実に約142万円にもなります。
多くの金融機関が年収600万円の返済負担率の上限を35%程度に設定していますが、これを計算してみましょう。
- 額面年収ベース(金融機関の審査):年収600万円 × 35% = 年間返済上限額 210万円(月々17.5万円)
- 手取り年収ベース(あなたのリアルな家計):この年間210万円の返済は、手取り年収458万円に対して、210万円 ÷ 458万円 × 100 = 約45.9%となります。
つまり、金融機関の審査基準である「返済負担率35%」でローンを組むということは、あなたの手取り収入の45%以上を返済に充てることに他なりません。
手取り月収約38万円のうち、17.5万円がローンで消え、残りの約20.5万円で家族全員の生活費、教育費、貯蓄、娯楽費のすべてを賄わなければならないのです。
この数字を見れば、額面年収ベースの返済負担率がいかに現実の生活感覚からかけ離れた、危険な水準であるかがお分かりいただけるでしょう。
「総返済負担率」に含まれる全ての借入
次に注意すべきは、返済負担率の計算に含まれる「年間返済額」は、これから借りる住宅ローンだけではないという点です。
金融機関が見ているのは、他のすべての借入を合算した「総返済負担率」です。
もし、あなたが住宅ローン以外に以下のような借入をしている場合、それらの年間返済額もすべて合算して計算されます。
- 自動車ローン(カーローン)
- 教育ローン
- カードローン、リボ払い、キャッシング
- スマートフォンの端末代金の分割払い
- 奨学金の返済
- その他、信販会社などを利用した分割払い(エステ、高額な家電など)
これらは、個人信用情報機関(CIC、JICCなど)にすべて記録されており、審査の際に金融機関は必ず照会します。
もし申告漏れがあれば、「虚偽申告」とみなされ審査に悪影響を及ぼす可能性すらあります。
例えば、月々3万円の自動車ローン(年間36万円)と、月々1.5万円の奨学金返済(年間18万円)がある場合、合計で年間54万円の返済がすでにあると見なされます。
この場合、年収600万円で返済負担率の上限が35%(年間返済上限210万円)だとすると、住宅ローンに充てられる年間返済額は、
「210万円 – 54万円 = 156万円(月々13万円)」
まで減少します。
見落としがちなスマホの分割払いなども、借入可能額を減らす要因となるため、住宅ローンの申し込み前には、ご自身の借入状況を正確に把握し、可能であれば完済して整理しておくことが、希望額の融資を受けるための重要な戦略となります。
審査で使われる「審査金利」とは
さらに、返済負担率の計算にはもう一つ、一般の消費者には知られていない重要な要素があります。
それが「審査金利(またはストレステスト金利)」の存在です。
あなたが広告や店頭で目にする「変動金利0.4%」といった金利は、実際にローン契約を結んだ後に適用される「適用金利」です。しかし、金融機関は審査の段階でこの金利を使いません。
なぜなら、変動金利は将来上昇するリスクがあるからです。
そのリスクに備えるため、金融機関は実際に貸し出す金利よりもはるかに高い、独自の「審査金利」(一般的に3%~4%程度)を設定し、この金利で計算しても返済負担率が上限内に収まるかどうかをチェックしているのです。
【年収倍率】からの借入額目安

住宅ローンの借入額を検討する際、多くの人がまず最初に参考にするのが「年収倍率」という指標です。
これは「物件価格 ÷ 年収」で算出される非常にシンプルな指標で、「自分の年収なら、大体これくらいの価格の家が買えるのか」という世間一般の相場観を手軽に知ることができるため、非常に重宝されています。
【データで見る】年収600万円世帯のリアルな購入物件価格
まず、実際に年収600万円の世帯は、どのくらいの価格の物件を購入しているのでしょうか。
住宅金融支援機構が公表している「2022年度 フラット35利用者調査」は、その実態を知る上で非常に参考になります。
| 住宅の種類 | 全国平均の年収倍率 | 年収600万円の場合の物件価格目安 |
| 新築物件 | ||
| 土地付注文住宅 | 7.7倍 | 4,620万円 |
| マンション | 7.2倍 | 4,320万円 |
| 建売住宅 | 6.9倍 | 4,140万円 |
| 中古物件 | ||
| マンション | 5.9倍 | 3,540万円 |
| 戸建 | 5.7倍 | 3,420万円 |
年収倍率が危険になり得る3つの理由
この便利な年収倍率ですが、使い方を間違えると非常に危険な判断基準となります。
理由1:金利の変動を無視している
年収倍率は、住宅ローン計画で最も重要な要素である「金利」を一切考慮していません。
これは最大の弱点です。
同じ年収倍率でも、金利が違えば月々の返済額、ひいては家計への負担度は全く異なります。
シミュレーション:年収600万円、年収倍率6倍(借入額3,600万円)、35年返済の場合
- 超低金利時代(金利0.5%): 月々の返済額は 約9.2万円
- 少し前の金利水準(金利2.0%): 月々の返済額は 約12.2万円
- 過去には当たり前だった金利水準(金利3.5%): 月々の返済額は 約15.8万円
ご覧の通り、金利が違うだけで月々の返済額は3万円~6万円以上も変わります。
年収倍率という「ものさし」そのものが、金利水準によって全く意味合いの異なるものになってしまうのです。
「昔の人は年収の7倍でも家を買っていた」といった話は、当時の金利や経済状況を抜きにしては語れません。
将来、金利が上昇する局面では、現在の感覚で年収倍率を当てはめるのは極めて危険です。
理由2:個人のライフプランや家族構成を考慮しない
年収倍率は、あなたの「年収」という一点しか見ていません。
しかし、同じ年収600万円でも、家族構成やライフプランによって住宅にかけられるお金は全く異なります。
- Aさん: 独身、30歳。自分のためだけにお金が使える。
- Bさん: DINKS(子どもなし共働き夫婦)、夫婦共に35歳。世帯収入は高く、比較的余裕がある。
- Cさん: 片働き、32歳、子ども2人(3歳と0歳)。これから教育費がどんどんかかってくる。
この3者が、同じ「年収倍率6倍(物件価格3,600万円)」の家を買ったとして、その家計へのインパクトは全く違います。
Aさんにとっては余裕のある買い物かもしれませんが、Cさんにとっては将来の教育費を圧迫し、家計破綻に繋がりかねない無謀な計画になる可能性があります。
年収倍率は、こうした個人の事情を全く反映しない、非常に大雑把な指標なのです。
理由3:「物件価格」の目安であり「借入額」の目安ではない
年収倍率が示すのは、あくまで「物件価格」の目安です。
しかし、あなたの返済計画の基盤となるのは「借入額」です。
この二つは、頭金の額によって大きく変わります。
- ケース1:頭金1,000万円|物件価格4,000万円(年収倍率6.7倍)→ 借入額3,000万円
- ケース2:頭金ゼロ(フルローン)|物件価格4,000万円(年収倍率6.7倍)→ 借入額4,000万円
同じ年収倍率の物件でも、頭金をしっかり用意できるケース1と、フルローンを組むケース2では、その後の返済負担は天と地ほどの差があります。
年収倍率だけを見て「このくらいの物件なら買えそうだ」と判断するのは早計です。
年収倍率の「賢い活用法」
これらを踏まえた上で、年収倍率は「絶対的な基準」としてではなく、あくまで「世間との比較を行うための、相対的なものさし」として活用するのが賢い使い方です。
- 初期段階での相場観の把握: 住宅探しを始める初期段階で、「年収600万円だと、大体みんなこれくらいの価格帯の物件を見ているんだな」という大まかな相場観を掴むために利用します。
- 自分の立ち位置の確認: あなたが検討している物件の年収倍率を計算してみて、それが平均(新築なら7倍前後、中古なら6倍前後)から大きく乖離していないかを確認します。
- 計画の妥当性を自問するきっかけに: もし、平均を大きく上回る年収倍率(例えば8倍超)の物件を検討しているのであれば、一旦立ち止まりましょう。そして、「なぜ自分たちは、平均よりもかなり高額なこの物件でなければならないのか?」「その負担増を吸収できるだけの特別な理由(潤沢な自己資金、将来の大幅な昇給見込み、親からの援助など)はあるか?」と自問自答するきっかけにするのです。
年収倍率は、あくまで住宅ローン計画のスタートラインに立つための「参考値」です。
この指標で大まかな当たりをつけたら、必ず次のステップである「あなたのリアルな家計に基づいた、手取りベースでの返済負担率の計算」に進まなければなりません。
この詳細な検証を抜きにして、年収倍率だけでGOサインを出すことだけは、絶対に避けるべきです。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
返済負担率から見る無理のない返済額目安

ここでは、「20~25%」という数字が絶対的な安全ラインなのか、そしてあなたのライフステージに合わせた最適な負担率をどう設定すべきかを、具体的なシミュレーションを交えて徹底的に解き明かしていきます。
「手取りの25%以内」が絶対的な安全ライン
「手取り収入の4分の1(25%)を住居費の上限とする」という考え方は、古くから家計管理の基本原則として知られています。
これは、長年の経験から導き出された、生活のバランスを崩さないための知恵の結晶です。
では、なぜ30%や35%ではダメなのでしょうか。
その理由は、手取り収入の使い道を分解してみると明確になります。
手取り収入100%の内訳(理想的なモデルケース)
- 住居費:25%
- 食費・日用品費:20%
- 水道光熱費・通信費:10%
- 教育費:10%
- 保険料・車両費など:10%
- 貯蓄(老後・教育・投資):10%
- 予備費・娯楽費:15%
このモデルを見てわかるように、住居費を25%に抑えることで、初めて「貯蓄」や「予備費・娯楽費」といった、人生の豊かさと安心感に直結する項目に十分な資金を割り振ることが可能になります。
ライフステージ別の目標返済負担率
同じ年収600万円でも、家族構成や年齢によって「無理のない」水準は異なります。
全員が同じ「25%」を目指すのではなく、ご自身の状況に合わせて目標を設定することが重要です。
- ケース①:【独身・DINKS(子どもなし共働き)】世帯 → 目標:25%以内
- ケース②:【子育て世帯(未就学児)】世帯 → 目標:20%以下
- ケース③:【子育て世帯(小学生~高校生)】世帯 → 目標:22%以内
【シミュレーション】手取り38万円の「現実的な借入額」
では、年収600万円(手取り月収約38万円)の世帯が、これらの目標返済負担率でローンを組んだ場合、借入額はいくらになるのでしょうか。
(金利0.5%、返済期間35年、元利均等返済で計算)
【超安全ライン】返済負担率19%(月々返済額 約7.2万円)
- 借入額目安:約2,700万円
- ある調査(ゼロリノベジャーナル)で「子ども1人の片働き世帯でも余裕を持てる」とされたのがこの水準です。将来の私立大学費用など、高額な教育費までしっかりと備えたい、何があっても絶対に家計を揺るがせたくない、という最も堅実な選択です。郊外であれば新築戸建も視野に入りますが、都心部では中古マンションなどが主な選択肢となるでしょう。
【理想的な安全ライン】返済負担率20%(月々返済額 約7.6万円)
- 借入額目安:約2,860万円
- 多くのFPが推奨する理想的な水準です。このラインを守れば、貯蓄や娯楽費にもきちんと資金を回し、バランスの取れた豊かな生活を送ることが可能です。
【許容できる上限ライン】返済負担率25%(月々返済額 約9.5万円)
- 借入額目安:約3,580万円
- これが、無理のない範囲での実質的な上限です。このラインを超えると、家計の柔軟性は失われ始めます。共働きで収入が安定している、当面は子どもの予定がない、といった家計に余裕のある世帯が、立地や物件の広さを優先する場合に検討できる上限値と捉えましょう。
具体的な返済シミュレーションとプランニング

頭で考えるだけでは、その選択がもたらす影響を実感することは困難です。
ここでは、具体的な数字を用いて、あなたの選択が35年後の未来にどれほど大きな違いを生むのかを可視化してみましょう。
パターン1:借入額による違い(金利0.9%、返済期間30年)
| 借入額 | 月々返済額 | 総返済額 | 手取り月収(38万)に占める割合 | 家計への影響度(解説) |
| 3,000万円 | 約9.6万円 | 約3,425万円 | 25.3% | 【安全圏】 1-3で解説した「手取りの25%」のラインをほぼクリア。貯蓄や教育費、娯楽費にも資金を回せる、最もバランスの取れた理想的な水準。 |
| 3,600万円 | 約11.5万円 | 約4,110万円 | 30.3% | 【要注意圏】 いわゆる「月10万円の壁」を突破。この水準から、家計の自由度は目に見えて低下し始める。共働き前提の計画となり、片方の収入が減ると一気に厳しくなる。 |
| 4,200万円 | 約13.4万円 | 約4,795万円 | 35.3% | 【危険水域】 手取りの3分の1以上がローンに消える。貯蓄はほぼできず、生活は「ローンのために働く」状態に。金利上昇や不測の事態への耐性が極めて低い。 |
パターン2:返済期間による違い(借入額3,000万円、固定金利1.82%)
| 返済期間 | 月々返済額 | 総支払額 | 支払う利息の総額 | 解説 |
| 35年 | 約9.7万円 | 約4,059万円 | 約1,059万円 | 月々の負担は最も軽いが、支払う利息の総額は1,000万円を超える。老後も返済が続くリスクがある。 |
| 30年 | 約10.9万円 | 約3,896万円 | 約896万円 | 月々1.2万円の負担増で、利息を163万円も節約できる。60歳定年なら完済も見えてくる現実的な選択肢。 |
| 25年 | 約12.5万円 | 約3,737万円 | 約737万円 | さらに月々1.6万円の負担増で、35年プランより利息を322万円も節約できる。この差額は、子どもの大学費用や車の買い替え費用に匹敵する。 |
パターン3:金利による違い(借入額3,600万円、返済期間35年)
| 金利 | 月々返済額 | 総支払額 | 0.5%との差額 | 解説 |
| 0.5% | 約9.2万円 | 約3,858万円 | – | 現在の変動金利の一般的な水準。しかし、この金利が未来永劫続く保証はない。 |
| 1.5% | 約10.8万円 | 約4,524万円 | +666万円 | 金利が1%上昇しただけで、総支払額は高級車1台分以上も増加する。月々の負担も1.6万円増え、家計を直撃する。 |
| 2.5% | 約12.5万円 | 約5,252万円 | +1,394万円 | 金利が2%上昇すると、支払う利息の総額はもはやマンションがもう一部屋買えるレベルに。変動金利を選ぶことの本当のリスクがここにある。 |
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
頭金はどのくらい用意すべきか

ここでは、頭金について、その効果をみていきます。
頭金がもたらす効果
頭金の効果は、単に借入額が減るという単純な引き算ではありません。
それは、将来にわたってあなたの家計に恩恵をもたらし続ける効果があります。
効果①:支払利息の劇的な削減
借入額が減れば、支払う利息も当然減ります。
その効果を具体的に見てみましょう。
シミュレーション:4,000万円の物件を購入する場合(金利0.5%、35年返済)
- ケースA(頭金ゼロ): 借入額4,000万円 → 月々返済約10.4万円 / 総支払額約4,363万円 / 総利息約363万円
- ケースB(頭金800万円): 借入額3,200万円 → 月々返済約8.3万円 / 総支払額約3,490万円 / 総利息約290万円
頭金を800万円入れることで、支払う利息の総額は約73万円も削減されます。
これは、最新の高級家電一式や、ちょっとした家族旅行数回分に相当する金額です。
効果②:「生活の自由度」向上
上記のシミュレーションで、月々の返済額は約2.1万円も軽くなっています。
この毎月生まれる2.1万円の余裕は、あなたの生活の質を劇的に向上させます。
この2.1万円で何ができるか?
- 子どもの習い事を一つ増やしてあげられる。
- 夫婦で月に一度、少しリッチな外食を楽しめる。
- 老後のために、積立NISAやiDeCoに全額を回し、資産形成を加速させられる。
- 家族の思い出を作るための旅行貯金ができる。
この「月々2万円の差」が、35年間続くのです。頭金は、未来の家計に継続的な「ゆとり」を生み出すための、最も確実な投資と言えるでしょう。
効果③:より有利な「ローン条件」の獲得
頭金の割合は、金融機関が提供するローン商品の金利そのものに影響を与えることがあります。
最も分かりやすい例が「フラット35」です。
フラット35では、物件価格に対する融資額の割合(融資率)が9割以下か、9割を超えるかで、適用金利が明確に分かれています。
融資率9割以下(=頭金1割以上)の方が、より低い金利で借りることができるのです。
これは、金融機関のリスクが低い顧客を優遇するという、当然の仕組みです。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
まとめ
この記事では年収600万円の住宅ローンについて解説してきました。
重要なことは、借りられる額と無理して返済できる金額には違いがあることです。
ぜひしっかりとした資金計画を行い、理想的な住宅ローンを組んでみてくださいね。
少しでもこの記事が参考になれば嬉しいです。



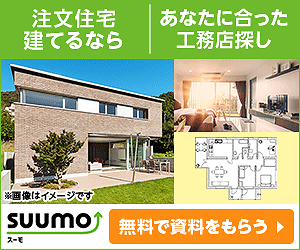




コメント