年収500万円は日本の平均的な収入水準に達し、多くの人が「そろそろ夢のマイホームを」と具体的な検討を始める、一つの節目となる年収帯です。
憧れの注文住宅、最新設備のマンション、自分好みに改装したリノベーション物件など理想の住まいを思い描きながら住宅ローンのシミュレーションを試した方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では年収500万円の人が借りられる金額から、無理なく返済できる金額、住宅ローンの注意点などを解説します。
ぜひ最後まで参考にしてみてください。
本文に入る前に、これから家づくりを考えている人や、現在進行形でハウスメーカー選びを進めている人に、後悔しない家づくりのための最も重要な情報をお伝えします。
早速ですが、質問です。
家づくりで一番大切なこと、それはなんだと思いますか?
おそらく間取りや予算、建てる場所などと考える人も多いかもしれませんね。
ですが実は、家づくりで最も大切なことは「気になっているハウスメーカーのカタログを、とりあえず全て取り寄せてしまうこと」なんです。
カタログを取り寄せずに住宅展示場に行き、営業マンの言葉巧みな営業トークに押されて契約を結んでしまうのは最悪なケース。
住宅展示場に行ってその場で契約をしてしまった人の中には、「もしもカタログを取り寄せて比較検討していたら、同じ間取りの家でも300万円安かったのに・・・」と後悔する人が本当に多いんです。
このように、もう少し情報収集をしていれば理想の家をもっと安く建てられていたのに、場合によっては何百万単位の損をして後悔してしまうこともあります。
だからこそ、きちんとした情報収集をせずにハウスメーカーを選ぶのは絶対にやめてください。
そんなことにならないようにハウスメーカーのカタログを取り寄せて比較検討することが最も重要なんです。

そうは言っても、気になるハウスメーカーはたくさんあるし、気になるハウスメーカー全てに連絡してカタログを取り寄せるなんて、時間と労力がかかりすぎるよ・・・
そう思う人も少なくありません。
そもそもどのように情報収集をしたら良いのかわからないという人もいるでしょう。
そんなあなたにぜひ活用してほしいサービスが、「ハウスメーカーのカタログ一括請求サービス」や「専門家に実際に相談してみること」です!
これらのサービスを活用することで、何十倍もの手間を省くことができ、損をするリスクも最大限に減らすことができます。
中でも、不動産業界大手が運営をしている下記の3つのサービスが特におすすめです。
|
東証プライム上場企業「LIFULL」が運営をしているカタログ一括請求サービスです。厳しい審査を通過した全国の優良住宅メーカーからカタログを取り寄せることが可能です。特にローコスト住宅に強いため、ローコスト住宅でマイホームを検討している人に非常におすすめです。 不動産のポータルサイトとしておそらく全国で最も知名度のあるSUUMOが運営しています。全国各地の工務店とのネットワークも豊富。住宅の専門家との相談をすることが可能で、住宅メーカー選びのみならず、家づくりの初歩的な質問から始めることが可能です。「何から始めたら良いのかわからない」と言う人はSUUMOに相談することがおすすめです。 上場企業でもあるNTTデータが運営しているサービスです。大手ということもあり、信頼も厚いのが特徴です。全国各地の大手ハウスメーカーを中心にカタログを取り寄せることができます。また、理想の家づくりプランを作ってもらえるのも嬉しいポイントです。 |
上記の3サイトはどれも完全無料で利用できる上、日本を代表する大手企業が運営しているため、安心して利用することができます。
また、厳しい審査基準で問題のある企業を事前に弾いているため、悪質な住宅メーカーに依頼してしまうというリスクを避けることも可能です。
正直言って、こちらの3サイトならどれを利用しても間違いはないでしょう。
また、どれを利用するか迷ったら、
- ローコスト住宅メーカーや大手ハウスメーカーを検討中:LIFULL HOME'Sでカタログ請求
- 工務店をメインで検討中:SUUMOカウンターで相談
- 資金計画や土地探しも相談したい:家づくりのとびら
というふうに使い分けてみるのもおすすめです。
そのほかに、SUUMOも無料カタログの一括請求サービスを提供しています。
こちらも無料なので、ぜひ利用してみることをおすすめします。
もちろんどのサービスも無料なため、全て活用してみるのもおすすめです。
後悔のない家づくりのため、1社でも多くの会社からカタログを取り寄せてみてくださいね!
\メーカー比較で数百万円得することも!/

【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる≫

【プロと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
家づくりで後悔しないために、これらのサービスをうまく活用しながら、ぜひあなたの理想を叶えてくれる住宅メーカーを見つけてみてください!
それでは本文に入っていきましょう!
住宅ローンの借入額の目安

年収500万円の方が住宅ローンを利用する際、「一体いくらまで借りられるのか?」という疑問に答えるには、まず「借入可能額は金融機関やローン商品によって大きく異なる」という大原則を理解する必要があります。
一般的に「年収の5倍から7倍」という目安がよく語られますが、これは非常に大雑把な指標に過ぎません。
実際には、金融機関が用いる独自の審査基準、特に「返済負担率」と「審査金利」という2つの重要なものさしによって、具体的な上限額が算出されます。
借入可能額を決める「返済負担率」とは
金融機関が融資額を決定する際に最も重視するのが「返済負担率(返済比率)」です。
これは、申込者の額面年収に占める、すべてのローンの年間合計返済額の割合を示す数値です。
計算式:年間総返済額 ÷ 額面年収 × 100 = 返済負担率(%)
多くの金融機関では、この返済負担率の上限を「30%~35%」の範囲で設定しています。
年収500万円の場合で考えてみましょう。
| 返済負担率35%の場合 年間返済上限額:500万円 × 35% = 175万円 月々返済上限額:175万円 ÷ 12ヶ月 = 約14.5万円 |
この月々約14.5万円という返済額から、金利や返済期間を基に借入可能額が逆算されます。
しかし、注意すべきは、この計算には住宅ローン以外のすべての借り入れが含まれるという点です。
自動車ローンや教育ローン、カードローン、さらにはスマートフォンの本体代金の分割払いなども合算して計算されるため、これらの借り入れが多いほど、住宅ローンに充てられる枠は少なくなります。
【金融機関別】借入可能額の算出方法の違いを比較
同じ年収500万円でも、申し込む金融機関によって借入可能額に数百万円単位の差が出ることがあります。
その最大の理由は、審査の仕組み、特に金利の考え方が異なるためです。
フラット35の特徴と借入可能額の考え方
住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する「フラット35」は、最長35年間の全期間固定金利が特徴です。
- 審査基準の明確さ: フラット35は、返済負担率の基準が「年収400万円未満は30%以下、年収400万円以上は35%以下」と明確に公開されています。この基準に沿って審査されるため、借入可能額の予測が立てやすいというメリットがあります。
- 金利の考え方: 審査では、実際に適用される金利(例:年1.96%)をそのまま用いて計算します。そのため、シミュレーション上では年収500万円で最大4,778万円(金利年1.48%、35年返済の場合)といった高額な借入可能額が算出されることがあります。
- 利用者の現実: しかし、これはあくまで制度上の上限値です。実際のフラット35利用者の平均借入額は年収の5倍弱(約2,500万円前後)に留まっています。これは、多くの人が、将来の金利変動リスクがない固定金利の安心感を選びつつも、上限額まで借りることのリスクを理解し、自己防衛的に借入額を抑えていることの表れと言えるでしょう。
民間金融機関の「審査金利」という壁
一方、メガバンクやネット銀行などの民間金融機関では、「変動金利」が主流です。
現在の超低金利下では、年0.3%台といった非常に魅力的な金利が提示されていますが、借入可能額の審査ではこの金利は使われません。
代わりに用いられるのが「審査金利(または査定金利)」です。
- 審査金利とは?: 将来の金利上昇リスクに備えるため、金融機関が独自に設定している審査用の高い金利のことです。実際の適用金利が0.3%台でも、審査では年3%~4%程度の金利で返済額が計算されます。
- なぜ審査金利を使うのか?: これは、もし将来金利が大幅に上昇しても、利用者が返済を続けられるかというストレステストを行うためです。銀行のリスク管理であると同時に、利用者が将来返済不能に陥るのを防ぐためのセーフティネットの役割も果たしています。
- 借入可能額への影響: この高い審査金利で計算するため、民間金融機関の借入可能額はフラット35のシミュレーション結果よりも低くなる傾向があります。SBI新生銀行の約3,750万円やauじぶん銀行の3,970万円といった目安額は、この審査金利を考慮した、より現実的な数値と言えます。つまり、適用金利の低さだけで「たくさん借りられる」と考えるのは早計なのです。
借入可能額を下げる要因
上記の返済負担率や審査金利に加え、個人の属性や購入物件の価値も借入可能額に影響を与えます。
- 個人の属性(信用力): 勤続年数が1年未満であったり、契約社員や個人事業主であったりすると、収入の安定性の観点から審査が厳しくなり、借入額が減額される、あるいはローンが組めない場合があります。
- 購入物件の担保評価: 金融機関は融資の対象となる不動産を担保とします。そのため、物件の価値(担保評価額)を算定し、その評価額が低い場合は、希望する融資額が承認されないことがあります。特に、築年数が古い中古物件や、再建築が難しい土地などは担保評価が低く出る傾向があるため注意が必要です。
このように、住宅ローンの借入可能額は、単一の指標ではなく、金融機関のルール、個人の経済状況、物件の価値など、複数の要素が複雑に絡み合って決定されることを理解しておきましょう。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
無理なく返せる住宅ローンの目安

住宅ローンの計画において、金融機関が提示する「借入可能額」はあくまでスタートラインに過ぎません。
本当に重要なのは、その金額ではなく、あなたの家族が将来にわたって「暮らしの質」を維持しながら、安心して支払い続けられる「無理のない返済額」を見極めることです。
この金額を基準に借入額を決定することが、住宅ローンで後悔しないための絶対的な鉄則と言えます。
年収500万円のリアルな可処分所得とは
資金計画を立てる際、絶対に間違えてはいけないのが、計算のベースにする年収です。
多くのシミュレーションでは「額面年収」を入力しますが、実際に私たちが自由に使えるお金は、税金や社会保険料が差し引かれた後の「手取り年収(可処分所得)」です。
年収500万円の会社員の場合、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料といった社会保険料と、所得税、住民税が給与から天引きされます。
これらの金額は扶養家族の有無などによって変動しますが、一般的に額面年収の約75%~85%が手取り額となります。
年収500万円(額面)の場合の手取り額シミュレーション
|
住宅ローンのような長期にわたる固定費を考える際は、この実際に口座に振り込まれる「手取り額」を基準にしないと、現実離れした過大な計画になってしまいます。
まずはご自身の給与明細を確認し、毎月の手取り額を正確に把握することから始めましょう。
「手取りの20~25%」の根拠
専門家の間で、無理のない返済負担率の目安としてよく挙げられるのが「手取り年収の20%~25%以内」という黄金比です。
なぜこの比率が推奨されるのでしょうか。
手取りの20%(理想ライン)
年収500万円(手取り400万円と仮定)の場合
- 年間返済額: 400万円 × 20% = 80万円
- 月々返済額: 約6.7万円
この水準であれば、子どもの教育費の増加や、不測の事態(病気や収入減)にもある程度の余裕を持って対応できます。
貯蓄や投資、レジャーなど、生活の豊かさを維持しやすい理想的なラインです。
手取りの25%(上限ライン)
年収500万円(手取り400万円と仮定)の場合
- 年間返済額: 400万円 × 25% = 100万円
- 月々返済額: 約8.3万円
このラインが、家計に大きな負担をかけずに返済を続けられる現実的な上限とされています。
これを超えると、少しの家計の変化で貯蓄が難しくなったり、生活費を切り詰めたりする必要が出てくる可能性が高まります。
この月々の返済額から、実際に借り入れできる金額を逆算してみましょう。
(金利1.5%、35年元利均等返済で試算)
- 月々6.7万円の返済: 借入額 約2,280万円
- 月々8.3万円の返済: 借入額 約2,830万円
この結果から、年収500万円の方が無理なく返済できる借入額の目安は、「2,300万円~2,800万円程度」であるという、より具体的な数字が見えてきます。
住宅ローンを上限額まで借りることのリスク

金融機関のシミュレーションで表示される「借入可能額」は、一見すると夢のマイホームを実現するための心強いパスポートのように思えるかもしれません。
「これだけ借りられるなら、少しグレードの高い物件にしよう」「せっかくだから希望をすべて詰め込みたい」と考えるのは自然な心理です。
しかし、この上限額は、あなたの未来の家計の安定性を保証するものでは決してありません。
減収のリスクに備える
住宅ローンの返済計画を立てる際、多くの人が無意識に「これからも給料は上がり続けるだろう」という楽観的なシナリオを描きがちです。
しかし、35年という長い返済期間中、収入が右肩上がりを続ける保証はどこにもありません。
共働き世帯の「世帯年収」という落とし穴
ペアローンや収入合算を利用して借入額を増やす場合、特に注意が必要です。審査の基準となる「世帯年収」は、夫婦二人の収入が継続することが大前提です。
しかし、妻の出産・育児によるキャリアの中断は、世帯収入に直接的な影響を与えます。
育児休業給付金は元の給与の満額が支給されるわけではなく、復職後も子育てとの両立のために時短勤務を選択すれば、収入は以前より減少します。
例えば、夫婦合算年収800万円(夫500万円、妻300万円)で上限ぎりぎりのローンを組んだ後、妻の収入が育休や時短で150万円に半減した場合、家計の返済負担率は一気に跳ね上がり、たちまち生活は苦しくなります。
会社の業績という自分ではコントロール不能なリスク
終身雇用や年功序列が当たり前ではなくなった現代において、会社の業績不振によるボーナスカットや給与の減額は、もはや他人事ではありません。
特に、毎月の返済額を抑えるためにボーナス払いを多めに設定している場合、ボーナスが削減されると返済計画は即座に破綻します。
病気や怪我による長期療養で、収入が途絶えるリスクも常に存在します。
将来の不確実性を無視し、「今の収入が続く」という前提だけで上限額のローンを組むのは、非常に危険な賭けなのです。
家計のブラックホール
住宅ローン返済以外にも、マイホームを維持するためには継続的なコストがかかります。
これらを「隠れコスト」と軽視し、予算に組み込んでいないと、想定外の支出に苦しむことになります。
可視化しにくい「維持・修繕コスト」
マンションであれば管理費や修繕積立金が毎月かかりますが、この修繕積立金は将来的に値上がりする可能性が高い項目です。
戸建ての場合は、自分自身で修繕計画を立て、資金を積み立てる必要があります。
例えば、10~15年周期で必要になる外壁・屋根の塗装には100~200万円、給湯器の交換には20~40万円、その他にもエアコンの買い替えや水回りのメンテナンスなど、突発的な高額出費が待ち構えています。
これらの費用を考慮せずにローン返済額を設定すると、いざという時に貯蓄が足りず、追加でリフォームローンを組むといった悪循環に陥りかねません。
無限に膨らむ「子どもの教育費」
子どもの成長は喜びであると同時に、家計への大きなプレッシャーとなります。
「高校入学から大学卒業までで子ども1人あたり約1,000万円」というデータは有名ですが、これはあくまで平均値です。
もし子どもが私立の大学(特に理系や医歯薬系)に進学すれば、費用はさらに跳ね上がります。
塾や習い事、留学など、親として「できる限りのことをしてあげたい」と思えば、教育費は青天井になりがちです。
ローン返済で家計がカツカツの状態では、子どもの進路の選択肢を狭めてしまう可能性すらあるのです。
金利上昇のリスク
現在の超低金利時代において、変動金利は非常に魅力的に映ります。
しかし、その裏には金利が上昇した際に家計を直撃する大きなリスクが潜んでいます。
「5年ルール」「125%ルール」は救済措置ではない
多くの変動金利ローンには、返済額の急激な変動を緩和するための「5年ルール(5年間は毎月の返済額が変わらない)」や「125%ルール(見直し後の返済額は、従前の1.25倍が上限)」といった仕組みがあります。
しかし、これは単なる一時しのぎに過ぎません。
このルールが適用されている間も、水面下では市場金利に合わせて利息の計算は行われています。
もし金利が大幅に上昇した場合、毎月の返済額を利息額が上回ってしまうことがあります。
この、支払いきれなかった利息は「未払い利息」として繰り延べられ、ローンの最終回にまとめて請求されたり、元本に上乗せされたりします。
元本が減らない
未払い利息が発生すると、毎月ローンを返済しているにもかかわらず、元本が全く減らない、あるいは未払い利息のせいで元本が増えてしまうという恐ろしい事態に陥る可能性があります。
上限額まで借り入れていると、この金利上昇の影響をまともに受けることになり、返済計画は根底から覆されます。
ローンに縛られ人生の選択肢を失うリスク
上限額での借り入れがもたらす最大のリスクは、お金の問題だけにとどまりません。
それは、あなたの「人生の自由度」を奪うことにも繋がります。
返済のために家計に余裕がなくなると、自己投資(スキルアップのための学習や資格取得)や、将来のための資産形成(iDeCoやNISAなど)に回す資金がなくなります。
その結果、キャリアアップの機会を逃したり、老後資金に不安を抱えたりすることにもなりかねません。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
無理なく住宅ローンを組むためのポイント

これまでの章で、住宅ローンに潜む様々なリスクについて解説してきました。
しかし、それは決して「家を買うべきではない」という結論に繋がるわけではありません。
リスクを正しく理解し、それに対する具体的な対策を講じることで、住宅ローンはあなたの人生を豊かにする強力なツールとなり得ます。
【ポイント1】頭金戦略
頭金を用意することは、無理のない住宅ローン計画における最も基本的かつ効果的な戦略です。
単に借入額を減らすだけでなく、金融機関からの信用を高め、より有利な条件を引き出すための重要な鍵となります。
金利優遇を引き出す
頭金の最大のメリットの一つが「金利優遇」です。
特にフラット35では、物件価格に対する借入額の割合である「融資率」が9割以下の場合、9割を超える場合に比べて適用金利が約0.2%も低く設定されます。
例えば、3,000万円の物件を購入するケースで考えてみましょう。
- 頭金なし(融資率100%): 借入額3,000万円、金利1.8%、35年返済 → 総返済額 約4,047万円
- 頭金300万円(融資率90%): 借入額2,700万円、金利1.6%、35年返済 → 総返済額 約3,490万円
この場合、頭金を1割(300万円)入れるだけで、総返済額は約557万円も少なくなります。頭金の効果は、単に入れた金額以上に、将来の利息負担を劇的に軽減する力を持っているのです。
「貯金の全額投入」はNG
金利優遇のメリットが大きいからといって、貯金のすべてを頭金に注ぎ込むのは絶対に避けるべきです。
住宅購入時には、頭金とは別に物件価格の3~9%程度の諸費用(登記費用、ローン手数料、印紙税など)を現金で支払う必要があります。
さらに重要なのが、万が一の事態に備える「生活防衛資金」です。
これは、病気や失業などで収入が途絶えた場合でも、当面の生活を維持するためのお金で、一般的に生活費の半年から1年分が目安とされています。
この生活防衛資金と諸費用を確保した上で、残った余裕資金を頭金に充てる、という順番を間違えないようにしましょう。
【ポイント2】「完済年齢」から逆算する
返済期間の選択は、月々の返済額だけでなく、あなたの老後設計そのものに直結する重要な決断です。
多くの金融機関では最長35年でローンを組めますが、安易に最長期間を選ぶのは危険です。
「長期ローン+繰り上げ返済」という選択肢
一つの賢い戦略として、「返済期間は最長の35年で組み、余裕ができた資金で積極的に繰り上げ返済を行う」という方法があります。
- メリット: 最初は長期で組むことで月々の返済額を低く抑え、家計に余裕を持たせることができます。これにより、子育て期間中の急な出費や、貯蓄・投資に資金を回すことが可能になります。そして、ボーナスや昇給で資金に余裕が生まれたタイミングで「期間短縮型」の繰り上げ返済を行えば、当初の予定より早く、かつ総返済額を抑えてローンを完済することができます。
- 注意点: この戦略は、繰り上げ返済を計画的に実行する強い意志が必要です。また、繰り上げ返済には手数料がかかる場合があるため、事前に確認しておきましょう。
危険な返済計画
最も重要なのは「完済時年齢」です。理想は、定年退職を迎える60歳や65歳までに完済する計画を立てることです。
退職後もローン返済が続くと、年金収入の中から返済を続けることになり、老後の生活を著しく圧迫します。
「最後は退職金で一括返済すればいい」と安易に考えるのは危険です。
会社の業績や制度変更により、想定していた退職金がもらえない可能性もありますし、そもそも退職金は大切な老後の生活資金です。
これをローン返済に充ててしまうと、豊かなセカンドライフが送れなくなる本末転倒な事態になりかねません。
【ポイント3】金利タイプを見極める
金利タイプにはそれぞれ一長一短があり、どれが絶対的に正しいという答えはありません。
経済的な合理性だけでなく、ご自身のライフプランやリスクに対する考え方(性格)に合わせて選ぶことが重要です。
変動か固定か?
- 変動金利が向いている人: 当初の金利の低さは最大の魅力です。金利上昇リスクに対応できるだけの貯蓄がある人、共働きで収入に余裕がある人、または将来的に繰り上げ返済で短期完済を目指している人に向いています。
- 全期間固定金利が向いている人: これから子どもの教育費が増えるなど、将来の支出増が明確に決まっている人、金利の動向に一喜一憂したくない安定志向の人に最適です。返済計画が立てやすく、精神的な安心感が得られます。
- ミックス型が向いている人: 変動と固定のどちらか一方に絞り切れない場合、両方を組み合わせることでリスクを分散できます。ただし、仕組みが複雑で、金利の動向を常にチェックする必要があるため、ある程度金融知識がある人向けの選択肢と言えます。
【ポイント4】資金計画の精度
住宅ローンの返済計画は、物件価格とローン金利だけで考えてはいけません。
購入時と購入後に発生する「見えないコスト」をすべて洗い出し、予算に組み込むことで初めて、現実的な資金計画が完成します。
FPに相談
将来の家族計画(子どもの人数や進学プラン)、キャリアプラン、車の買い替え、親の介護などを時系列で書き出し、それに伴う収入と支出を一覧にした「キャッシュフロー表」を作成することを強く推奨します。
これにより、人生のどのタイミングでどれくらいのお金が必要になるかが「見える化」され、漠然とした将来の不安が具体的な課題に変わります。
自分たちで作るのが難しい場合は、中立的な立場のファイナンシャルプランナー(FP)に相談するのも有効な手段です。
諸費用と維持費を足した「真の住居費」で考える
月々のローン返済額だけでなく、以下の費用も合算した「真の住居費」で家計を管理しましょう。
- 税金: 固定資産税・都市計画税(年間10~15万円程度)
- 保険料: 火災保険・地震保険料
- 維持費: マンションの管理費・修繕積立金(月平均2.4万円程度)、戸建ての将来の修繕積立(月1~2万円程度)
これらの費用を月割りにしてローン返済額に上乗せした金額が、手取り月収の20~25%に収まるかどうかをチェックすることが、無理のない計画を立てるための試金石となります。
【ポイント5】審査を有利に進める最終準備
理想の物件が見つかったら、万全の状態で住宅ローン審査に臨みたいものです。
最後に、審査を有利に進めるための最終チェックポイントを確認しましょう。
共働き夫婦が知るべき「ペアローン」と「収入合算」の違い
共働き世帯が借入額を増やす方法として、「ペアローン」と「収入合算」があります。
- ペアローン: 夫婦それぞれが主債務者としてローン契約を結ぶ方法。それぞれが住宅ローン控除を使えるメリットがありますが、契約が2本になるため諸費用が割高になるデメリットも。
- 収入合算: どちらか一方が主債務者となり、もう一方の収入を合算する方法。「連帯保証」と「連帯債務」があり、「連帯債務」の場合は2人とも住宅ローン控除の対象となります。
離婚時の手続きの煩雑さなども含め、それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご自身の家庭に合った方法を選びましょう。
信用情報のクリーンアップ
住宅ローンの審査では、個人の信用情報が必ずチェックされます。
スマートフォンの分割払いの支払遅延や、クレジットカードのキャッシング、カードローンの利用履歴などもすべて「総返済負担率」に影響します。
審査に申し込む前に、不要なクレジットカードを解約したり、完済できるローンは済ませておいたりするなど、ご自身の信用情報をできるだけクリーンな状態にしておくことが、スムーズな審査通過のための重要な一手となります。
\家づくりで「何から始めたらわからない」と感じるあなたへ/
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sでカタログ一括請求してみる≫
【初心者におすすめ】スーモカウンターで相談から始めてみる≫
↓↓全国から31社を厳選!
【2025年最新】おすすめハウスメーカーランキングはこちら≫
まとめ
この記事を通じて、年収500万円での住宅ローン計画における様々な側面を深掘りしてきました。
本当の意味で成功する住宅ローン計画とは、「借りられる額」ではなく「無理なく、安心して返し続けられる額」を基準に、自分自身の人生設計図から逆算して組み立てるものです。
それは、ご自身の「手取り収入」を正確に把握することから始まり、将来の昇給という不確かな期待よりも、育児や介護、そして自身の老後といった、これから確実に訪れるライフイベントのための支出を優先的に確保することで実現するでしょう。
ぜひこの記事の内容も参考にしながら、理想的な住宅ローン計画を進めてみてくださいね。



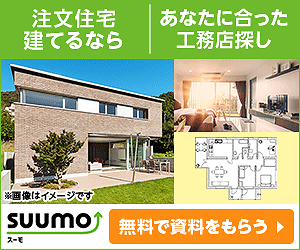




コメント