施設探しのご相談は24時間365日可能!
0120-469-448
※施設へはつながりません。施設の電話番号等の案内は承っておりませんので
入居相談以外のお問い合わせはご遠慮ください。
MENU
まごころ介護のお役立ち動画コラム
MAGOCORO MOVIE COLUMN
当サイトでは、動画の内容を加筆・編集して作成しています。
【在宅看取り】ケアマネと医療連携の役割と苦悩
近年、在宅での看取りを選択する家庭が増えてきています。
ケアマネージャーは、在宅で最期を迎える方とその家族を支える重要な存在です。
制度の壁や医療との連携の難しさに直面しながらも、日々奮闘しています。
本記事では、在宅看取りにおけるケアマネージャーの役割や医療との連携、グリーフケアの重要性について詳しく解説します。
在宅看取りにおいて、ケアマネージャーは単なる介護プランの作成者ではありません。
訪問診療医や訪問看護師、ヘルパーと連携しながら、利用者と家族が最期の時間を穏やかに過ごせるよう支援します。
特に、末期がんや進行性の難病の場合、医療と介護の連携は欠かせません。
ケアマネージャーは、医療機関と介護サービスの調整を行い、スムーズな支援ができるようコーディネートする役割を担います。

介護保険制度では、新規申請から認定が下りるまで約1カ月かかります。
この間、仮のケアプランを作成できますが、認定結果が予想より軽度になると、サービスの利用調整が必要になることもあります。
また、介護保険では利用できるサービスが制限されており、必要なケアを十分に提供できないケースも少なくありません。
例えば…
末期がんの方が在宅で看取られる場合、24時間対応の医療・介護が必要になるが、保険適用の制限がある
軽度認定を受けた利用者に対し、実際には重度のケアが必要でも、サービス提供が難しい
認定を待っている間に症状が悪化し、必要な支援が間に合わない
このような状況の中で、ケアマネージャーは利用者と家族に寄り添いながら、最善の方法を模索し続けています。

かつて、介護職は医療職に比べて低く見られることがありました。
しかし、現在は在宅医療の普及に伴い、医師や看護師とケアマネージャーが対等な立場で話し合う場面が増えています。
実際に、医療従事者から「この方はどんな生活を送っていたのか?」と質問される機会も増えており、介護の視点からの情報提供が重要視されるようになってきました。
それでも、医療との連携に苦労するケアマネージャーは少なくありません。
特に、病院からの情報提供が十分でない場合や、医師が利用者や家族の希望を十分に聞かずに治療方針を決定する場合、ケアマネージャーが間に立って調整する必要があります。
在宅で看取りを進める中で、利用者の人生や価値観を大切にすることが求められます。
そのためのツールとして「エンディングノート」の活用が注目されています。
エンディングノートとは、自分の人生の最終段階や死後の希望、個人情報、財産状況などを記録したノートのことです。法的拘束力はありませんが、残された家族や関係者が故人の意思を尊重し、適切な対応を行うための指針となります。
エンディングノートには、以下のような内容を記録できます。
これまでの人生で大切にしてきたこと
最期をどのように迎えたいか
死後の手続き(葬儀、供養、財産管理など)
エンディングノートを作成し、病院やホスピスへ引き継ぐことで、利用者の意思を尊重したケアが可能になります。
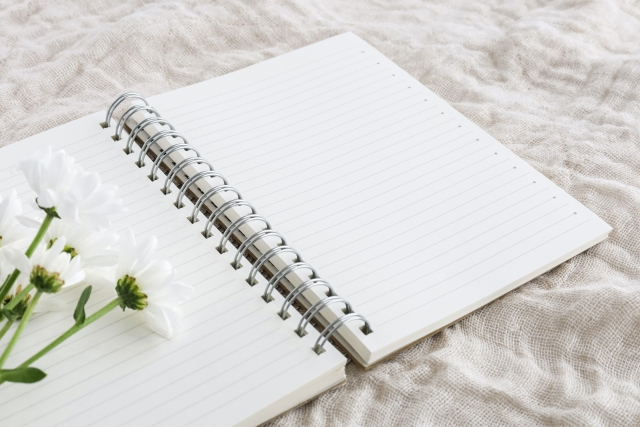
看取りの後、家族は深い悲しみ(グリーフ)を抱えることが多いです。
「グリーフケア」とは、愛する人を失った遺族が抱える深い悲しみや喪失感に寄り添い、再び日常生活に適応できるよう支援することを指します。
このケアは、遺族の感情や行動を否定せず、受け入れることが重要です。
グリーフケアは、人生の危機を回復へと導く力となり、自分自身や死、そして故人について深く問いかける機会を提供します。
具体的な支援方法としては、以下のような支援を行っています。
遺族向けのサポートグループの紹介
カウンセリングや電話相談の案内
地域のグリーフケアサービスの情報提供
近年、全国各地でグリーフケアを専門とする団体や医療機関が増えてきています。
ケアマネージャーとしても、これらの情報を把握し、必要な家族に適切に紹介できるよう準備しておくことが重要です。

在宅看取りにおいて、ケアマネージャーは単なる調整役ではなく、「利用者の想いを繋ぐ架け橋」としての役割を果たしています。
医療とのスムーズな連携が大切
エンディングノートの活用で、最期の希望を尊重
看取り後の家族に寄り添うグリーフケアの重要性
今後、在宅看取りの需要が高まる中で、ケアマネージャーの支援体制の強化が求められています。
\ 福祉の福ちゃんが講師を務める「介護・福祉セミナー」を開催しています /
監修

公開日:2025年1月29日 更新日:2025年2月6日
24時間365日 通話料無料でご相談